学び!と美術
学び!と美術
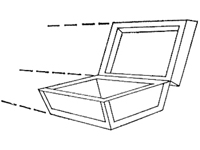
教育の基盤である「子ども」について語る上で、文化という視点は重要です。本稿では、写真や絵と錯覚の問題を取り上げて私たちが優れて文化的な生き物であることについて考えてみましょう(※1)。
写真はありのまま?
写真はありのままを写しません。例えば、風光明媚な観光地に行ったときがそうです。目の前の山が屏風のように立ちはだかっていたのに、撮った写真を後から見ると「あれ?こんな感じだったかな」と思います。私は富士山が好きなので、よく撮影するのですが、あのするどい「高さ」はどうにも写真に現れません。
精神科医で現象学者のヴァン・デン・ベルクも、写真は、地面に平行なはずの直線、つまり私たちが水平だと思っている線が全て曲がっていたり、斜めだったりしており、「日常生活から一番遠い」と述べています(※2)。
私たちは地面が、道路が、机が平らだと感じています。立体の中にいて、空間を感じながら生きています。写真は、それを無理やり平面に置き換えます。廊下の直線は「斜め」になり、四角い机は「矩形」になります。でも、私たちは、廊下を斜めにとらえて歩いてはいませんし、机は四角く、水平なままです。写真の「表象」は、私たちが身体的に感じる世界と根本的に異なっています。「写真がありのままを写す」という考え方があるとしたら、それは「写真が私たちの感覚と同じだ」ととらえる思い込みでしょう。
写真は読むもの
昔の人が写真を「読めなかった」ことを示す記述は複数あります。
例えば、中川作一は、視覚文化が十分入り切っていない地域で、人々が戸外の風景写真の奥行きが読めなかった事例を紹介しています。そして「おそらく、子どものころ、彼らの知覚が視覚文化の影響を受けない環境で育てられたためだろう」(※3)と述べています。
写真家の東松照明も似た事例を報告しています。東松は1972年に沖縄の宮古島に移住、周辺の島々も含め様々な人々の写真を撮影します。彼は律儀な人で、撮影した写真は現像して本人宛に郵送したり、直接本人に持参したりしていました。その際「ときに面食らうこと」があったようです。以下の記述はあるオバアに持参したときの話です。
「礼をいって写真を渡すと、老婆は、生娘のごとくからだをくねらせて恥ずかしがる。老婆は食い入るようにして写真を眺める。何分も、ずーっと姿勢を崩さずに見つづける。変だな、と思ってのぞき込むと、老婆は、写真を上下逆さにしてみているのだ。
信じられない話だが、息子さんに質すと、前にも同じようなことがあったという、横の写真を縦にして見ていた、と。(※4)」
オバアの年齢は書いてありませんが、おそらく1880年前後の生まれだと思われます。テレビや写真が豊富に入り込んできたのも、オバアが70歳近くになってからでしょう。視覚文化の影響を受けなかったオバアにとって、白黒写真を読むことは難しかったようです。
文化的な錯視としての透視図法
透視図法は一種の錯視です。錯覚は物理的、生理的だけでなく、文化的な原因によっても起こります。
中川が紹介するのは、明治初期の人が透視図法で描かれた絵を正しく認識できなかった事例です。洋画家の牧野義男の父親は、国定教科書に描かれた正確な透視図法による四角い箱の絵を見て次のように言ったそうです。
「何だ?この箱は確かに四角じゃない。わしにはひどくいびつに見えるぞ(※5)」
 牧野義男は1870年生ですので、父親の言葉が発せられたのは、おそらく1880年(明治13年)前後のことでしょう。江戸生まれの父親は、透視図法で描かれた図を「正しい」絵だと知覚できなかったのです。
牧野義男は1870年生ですので、父親の言葉が発せられたのは、おそらく1880年(明治13年)前後のことでしょう。江戸生まれの父親は、透視図法で描かれた図を「正しい」絵だと知覚できなかったのです。
しかし、9年後に彼は真逆のことを言います。同じ図画の本を見ながら、彼を呼んで「妙なものだ。この四角い箱は、いびつだと思ったものだが、今は真四角に見える」といったのです。江戸時代に生まれた人が、当初は透視図法を受け入れられなかったこと、それが明治時代になってから変化したことが分かる記述です。
 線遠近法との効果で錯視を起こす有名なミュラー=リヤーの図(右図)も、世界的に見れば錯視を起こす率が異なり、特に西洋文化が到達していない地域では錯視を起こさなかったとする報告もあります(※6)。
線遠近法との効果で錯視を起こす有名なミュラー=リヤーの図(右図)も、世界的に見れば錯視を起こす率が異なり、特に西洋文化が到達していない地域では錯視を起こさなかったとする報告もあります(※6)。
ミュラー=リヤーの錯視の原因は「内向き、外向きの矢が、透視図的な見方を促進する」「矢によって電気生理学的な作用が起きる」など言われていますが、そもそも長さを測るということ自体が、かなり文化的な実践です。
 例えば、北村、川村らは、日本人は周囲との関係で長さを目測する傾向があるのに対して、西洋文化圏の人々が、長さそのものをとらえようとする傾向があること、さらに、西洋文化圏から日本に来た留学生が、日本的な測り方をするようになることを心理学的な実験から指摘しています(※7)。
例えば、北村、川村らは、日本人は周囲との関係で長さを目測する傾向があるのに対して、西洋文化圏の人々が、長さそのものをとらえようとする傾向があること、さらに、西洋文化圏から日本に来た留学生が、日本的な測り方をするようになることを心理学的な実験から指摘しています(※7)。
さて、子どもはどうだ?
哲学者のメルロ・ポンティは「知覚において私の所有しているのは物それ自体であって表象ではない(※8)」と語っています。写真、透視図などは文化的に生み出されたまぎれもない「表象」です。私たちが感じている世界は「それ自体」です。写真、透視図などは「表象」であり、それを見ることは、すぐれて文化的な実践だろうと思います。
子どもたちはどうなのでしょう。年齢によって異なりますが、少なくとも、私たちの文化や見方には染まり切っていません。おそらく、多くの子どもたちは、私たちの文化や見方とせめぎ合っている状態だと思います。一方で、現代の子どもたちが、昔の子どもたちと同じだと考えることも危険でしょう。牧野の父親やオバアと異なり、子どもたちは、0歳児の頃から視覚文化の影響に浸っているのです。
絵を描く、写真を撮るなど、図画工作や美術の教育では、当たり前のように行われている実践です。その当たり前を、文化的なまなざしから問い直すことは大事なことかもしれません(※9)。
※1:本稿は、奥村高明著「マナビズム 「知識」は変化し、「学力」は進化する」東洋館出版 2018(印刷中)第2章を加筆したものです。
※2:ヴァンデン・ベルク著 立教大学早坂研究室訳「現象学の発見 歴史的現象学からの展望」勁草書房 1988、6-9p
※3:中川作一著「目と絵の社会心理学」法政大学出版局 1984、74p
※4:東松照明著「新編 太陽の鉛筆」赤々舎 2015、50p
※5:前掲書2、62p
※6:広い平原に暮らす環境要因、紙のような平面画像に慣れないため、矢の部分と軸の部分を切り離して見る能力が優れていたためなど様々な理由が指摘されている。
※7:Shinobu Kitayama, Sean Duffy, Tadashi Kawamura, Jeff T. Larsen “Perceiving an Object and Its Context in Different Cultures A Cultural Look at New Look” Psychological Science 2003 pp.201-206
※8:M.メルロ=ポンティ著 滝浦静雄・木田元共訳「見えるものと見えないもの」みすず書房 1989、16p
※9:40年近く前の話になりますが、私が受け持った中学生に、どうしても透視図法が描けない子どもがいました。他のすべては優秀な子どもだったので、当時「なぜ描けないのか」と、ずいぶん叱った思い出があります。もう少しやさしい言葉がかけてあげればよかったと、今は思います。