
|
日文の教育情報 No.15
|
平成16年11月 発行
|
|
|
|
●研究発表大会で
今年の秋は、ずいぶんたくさんの研究発表大会に呼んでいただいた。
研究授業のあと、指導講師をしたり、記念講演をしたり、パネルディスカッションに参加したりした。
おかげで、いろんな授業を見ることができた。
千差万別、ピンからキリまでの授業に出あった。
授業を見ていて、共通した傾向があるように思えた。
「授業は、前から見るもんや」
というのが、私の持論である。教室の前から子どもたちの表情を見ると、その授業が生きているのか、死んでいるのかがすぐ分かるからである。
子どもの目を見ていると、子どもの気持ちが読める。
授業に参加している子どもの目は、黒板を見たり、教科書を見たり、先生を見たりして同じように動く。
ところが、皆と違う方向を見ている目がある。
皆が前を向いている時に、下を向いていたり、皆が下を向いている時に窓の方を向いている目がある。
授業に参加していない目である。
そういう目が増えてきているように思えてならない。
明らかに、子どもの気持ちと先生が教えようとしていることとの間にミスマッチが起こっている。
●ミスマッチの原因
「どうしたら、子どもはこっちを向いてくれるのだろうか」
「教科書の内容をこれだけ工夫して、分かりやすく説明しているのに・・・」
と先生たちは悩む。
どこかで、すれ違いが起こっている。
下図は「学力の構造図」である。
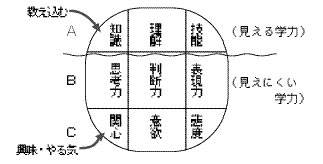
授業中の目線が別のところにある子どもたちの多くは、学力のCの部分で、興味もやる気もなくしている状態にある。
ところが、先生たちの多くは、学力のAの部分で頑張って「分かりやすく教えよう」と力を入れている。
何の興味も関心ももたない子どもに、知識・理解・技能のAの学力を教え込もうとしても、嫌がる馬にむりやり、水を飲ませようとしているのと似ている。
先生たちがまず工夫しなければならないのは、Cの学力ではないのか。
「どうすれば、子どもの興味や、やる気を引き出すことができるのか」
ということが、教材研究の最初に必要なことである。
例えば、算数の「大きな数」を扱う時に、校長先生の顔が印刷された1万円札や千円札の札束を配って考えさせている授業も参観したが、子どもたちは乗っていた。
●「貯める学力」より「使う学力」
ミスマッチの2つ目は、私たち教師の多くは、学力とは貯めるものという意識が強いことにある。
「まず、知識を貯めなければ使うこともできない」と思っている。
雪だるまを作るには、雪をたくさん貯めなければ作れないと考えている。
ところが、子どもたちは握りこぶし程度の雪で、転がしたり雪合戦をしたり、雪を使って遊びながら雪だるまを楽しく作ってしまう。
学力とは、使っているうちに貯まっていくものなのである。
A→B→Cという学び方もあるが、C→B→Aという学び方もある。
言葉を変えれば、偏差値で表されるAの学力に重点を置きすぎると、子どもの生活や体験から離れたものになりやすい。
偏差値よりも経験値を大切にする、生活や体験に根ざしたところからの学びは、子どもたちの興味・関心を呼び起こし自ら学ぶ力につながっていく。
学力を高めるエンジンの役目は、Cの学力が荷っている。
偏差値学力は時間がたつと忘れてしまい剥落するが、経験値学力はなかなか剥落しないで身についていく。
著者経歴
元大阪府堺市教育長
元大阪府教育委員会理事 兼教育センター所長
元文部省教育課程審議会委員
|