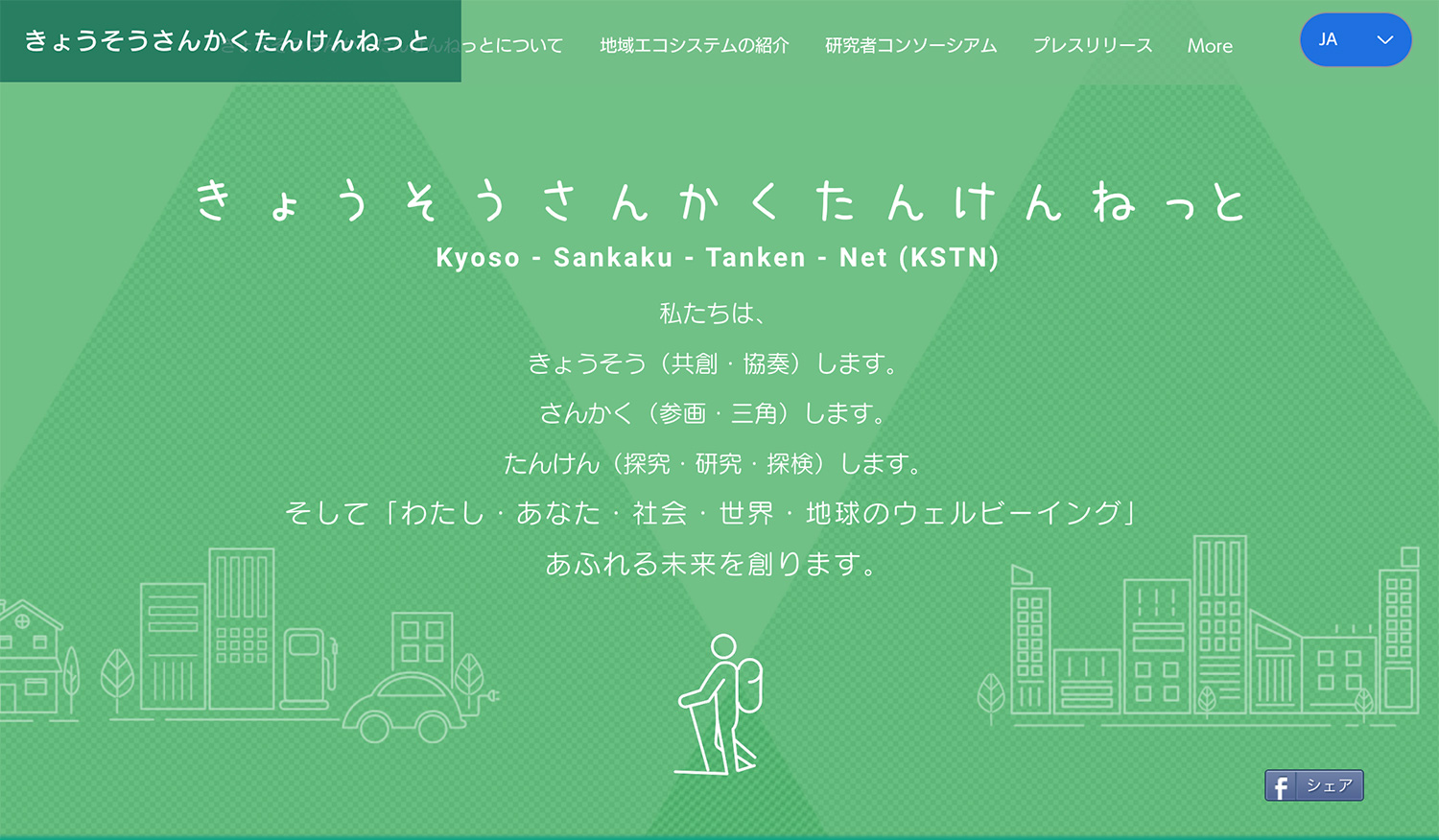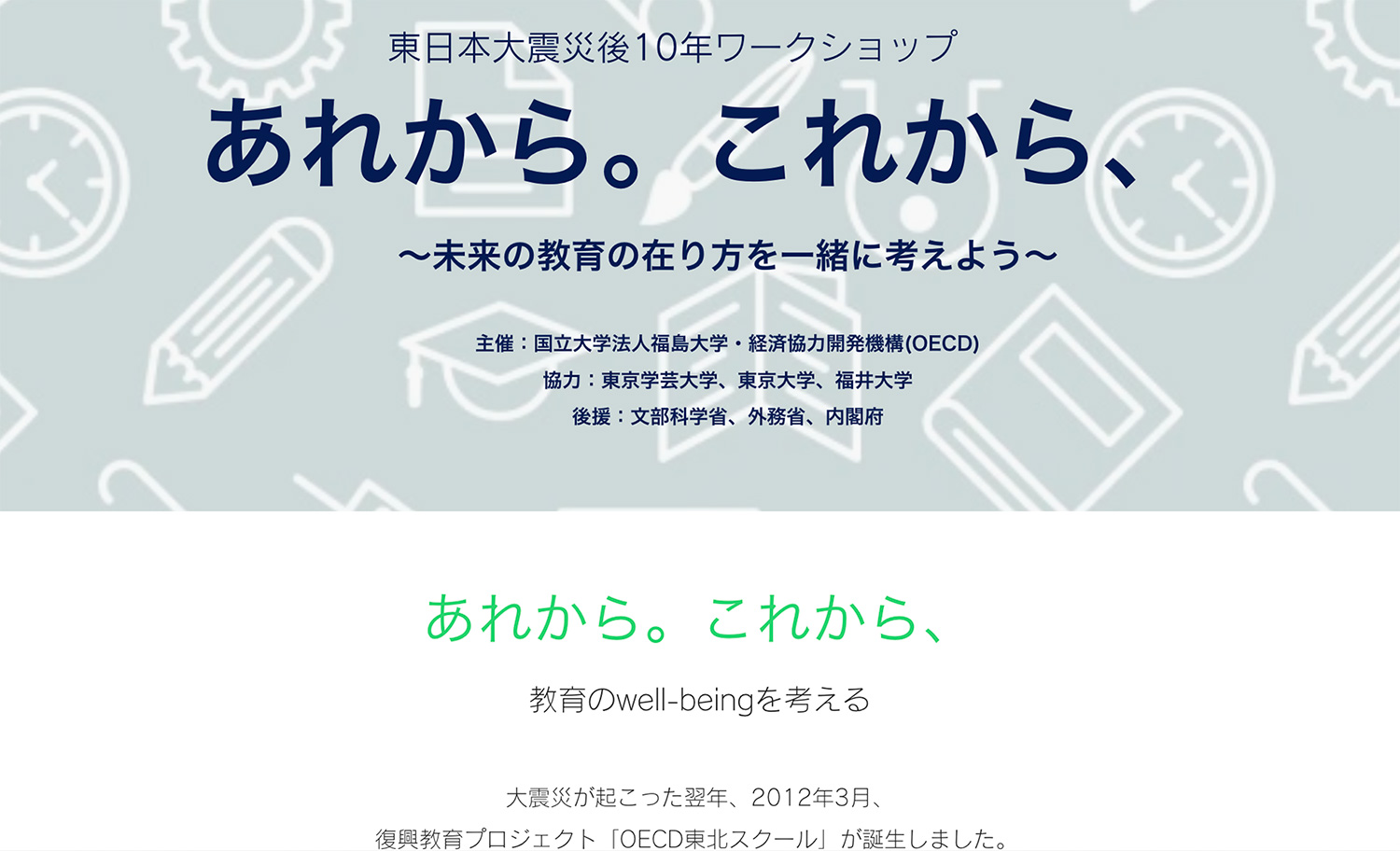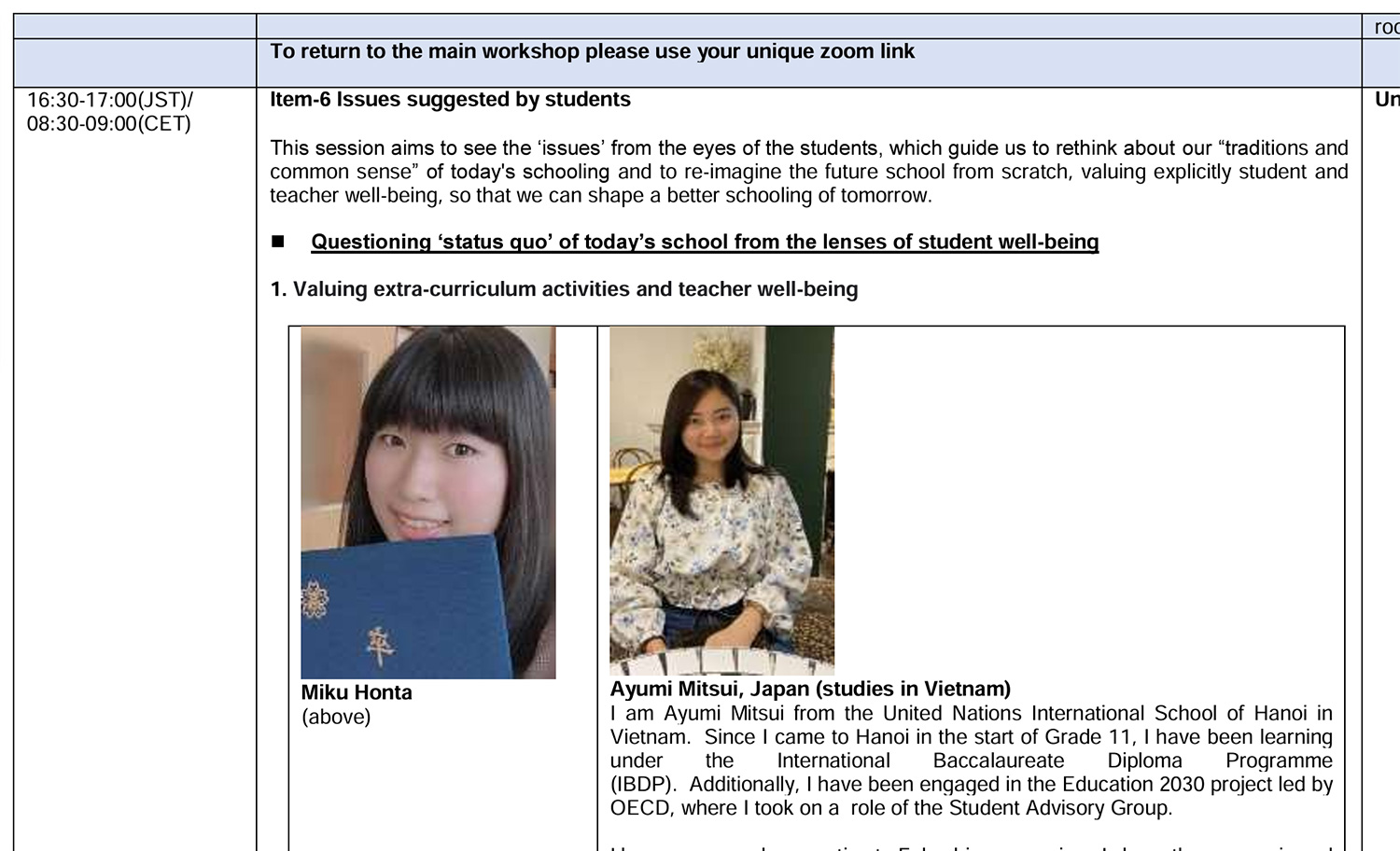学び!とPBL
学び!とPBL

様々なプロジェクトを経験し、今年福島大学を卒業し福島市役所で働く社会人の本多美久さんのインタビューの3回目となります。プロジェクト学習を通してどのような力が伸長するのか、考えてみたいと思います。
1.「きょうそうさんかくたんけんねっと」
図1 きょうそうさんかくたんけんねっとのホームページ
2.「昭和・平成」型から「令和」型プロジェクトへ
イベントの名前は「あれから。これから、」(*2)です。「あれから。」というのは、過去を大切にしつつ、区切りをつけるという意味合いがあり、東日本大震災だけでなく、これまでの教育や社会のあり方も含まれます。「これから、」というのは、これまでの学びを止めない、新しい旅のようなものを意味しています。
コロナ禍の中ですべてバーチャルでしたが、被災地の大熊町での実況映像などは衝撃を与え、「あれから。これから、」は成功したと思っています。
図2 「あれから。これから、」のホームページ
3.世界と日本、東京と地方……
加えると、コロナ禍で始まり比較的時間に余裕があったものが、学校が再開し時間がなくなったことも活動を困難にした原因です。いずれにしてもゴールが大きすぎて着地点が決められなかったことは反省点だと思います。
図3 きょうそうさんかくたんけんねっとの活動
本多さんは、今年(令和6年)元旦に発生した能登地震被災地の教育復興プロジェクトに参加しています。8月に第1回の能登スクール(*3)が開催され「令和版東北スクール」として始動しました。彼女はボランティア休暇を取って同スクールに参加し、状況を報告してくれました。中学2年生の時からしっかりした生徒だと思っていましたが、その彼女が9年を経て、他地域の子どもたちを守るとても頼り甲斐のある女性に成長していたことがとても感慨深く感じられました。一連のインタビューを通して、プロジェクトの中では感じられなかった意外な一面に気づかされました。
図4 令和6年8月の能登スクールの様子(左の写真の中央のTシャツは10年前のOECD東北スクールのもの)
*1:きょうそうさんかくたんけんねっと
https://www.edu-kstn.org/
*2:「あれから。これから、」
https://jupiter354.wixsite.com/website/kyososankaku
*3:国際共創プロジェクト「壁のないあそび場-bA-」 2024年8月能登スクール
https://gakugei-asobiba.org/2024notoschool