社会
社会
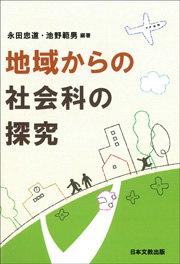
『小学社会』の監修者である広島大学の池野先生と永田先生が,日本各地で取り組まれている社会科を取材し,
その社会科を創設・指導してこられた先達にお話を伺うとともに,
現在行われている実践を紹介することで,日本の社会科の深化・発展の可能性を探る。
<目次>
はじめに
序 章 各地域の先達と多様な社会科の探究
1 社会科のゆるやかな交通整理
2 先達による社会科とゆるやかな交通整理との関連
3 ある枠組みだけでは描ききれないからこそ魅力的な社会科の多様性
第1部 知識・概念・教材を軸とする探究学習
第1章 知識の構造化による探究学習
第1節 先達:松田康博先生と伊東冨士雄先生のお話
第2節 東京都の実践例から
①地域が支えるお祭りとわたしたち(小3)
②つながるからつなげるへ(小5)
第3節 [研究者コメント]東京の社会科
第2章 教材の人間化による探究学習
第1節 先達:立岡誠先生のお話
第2節 長崎の実践例から
くらしを支える情報(小5)
第3節 [研究者コメント]「人間化」というキーワードが示す道
第3章 中心概念による子どもの探究学習
第1節 先達:佐藤正一郎先生のお話
第2節 千葉の実践例から
これからの食生活とわたしたち(小5)
第3節 [研究者コメント]レジェンドな実践者と地域性をふまえた実践例
第4章 「窮め探り,その極を覧る」探究学習
第1節 先達:辻迪夫先生のお話
第2節 京都市の実践例から
情報を生かすわたしたち(小5)
第3節 [研究者コメント]歴史と伝統ある京都社研「極覧」の神髄とは
第2部 子どもと人間の意識を軸とする問題解決学習
第5章 「子どもの意識の流れ」による問題解決学習
第1節 先達:堀公明先生のお話
第2節 大阪市の実践例から
ものを作る人びとのしごと(小3)
第3節 [研究者コメント]堀公明社会科の理論と実践
第6章 「なお,……したい」ことをめざす問題解決学習
第1節 先達:安東裕先生のお話
第2節 大分の実践例から
資源プラ分別のきまりをゆるめた清掃センターのSさん(小4)
第3節 [研究者コメント]教師が本気で子どもたちに問題解決を期待するとき,
子どもたちは無意識のうちにそれに応える
第7章 人間教育の核としての問題解決学習
第1節 先達:深谷孟延先生のお話
第2節 愛知の実践例から
我々の誇りを未来に伝える~半田に残る歴史遺産と私たちとのつながり~(小6)
第3節 [研究者コメント]問題解決学習のこれから
第8章 子どもが主体的に追究する問題解決学習
第1節 先達:片桐清司先生のお話
第2節 和歌山の実践例から
もっともっと工業!~オカジのダンボール作りから考えよう~(小5)
第3節 [研究者コメント]地域に根づく問題解決学習
第3部 子ども同士や地域を軸とする関連相関による社会科学習
第9章 「聴き合い」による社会科
第1節 先達:山田耕司先生のお話
第2節 福岡市の実践例から
オッペケペー節と自由民権運動(小6)
第3節 [研究者コメント]戦後社会科の初志を引き継ぐ実践として
第10章 子どもの身近なかかわりを核とする社会科
第1節 先達:砂田武嗣先生のお話
第2節 石川の実践例から
新しい日本 平和な国へ~東京オリンピックと昭和時代~(小6)
第3節 [研究者コメント]受け継がれる社会科実践研究
第11章 「こ・た・ね(個・多・練)」の社会科
第1節 先達:渋谷光夫先生のお話
第2節 山形の実践例から
ごみの?(ハテナ)大研究(小4)
第3節 [研究者コメント]芳醇端麗の社会科「こたね」─子どもの主体性喚起と
教師としての条件の追究─228
第12章 子どもが自ら楽しく取り組む教材の開発による社会科
第1節 先達:岡崎明宏先生のお話
第2節 岡山の実践例から
アジア・太平洋に広がる戦争と国民生活(小6)
第3節 [研究者コメント]自ら学ぶ子どもを育てる社会科の継承と創造
第13章 郷土室の整備と地域素材の教材化による社会科
第1節 先達:中村雅利先生のお話
第2節 茨城の実践例から
金沢用水(小4)
第3節 [研究者コメント]足下からの社会科地域教材の開発
終 章 世界的視野の中での地域からの社会科の探究
1 終章の意図
2 本書の意図と成果
3 世界の中の社会科