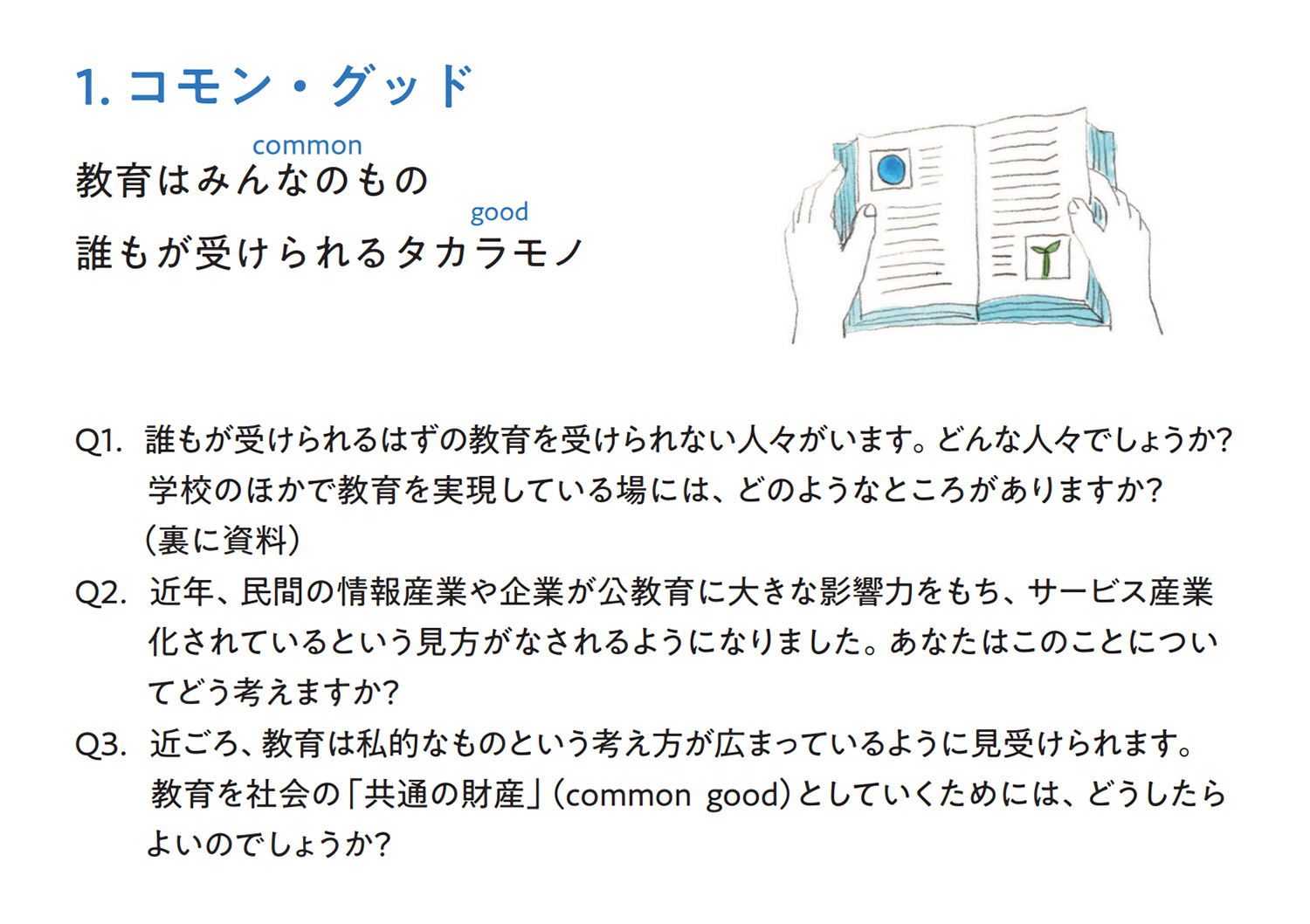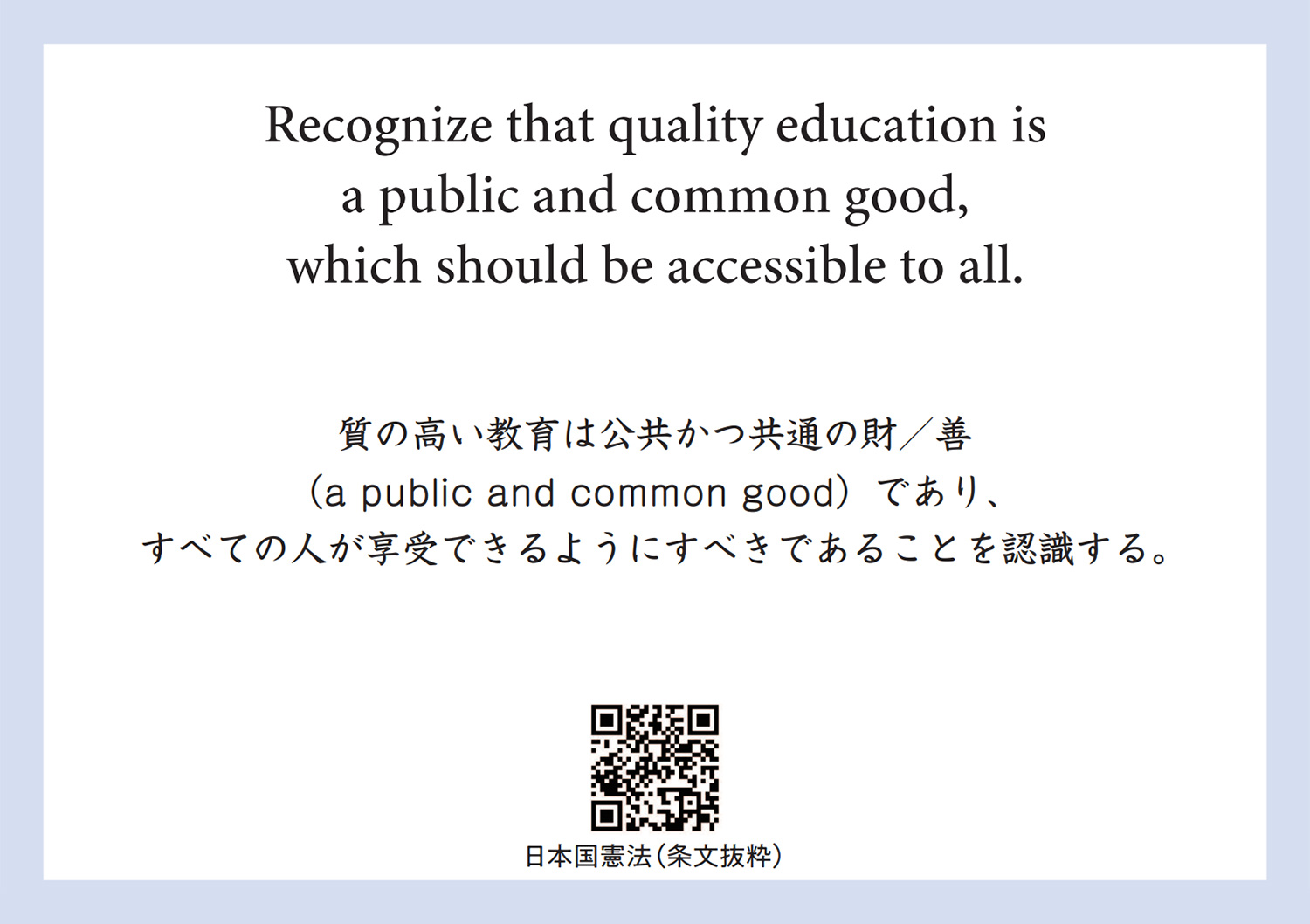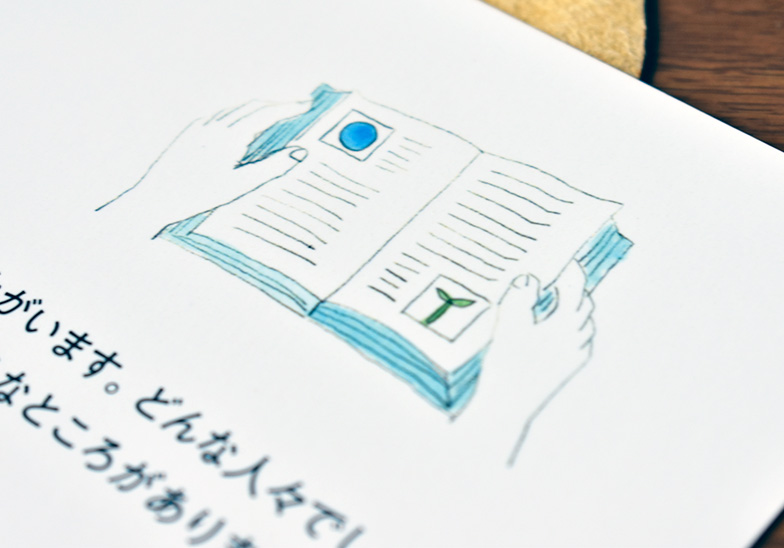学び!とESD
学び!とESD

世界の多くの場において国家や非政府の多様な関係者が協力して
公教育の公共性を保障していることを忘れてはなりません。
(UNESCO 2021, p.109.)
今号から新たなシリーズをはじめます。2023年のユネスコ総会で半世紀ぶりに改定された「ユネスコ教育勧告」(正式名称「平和と人権、国際理解、協力、基本的自由、グローバル・シチズンシップ、持続可能な開発のための教育に関する勧告」)には、勧告のエッセンスとも言える「主導原則(guiding principles)」が14あります。今号から、カード型教材(日本国際理解教育学会と聖心女子大学の有志による共同開発)を用いて一つひとつの原則に解説を添えていきます。また、すべてのカード教材には素敵なイラストが描かれており、その一つひとつの作品についてもイラストレーターの池田系さんに解説をしていただきます。
このカード型教材は、表(おもて)面(図1参照)に、主導原則のキーワードと同勧告の該当箇所の意訳、3つの問いを載せ、裏面(図2参照)に各主導原則の原文(英語)と邦訳を載せています。カードによっては、参考になる情報の二次元コードが載せられているものや表面の作品をもとに描かれたイラストが添えられているものもあります。
出典:聖心女子大学グローバル共生研究所(https://kyosei.u-sacred-heart.ac.jp/unesco2023/ )
)
今号は第一弾の「コモン・グッド」です。このカード(2024年版)には次の3つの問いが記載されています。
①誰もが受けられるはずの教育を受けられない人々がいます。どんな人々でしょうか?学校のほかで教育を実現する場にはどのような所がありますか?(裏に資料)(*1)
②近年、民間の情報産業や企業が公教育に大きな影響力をもち、サービス産業化されているという見方がなされるようになりました。あなたはこのことについてどう考えますか?
③近ごろ、教育は私的なものという考え方が広まっているように見受けられます。教育を社会の共通の財産(common good)としていくためには、どうしたらよいのでしょうか?
さて、皆さんはこれらの問いにどのように答えるでしょうか。ここでは、この教材を用いて実施した、一般市民対象のワークショップで実際にどのような答えが共有されたのかをお伝えします。
①の問いに対しては「インドで労働を強いられている少女」「戦禍のガザで暮らす少年」「日本語習得が不十分なまま日本の公立学校に通う外国籍の子ども達や不登校の子ども達」が具体例として挙げられていました。世界には飢餓状態や戦争などで教育が受けられない子どもたちがいる一方で、日本では教育を受ける権利が保障されているにもかかわらず自ら学校教育を受けない子ども、つまり不登校の子どもたちが34万人以上もいるのはなぜだろう、という更なる問いへと誘われたグループもあったようです。また学校以外の教育の場としてはフリースクールの他、お寺なども挙げられていました。確かに江戸時代など、寺子屋としてお寺は各地で重要な役割を担ってきました。
②と③の問いになると、回答者は社会全体のトレンドに視野を広げることが求められます。特に巨大なIT企業が学習用のアプリやAI教材を提供し、自治体もそれを公的に採用する例が増加している状況は、グローバルな課題を生んでいます。1人1台のタブレット端末が普及したことは利点もある一方で、公教育がEdTech産業の顧客囲い込みの場になっているのではないかという批判もあります。
以上から、「共通善」や「公共財」と訳され(同勧告では「公共かつ共通の善(public and common good)」も使用されています)、カード上では「社会の共通の財産(タカラモノ)」と解釈されている「コモン・グッド」は複数の文脈で語られていることが分かります。つまり、人間らしい(decent)生活を送るための基盤となる教育が保障されているかどうかという、しばしば途上国や貧困地域の教育課題として語られる文脈と、市場が及ぼす教育への影響によって公正性が担保されなくなるのではないかと懸念される文脈です。これらの「共通善」をめぐる情勢はかつての先進国と途上国という境界線が曖昧になった現在、テクノロジーの進展も相まって、やや複雑な様相を呈しています。
人類が進歩すれば、誰もが教育を受けられるようになり、平和な社会も築かれる。そう信じて、ユネスコをはじめとした国際機関は学校教育の普及に努めてきました。ところが、近年、学校は普及したにもかかわらず、教育が保障されていない子ども・若者が地域によっては増えています。
日本も例外ではありません。全国の隅々まで学校は普及しましたが、皮肉なことに、通学・就学を拒む子ども・若者は増加の一途を辿っています。特にコロナ禍を機に不登校の子どもは急増し続けており、義務教育段階で35万人近くの子どもが、高校段階も含めると41万人以上の子ども・若者が学校に通っていません。
世界的に、質の高い教育を受けられる層とそうでない層との格差が広がる傾向が指摘されています。教育機会が等しく人々に保障されていないという問題は、コロナ禍以前から国際的に指摘されていました。ユネスコ教育勧告が採択される2年前にユネスコが刊行した画期的な報告書『私たちの未来を再想像する』(「学び!とESD」Vol. 31)では、中国、インド、北米、ロシア等、各国内における不平等の拡大に関する問題に焦点が当てられており、大半の国々で資本が公的な所有から私的な所有にシフトしてきた結果、貧しい人々が社会的に排除されてきた問題が強調されています(UNESCO 2021, p. 24)。こうした格差や不平等は、特にコロナ禍の時期に顕在化し、だれも取り残されないことを標榜するSDGsなど、予断を許さない情勢にあるといえましょう。
このような状況下で前述の報告書では、共通善としての教育の原則はグローバルな責務と密接に関わっていることが強調されています(p.136)。COVID-19へのワクチン開発においては科学者らの協力を通して従来にないほどの迅速さをもって対応できたにもかかわらず、その分配においては全く公平性を欠く事態がそこかしこに見られました。報告書では、同様に、教育支援についても格差が生じてしまったことに対して厳しく問いています。
ユネスコ教育勧告の審議がスタートしたのはコロナ禍の只中、つまり教育へのアクセスの不平等や教育格差の拡大が世界的に問題視されている時でした。14の主導原則(このシリーズでは「エッセンス」と称します)のうち、条文の中で最初に掲げられているのが共通善であることは、こうした時代背景を踏まえると首肯できます。
以上は、国家による教育への平等なアクセスと質保証の問題ですが、他方で市場からの教育への影響力も近年、急速に増大しており、各地で育まれてきた「タカラモノ」が崩されてしまうのではないかという懸念も広がっています。特にITやAIを通した教育のサービス産業化の結果、利便性の促進、思考過程の効率化、関心事の個別最適化などが進み、本質的に手間暇のかかる人間形成や民主主義の構築、共生などの教育の本質的とも言える課題意識が後退する可能性が指摘されています。
このカードのイラストに描かれた書物をめくる手の行為や時間をかけて知識を内在化していく学びのあり方、そしてその過程で育まれてきた民主主義や協力・協働などの価値観はますます希少性を帯びていく時代になるのかもしれません。
【参考文献】
- UNESCO (2021)
Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education.
(ユネスコ『私たちの未来を共に再想像する―教育のための新たな社会契約―』)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707
- 聖⼼⼥⼦⼤学グローバル共⽣研究所 ”わたしたちがつくる平和・人権・持続可能な開発” 「ユネスコ教育勧告」カード型教材及び解説
https://kyosei.u-sacred-heart.ac.jp/unesco2023/
*1:「日本国憲法」条文抜粋
https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/a002.htm