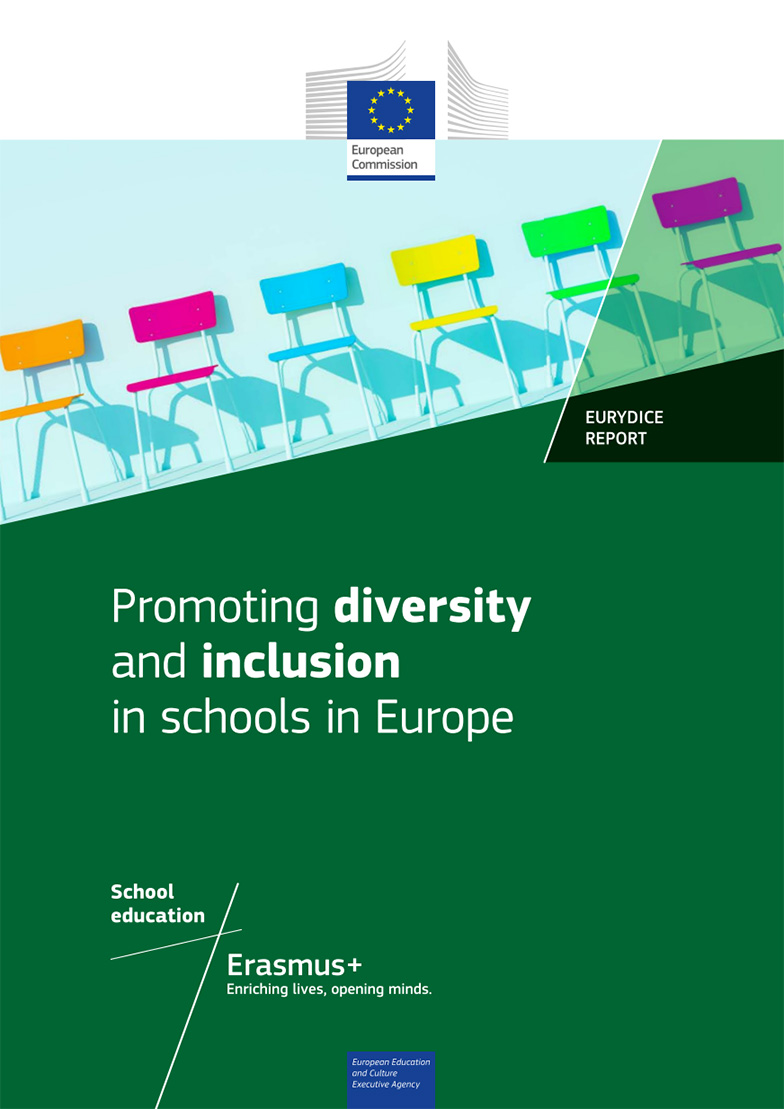学び!と共生社会
学び!と共生社会
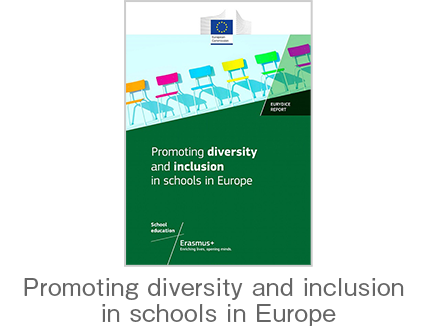
1.はじめに
EU関連サイトの一つであるEurydice(*1)は、ヨーロッパ諸国の教育制度や特定のテーマに関する比較研究、教育分野の指標や統計に関する情報等を提供しています。
そのEurydiceで、2023年に「ヨーロッパの学校における多様性とインクルージョンの促進(Promoting diversity and inclusion in schools in Europe)」と題する報告書(*2)が公開されました。
これまでも本連載ではEU圏におけるインクルーシブ教育への取り組みの状況を紹介してきましたが、この報告書からは直近のEU諸国におけるインクルーシブ教育への取り組みの達成状況や課題等に関する知見を得ることができます。
インクルーシブ教育については、現在の取り組みの状況を短期的に把握し評価することも大切ですが、目指そうとしているゴールを明確にしてそれに向かってどのように歩みが進んでいるかという大局的な視点から変容のプロセスをとらえていくことも大事なことです。そこで、今回はこうした観点からこの報告書を紐解き、直近のEU圏でのインクルーシブ教育への取り組みの状況を探ってみたいと思います。
2.報告書の概要
この報告書は7つの章から構成されていて、EU圏の国々の学校の多様性とインクルージョンへの取り組みの状況がまとめられています。各章の概要を紹介します。
(1)第1章:学校教育の文脈における多様性とインクルージョン
障害者権利条約(*3)では、「障害に基づくあらゆる差別」を禁止しており、それに対応するためには、より公平でインクルーシブな教育に焦点を当て、一人一人の児童生徒の具体的で多面的なニーズに考慮することが必要になってきます。既にEU圏ではその考え方が主要な政策に広く反映されているのですが、この章ではEU各国の特徴ある取り組みが紹介されています。その上でこの報告書では、不平等と差別に対処する際の「包括的でかつ交差的なアプローチ」の重要性を指摘しています。
個人は複数のアイデンティティ(人種、性別、階級、性的指向、性自認など)を有しているので、不平等と差別に対しても単一のアイデンティティのみに対処するだけで不十分で、複数のアイデンティティが交差していることを理解して対応していく必要があるということです。報告書では「難民」の例を挙げてこのことを説明しています。つまり、「難民」の児童生徒が「難民」という視点からしか見られていないと、学校では言語学習のみの支援に重点が置かれ、広く教科全般にわたる配慮がなされなくなってしまうということです。日本でも、日本語を習得していない外国籍の児童生徒を特別支援学級に在籍させるという形で対応している事例がたびたび報道されています(*4)。インクルーシブな政策とその対応においては、児童生徒一人一人の具体的かつ多面的なニーズが考慮されなければならないということが理解できます。
(2)第2章:学校における差別と多様性のモニタリング
本報告書によると、EU圏のほとんどの国には、差別をモニターするための国レベルでの機関が設置されています。この機関は、差別に対応するためにさまざまな組織と協力して活動しているということです。したがって、そうした国では個々の児童生徒の特性、特別な教育的ニーズや障害、国籍、出生国、社会経済的背景などに関するデータにアクセスすることが可能です。そしてこれらのデータから、最も一般的な差別は特別な教育的ニーズや障害、および民族的背景が根拠になっていることも確認できているということです。こうしたエビデンスに基づく情報は政策の策定や評価にも有用で、教育当局が特定の学習者グループに対する特定の措置の影響を理解し、学習者を支援したり学校が最も必要とされるリソースを活用して適切な介入プログラムを計画したりするのに役立たせているということがこの報告書に記されています。
他方、こうした体制が整備されているにもかかわらず、半数以上の国では児童生徒の難民(亡命希望者)や移民の経歴、家庭での言語に関するデータについては把握できていない状況にあることも明らかにされています。
特別な教育的ニーズや障害、および民族的背景が差別の大きな根拠となっていることから本章では関係機関等と連携した包括的なデータ(comprehensive data)の収集とモニタリングの重要性が訴えられています。
(3)第3章:学校における多様性やインクルージョンを促進する国レベルでの法律、戦略、行動計画
この章では、国レベルの法律、戦略、行動計画について報告されています。国レベルの法律、戦略、行動計画は、学校に内在する既存の障壁を取り除き、学校における平等と包摂性を体系的に促進することに貢献するということ、そして、EU各国の教育システムにはこのような包括的な政策の枠組みが整えられていることが記されています。
それらの多くは近年導入されたもので、関連するEU政策イニシアチブ(例えば、「EU反人種差別行動計画」、「EU LGBTIQ平等戦略」)に基づいている場合もあるということです。
ほとんどの教育制度は、制度の改善(とりわけインクルーシブ教育、平等なアクセス、児童生徒への適切な支援)をグローバルな目標としており、教育における差別の防止と機会均等の促進、児童生徒の学習成果の向上、学校教育からの早期離脱防止に重点を置いた政策の枠組みとなっているものが多かったということです。
こうした戦略的な政策の枠組みは、ロマ(インドに起源を持つ移動型の少数民族)の児童生徒、特別な教育的ニーズや障害のある児童生徒、移民や難民の児童生徒のインクルージョンを促進しようとするものが中心で、ジェンダーの平等の促進、反ユダヤ主義との闘い、LGBTIQ+(lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer and other sexual identities)については、それほど焦点が当てられていないということも記されていました。
本章からは、学校における平等と包摂性を体系的に促進するためには国レベルの法律、戦略、行動計画の整備が大事であることが伝わってきます。また、適切な資源配分と結果のモニタリングと評価が不可欠であることも学びました。
(4)第4章:学校へのアクセスと参加の促進
この章は、EU諸国における学校へのアクセスと参加に関する政策についてまとめられています。学校へのアクセスと参加という観点からは、主として特別な教育的ニーズや障害のある児童生徒、移民、難民、少数民族を背景とする児童生徒に対するインクルーシブ教育及び社会経済的に恵まれない児童生徒への経済的支援に焦点が当てられているということがわかりました。
また、通常の学校へのアクセスと参加を促進するために最も広く報告されている政策は、特別な教育的ニーズや障害のある児童生徒のアクセスを向上させるための取り組みでした。これには物理的なアクセシビリティの改善、学校生活や学習活動の基盤となる施設や設備の改善、支援技術の改善などが含まれています。
国連障害者権利条約第24条に明記されているように、教育を受ける権利がある子どもには障害のある子どもも含まれています(*2)。このことからEU諸国では、政策レベルにおいて通常の学校教育のインクルーシブ性を高め、特別支援学校の児童生徒数を減らすという明確な推進力が働いていたようで、この報告書に掲載されている多くの国々の教育制度において、特別な教育ニーズのある生徒にとって通常の学校が第一の選択肢であるべきという規則が設けられていることからもそのことがわかります。
しかし、この報告書では、特別な教育ニーズがあると認定された児童生徒への対応について、通常の学校への就学率が国によって異なっており、場合によっては低い傾向にあるということが報告されています。「European Agency for Special Needs and Inclusive Education (EASNIE)」の2019/2020学年度のデータによると、特別な教育ニーズがあると正式に認定された児童生徒の通常の学校への就学率は、初等教育(小学校)レベルで43.07%から99.05%の範囲、前期中等教育(中学校)レベルで22.55%から100.00%、後期中等教育(高等学校)レベルで0.74%から100.00%となっていたということです(*5)。
このことから、この報告書では、差別的な慣行が依然として根強く残っている可能性があることを指摘し、特別な教育ニーズのある児童生徒が通常の学校に在籍できるように、また、適切な支援を行うために必要な手段や資源を通常の学校が確保できるようにしていくためには、より強い信念を持った対応が必要になってくるだろうと指摘しています。
また、「Inclusion Europe」などの組織が、特別支援学校が存在し続け、十分な資金の確保もされないのであれば、ほとんどの国ではインクルーシブ教育の目標達成に向けて困難を強いられることになるだろうという見通しを示しているということも紹介されています(*6)。同様に、2021年版中央・東ヨーロッパ世界教育モニタリング報告書でも、分離教育防止の法律があるにもかかわらず、依然として障壁が残っていることが指摘されているということです(*7)。
こうした分離教育の慣行が残っている一方、すべての児童生徒が通常の学校に在籍することをポリシーとしている国も存在します。そうした国の例として、報告書ではイタリアとリトアニアの制度が紹介されていました。その他にも、特別な教育的ニーズや障害のある生徒に対して、質の高い教育と学習を提供できるよう通常の学校への支援を強化している国々の取り組みもこの章では紹介されていました。
特別な教育ニーズがあると認定された児童生徒の通常の学校への就学については、国連の委員会から改善が求められたこともあって(*8)、日本でも大きな課題となっています。そこで、この第4章の内容については、改めて詳しく紹介したいと思っています。
(5)第5章:学校のカリキュラムと評価における多様性とインクルージョンの強化
この章では、カリキュラムの改訂を通じて多様性とインクルージョンを推進し、評価についてもより包括的なものにしようとする取り組みが進められていることを紹介しています。インクルーシブ教育を推進するためには、通常の学校の改革が不可欠です。EU諸国のすべてで、こうしたカリキュラムの改訂作業が進められているということで、インクルーシブ教育に正面から向き合っている真摯さが感じられました。
カリキュラムにおける多様性と包摂性への対応について、半数の国の教育システムでは、特定の学習者グループを具体的にターゲットとしていませんでした。特定のグループに言及している場合は、特別な教育的ニーズや障害のある児童生徒、少数民族の児童生徒が最も多く、次いで移民、難民の児童生徒、恵まれない社会経済的背景を持つ児童生徒と宗教的少数派の児童生徒となっていて、LGBTIQ+については、最も言及が少なかったということです。
(6)第6章:ねらいを定めた学習と社会情緒的支援の促進
この章では、学校が個々の児童生徒の学習や社会情緒的なニーズに的確に把握し、適切に対応していくことを支援するために、EU諸国の教育システムにおいて推進されている政策や施策が紹介されています。
学校が生徒の学習ニーズと社会情緒的支援ニーズを特定するために、多くの国では、生徒の学習上の困難、行動、社会情緒、家族の問題などを評価するためのガイダンスやカウンセリングサービスを利用する取り組みが進められていて、生徒の学習ニーズと社会情緒的ニーズを評価するための具体的なガイドラインやツール、学習ニーズを評価するための全国的な診断テスト、言語能力を評価するためのガイドラインやツール等は、あまり用いられていませんでした。
また、学校における学習支援の提供を促進するために、特に特別な教育的ニーズや障害がある児童生徒、移民、難民、少数民族の児童生徒、恵まれない社会経済的背景を持つ児童生徒など、特定のリスクのある児童生徒を対象とした支援介入を促進する政策や施策を実施している国が多かったことも報告されています。
(7)第7章:多様性と包摂性を促進するための教員と教員研修
この章では、教育を所管する官庁が多様性とインクルージョンに関する教員教育や研修の機会を多く提供し、教育支援スタッフ活用を推進しているということが報告されています。
併せて、インクルーシブな学級を運営するための教員の準備不足や支援スタッフを雇用するための資金の不足が、依然として課題となっていることも示されています。
教員の多様性の欠如は、エビデンスベースで明白であるにもかかわらず、多様な経歴を持つ教員の採用を促進する政策や施策を打ち出している国は8か国に過ぎないこと、そうした施策が存在する場合でも、主に障害を持つ教員や移民出身の教員の採用が奨励されていること、研修プログラムへの教師の参加率が低い場合があることなども指摘されています。
また、制度としては、学校にさまざまな専門家(例:心理学者、言語聴覚士、特別な教育ニーズの専門家、ソーシャルワーカー)やティーチングアシスタントを配置することを義務付けまたは推奨し、学校が支援スタッフを雇用するための財源も用意しているものの、用意された財源が十分でないために学校が必要な教育支援スタッフを雇用できない実態があることも記されています。
日本も似たような状態にあるといえ、多様性と包摂性を促進するためには教員や支援スタッフの確保と質の向上が国や地域を超えて共通の大きな課題になっているといえます。
3.まとめ
本報告書の序文には、次のように記されています。
「私たちは欧州市民として、日常生活に通底する共通の基本的価値観を共有しています。インクルージョンはその一つです。
多様な視点や経験に触れることで、文化的知性と共感力が育まれます。背景、出自、信条、人生の歩みに関わらず、誰もが平等に扱われるべきであり、誰一人取り残されるべきではないという共通の理解が生まれます。
そして、インクルージョンは、疑いなく学校から始まらなければなりません。」
このEurydiceのレポートには、こうした考え方を背景として、EU各国の教育当局が差別に対処し、学校における多様性とインクルーシブを促進するためにどのようなプロセスをたどって取り組みを行っているかが報告されていました。
報告の内容を俯瞰すると、日本における「インクルーシブ教育システムの構築」の取り組みと重なり合う部分もたくさんあることがわかります。
他方、インクルーシブな教育環境を創造するために通常の学校の改革に正面から取り組んでいるところには温度差が感じられました。
本報告書から、EUとして、通常の学校の教育内容や指導方法、そして日々の学校生活を通して多様性とインクルージョンを主流化していくことを柱に据えて取り組んできていることが理解できます。そして、国によって対応は異なっているものの、その目標が共有されていて、真摯に対応している姿勢には、学ぶところも多々あるのではないかと思います。
*1:Eurydice
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/
*2:European Commission/EACEA/Eurydice, 2023. Promoting diversity and inclusion in schools in Europe. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d886cc50-6719-11ee-9220-01aa75ed71a1/language-en
*3:障害者の権利に関する条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html
*4:例えば、2019年8月31日付の毎日新聞記事「外国籍は通常の2倍 特別支援学級在籍率 日本語できず知的障害と判断か」
https://mainichi.jp/articles/20190831/k00/00m/040/156000c
*5:European Agency for Special Needs and Inclusive Education(EASNIE)
https://www.european-agency.org/resources/publications/EASIE-2019-2020-cross-country-report
*6:Inclusion Europe “Exploratory study on the inclusion of pupils with complex support needs in mainstream schools”
https://www.inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2018/08/IE_CSN_Education_Report_Final.pdf.
*7:UNESCO, “Global Education Monitoring Report 2021 – Central and eastern Europe, the Caucasus and Central Asia – Inclusion and education: All means all: key messages and recommendations”
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375517
*8:国連・障害者の権利に関する委員会「日本の第1回政府報告に関する総括所見」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100448721.pdf