学び!と共生社会
学び!と共生社会
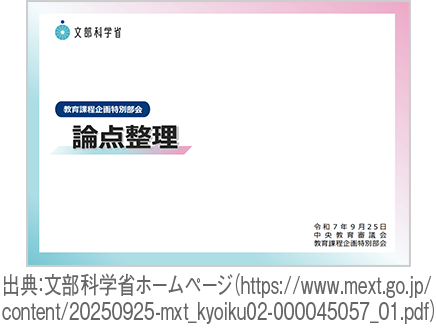
1.はじめに
最近、オーバーツーリズムや外国人労働者の増加の影響のせいか、SNSなどで「多文化共生は絵空事」という主張を耳にすることがあります。確かに急激な外国人の増加で、風景が変わってきているという印象は否めません。
しかし、今の社会情勢は、「共生」を抜きにして未来を語ることはできない状況にあります。障害者の社会参加についても、国連の障害者権利条約の批准以降、その認識が深まり、「共生社会」の実現に向けた動きが蝸牛のごとくではあるかもしれませんが進展してきているといえます。
そうした状況の中で、いくつか気になる報道に接しました。今回はそのことを取り上げてみたいと思います。
2.市川沙央さんの寄稿
9月12日に『ハンチバック』という小説で芥川賞を受賞した小説家の市川沙央さんの寄稿文が、朝日新聞に掲載されました(*1)。この寄稿文はデジタル版にも掲載されていて無料で読むことができます。見出しは、「奪われた「共生」の言葉 障害者なき対話に市川沙央さんは思う」となっています。掲載直後に大きな反響があり、私も複数の知人からの情報でこの記事のことを知りました。
内容は、2024年秋に朝日新聞社主催で開催された「朝日地球会議2024」におけるアクセシビリティ対応に対する異議申し立でした。「誰ひとり取り残さず、すべての人が暮らしやすい持続可能な地球と社会について、みなさまとともに考えていく」と謳っている『朝日地球会議』」に登壇する人達は、全て元気そうな人ばかり、障害当事者や家族あるいは支援者の立場の人すら一人もいない、プログラムのテーマにも、障害者に関するものは一つもないようだ。会場参加者のアクセシビリティに関しては手話通訳も同時字幕も用意されていないといった「共生」への対応の不徹底を批判したものです。詳細については原文を確認していただきたいと思います。
それに対して、朝日新聞社は即座に反応し、「市川沙央さんの朝日地球会議への指摘受け」という見出しの記事で「共生」への取り組みを強化していくという内容の記事を配信しました(*2)。そこには、「私たちはご指摘を重く受け止め、市川さんのおっしゃる「断絶」をなくす努力を続けてまいります。」という朝日新聞社の姿勢が示されていました。
障害者権利条約が批准されて10年が経過し、障害者を含めニーズがある人々へのアクセシビリティ対応が浸透してきていると思っていたのですが、「共生」を掲げた「朝日地球会議」では、障害者の参加が全く意識されていなかった、また、寄稿されるまでそうしたことに気づかず見過ごしていたという問題も指摘しているものでした。
対して同時期に開催された東京都主催の「だれもが文化でつながる国際会議2024」(*3)では十分な対応がなされていたということも対比されていました。私はこの会議の展示に少しばかり協力していたのですが、こちらは、クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー(高齢化や共生社会など、東京の社会課題解決への貢献を目指し、高齢者、障害のある方、外国にルーツのある方、赤ちゃんや子どもなどを対象者に「アクセシビリティ向上」と「鑑賞・創作・発表機会の拡大」に取り組むプロジェクト)の取り組みの一つであり、アクセシビリティについては、万全の対応がなされていたといえます。
私はこの異議申し立てを知って、障害者権利条約が批准された時の新聞報道を思い出しました。広く読者に伝わるように紙面の目立つところに掲載してくれるだろうと期待していたのですが、見出しも小さくわずかな分量の記事でした。障害者の社会参加への認識が、思っていた以上に希薄だと感じたものです。
その後、関連する国内法の改正等があり、アクセシビリティ対応についても改善が進んできていたのですが、まだまだ日常に溶け込む段階にまで至っていないことを、今回の出来事は教えてくれたように思います。
市川さんは、「365日ほとんど家の中に閉じこもっている私のところにだって障害者の苦境の情報は届くのです。足で稼ぐ新聞記者の目と耳にもっと多くの情報が入っていないわけがない。」とも記しています。情報が入っても、他人事としかとらえられていない現状は、一新聞社だけの問題ではなく、社会、ひいては通常の学校が、まだまだインクルーシブになっていないことの証左だといえるのかもしれません。今回の市川さんの問題提起を、自分事としてとらえていくことが大切だといえます。
3.舩後議員の参議院不出馬の表明
今年の6月に参議院議員の舩後靖彦さんが、参院選に不出馬の表明をしました(*4)。
ご存じのように、舩後さんは指定難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)で人工呼吸器をつけて活動されていました。舩後さんと木村英子議員が就任して以降、国会内のハード面/ソフト面でのバリアフリーが進みました。舩後さんが、「こののちに重度障害のある議員が就任した際の道筋になったと自負しております」と述べているとおり、全ての人に社会は開かれていることを体現され、合理的配慮の提供という観点からも大きな貢献をなされました。
その表明の中に、「共生社会」の形成に関連する重要な指摘がありました。
一つは、議員への道が全ての人に開かれていることを強く意識されていたということです。このことについて、次のように述べられています。
一方、働くなかで感じたのは、議員は「超人的に健康で、体力があって、元気な人ばかり」ということです。国会議員は「そういうもの」という固定観念は、「元気で動けなければ役に立たない」という優生思想につながってしまいます。この社会には、望んでいても十分に働けない人が多くいます。ごく一部の「強い男性」しか活動できないのは、国権の最高機関の姿として健全とは思いません。だからこそ、私や木村議員、天畠議員の存在意義を感じ頑張ってまいりましたが、年齢的にも体力的にも、さらに6年間は難しいと考えた次第です。
年齢や体力にあらがうことはできません。次に繋がっていくことが期待されます。
もう一つは、特別支援教育からインクルーシブ教育への転換に向けて積極的に活動されてきたという点です。表明では以下のように述べられています。
また、参議院議員となって最初の委員会質疑から継続的に取り組んできたのが、特別支援教育からインクルーシブ教育への転換です。合理的配慮やバリアフリー化などの環境整備に関しては、一定進んだと評価できる面もありました。しかし、就学先決定の仕組みを変え、誰もが共に学ぶインクルーシブ教育への制度転換は、国連・障害者権利委員会の勧告にもかかわらず、1ミリも進んでいません。このため子どもの数は減少しているのに、特別支援学校・学級で学ぶ子どもの数が急増し、分離が拡大しているという結果で、忸怩たる思いです。
インクルーシブ教育については、制度としては「共生社会」の形成めざす方向性が示されましたが、実態は、特別支援学校が増え、通常の学校での対応が追い付いていないという状況にあります。「分離が拡大している」と受け止めている舩後さんが議員から退かれることは大変残念なことです。
しかし、「今後は民間の立場から、「命の価値は横一列」、「可能性はノーリミット」を訴え、活動してまいりたいと思います。(中略)この活動は、終わりはないものと見ています。故に、後続されるみなさんがやりやすくする事がわたくしに課された使命と思っている次第です」と会見を締めくくられていました。今後のご活躍に期待したいと思います。
4.おわりに
「共生社会の形成」に関連して、二つのトピックを取り上げました。
市川沙央さんの朝日新聞の事業への異議申し立ても、舩後さんの参議院不出馬の表明も、学校教育や社会教育との関連を抜きにして考えることはできません。
「朝日地球会議2024」における障害者の参加やアクセシビリティの対応への配慮の欠如は、組織的な問題でもあり、イベントの主催者や参加者の意識の問題でもあります。障害がある人やニーズのある人との接点が希薄であったことが、背景にあると思われます。「共生社会の形成」に向けた学校教育段階の役割は大変重要だということが、改めて浮き彫りにされたように思います。
舩後靖彦さんは、「共生社会の形成」という観点から「インクルーシブ教育」の実現に向けて尽力されてきましたが、道半ばで引退されることになりました。
「共生社会の形成」は絵空事ではありません。現在、文部科学省では次期学習指導要領改訂に向けた取り組みが進められています。この9月25日には、教育課程企画特別部会における論点整理が報告されました(*5)。
「共生社会の形成」に向けた改善がどのように図られていくか、引き続き注視していきたいと思います。
*1:2025年9月12日、朝日新聞、「奪われた「共生」の言葉 障害者なき対話に市川沙央さんは思う」
https://www.asahi.com/articles/AST991S3BT99UPQJ00FM.html
*2:2025年9月12日、朝日新聞、「「共生」への取り組み強化 市川沙央さんの朝日地球会議への指摘受け」
https://www.asahi.com/articles/AST9B34Z8T9BULZU002M.html?iref=pc_leadlink
*3:だれもが文化でつながる国際会議2024
https://www.creativewell-conference.jp/
*4:【会見文字起こし&動画】参院選2025 不出馬表明 記者会見
https://reiwa-shinsengumi.com/activity/24771/
*5:2025年9月25日、「教育課程企画特別部会 論点整理」
https://www.mext.go.jp/content/20250925-mxt_kyoiku02-000045057_01.pdf