学び!と公民
学び!と公民

1.はじめに
生徒から、「なぜ社会科で『お金』を学ぶのか」と聞かれたら、どのように答えるのが正解でしょうか。
 自身の生活設計を見据え、資産形成の方法を身につけるため?これでは家庭科との区別がつきにくくなりそうです。いや、家庭科でも資産形成のハウトゥーまでは教えられていませんね。では、「教科書に載っているから!」との答えはいかがでしょう。正解ではあるけれども、何とも物足りません。そこで、少々ずるいのですが一問一答的に答えるのではなく、社会的な見方・考え方を働かせ、「分業と交換、希少性などに着目して考えてごらん」と問い返すことをおすすめします。生徒の素朴な疑問が「学び!」へと発展していく瞬間を目のあたりにすること請け合いです。
自身の生活設計を見据え、資産形成の方法を身につけるため?これでは家庭科との区別がつきにくくなりそうです。いや、家庭科でも資産形成のハウトゥーまでは教えられていませんね。では、「教科書に載っているから!」との答えはいかがでしょう。正解ではあるけれども、何とも物足りません。そこで、少々ずるいのですが一問一答的に答えるのではなく、社会的な見方・考え方を働かせ、「分業と交換、希少性などに着目して考えてごらん」と問い返すことをおすすめします。生徒の素朴な疑問が「学び!」へと発展していく瞬間を目のあたりにすること請け合いです。
2.金融教育の歴史
社会科での「お金の教育」に触れる前に、まず、戦後日本の金融教育の歴史をふり返ってみましょう。金融広報中央委員会Webサイト(アーカイブサイト)に「金融広報中央委員会の歩みと最近の取組み―創立70周年に寄せて―」との記事があります(武井 2022)。
それによると、第二次世界大戦後、日本は戦後復興のために巨額の資金が必要となり、政府と日本銀行が主導して国民に貯蓄を奨励、蓄積された資金を重工業などに優先的に割り当て、復興の礎が築かれた、とのことです。その際、貯蓄を全国一体となって推進するために1952(昭和27)年に創立されたのが貯蓄増強中央委員会でした。貯蓄増強中央委員会は、1953年初刊、70年以上過ぎた現在まで毎年発行されている政府刊行物『明るい暮らしの家計簿』の普及に努めたほか、「こども郵便局」(学校に近い郵便局が親局となり、学校に特設窓口を設置して運営。授業に差し支えのない時間を選んで、学童の貯金奨励と社会教育に資する目的で開局)を全国の学校に展開させ、貯蓄習慣の育成に一役買ったのです。
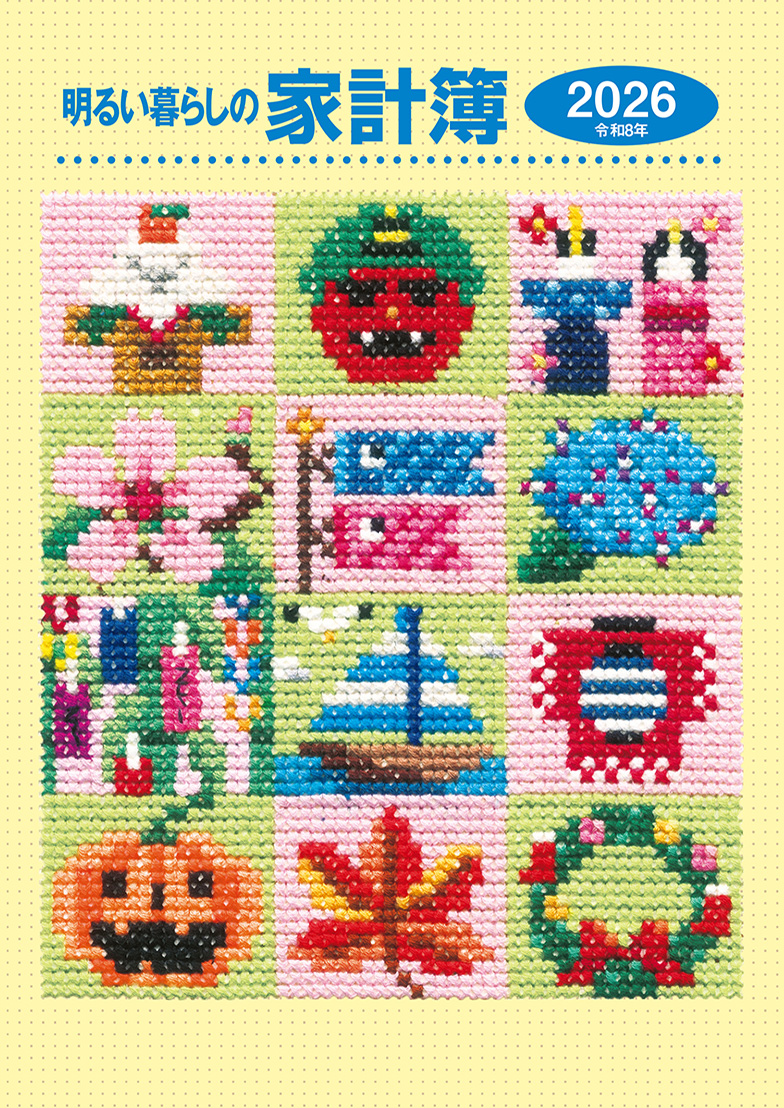 提供:ときわ総合サービス株式会社
1990年代半ばのバブル経済崩壊後、橋本内閣、小泉内閣によって金融機関に対する大規模な規制緩和が行われました(日本版金融ビッグバン)。2001(平成13)年度の「骨太の方針」で「貯蓄から投資へ」とのスローガンが掲げられ、従来のような「貯蓄」に焦点をあてるのではなく、広く金融経済に関する情報を提供することが国民のニーズにかなう、との認識が高まっていきました。そうした中、2001年に貯蓄増強中央委員会は金融広報中央委員会に改称し、個人の金融リテラシー向上に努める組織へと衣替えしたのです。
提供:ときわ総合サービス株式会社
1990年代半ばのバブル経済崩壊後、橋本内閣、小泉内閣によって金融機関に対する大規模な規制緩和が行われました(日本版金融ビッグバン)。2001(平成13)年度の「骨太の方針」で「貯蓄から投資へ」とのスローガンが掲げられ、従来のような「貯蓄」に焦点をあてるのではなく、広く金融経済に関する情報を提供することが国民のニーズにかなう、との認識が高まっていきました。そうした中、2001年に貯蓄増強中央委員会は金融広報中央委員会に改称し、個人の金融リテラシー向上に努める組織へと衣替えしたのです。
こうした社会の変化を受けて、2008年版学習指導要領で、公民的分野の改訂の要点に「法や金融などに関する学習の重視」がうたわれました。公民的分野、とりわけ経済領域の授業で「お金」を学ぶことが重視されることとなり、現行の2017年版学習指導要領に引き継がれています。
3.「お金」を通した「主体的に学習に取り組む/社会に関わろうとする態度」の育成
現行学習指導要領は、各教科等で育成することが求められる資質・能力が「内容」として明記されていますが、その書きぶりが、
ア 次のような知識(及び技能)を身に付けること。
イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。
と、「2観点」で統一的に示されたことから、学習の目的や主体性、すなわち「何のためにこの内容(本稿では「お金」)を学ぶのか」が見えにくくなっているのも確かです。ただし、公民的分野では、
イ 国民の生活と福祉の向上を図ることに向けて、次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。<大項目B(2)>
イ 地方自治や我が国の民主政治の発展に寄与しようとする自覚や住民としての自治意識の基礎を育成することに向けて、次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。<大項目C(2)>
(下線は筆者付記)
など、思考力、判断力、表現力等を身につけた先にある個人や社会の在り方を方向目標として明記している箇所もあり、これは他教科、他の分野には見られない特徴的な書きぶりです。個人と社会との関わりを、「お金」を仲立ちにして考察したり、理解を深めたりすることで社会参画意識の涵養につながることが期待されます。
【参考文献】
- 武井敏一「金融広報中央委員会の歩みと最近の取組み―創立70周年に寄せて―」金融広報中央委員会(現 金融経済教育推進機構(J-FLEC))、2022年
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/k_kikou/70th.html
- 文部科学省『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編』東洋館出版社、2018年
- 郵政省『郵政百年史』吉川弘文館、1971年