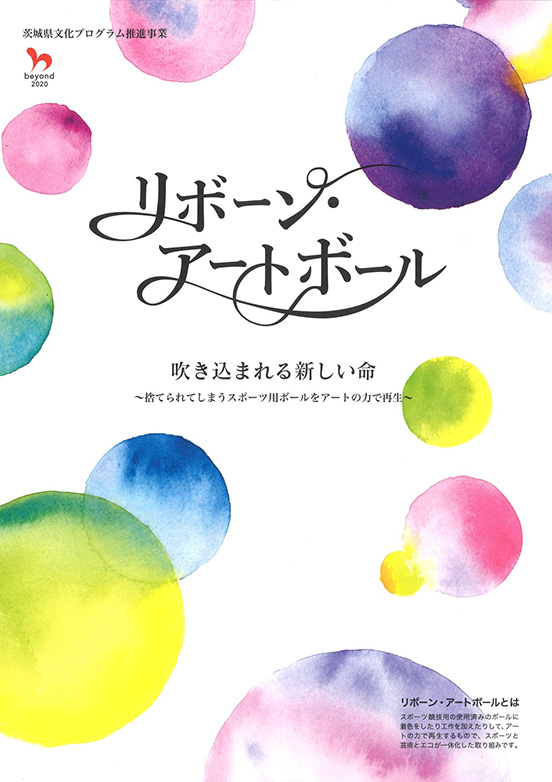読み物プラス
読み物プラス

リボーン・アートボールとは
「リボーン・アートボール」は、私が「かつてオリンピックに芸術競技があり、1936年ベルリン大会では二人の日本人画家の銅メダリストがいた」という史実を知ったことから始まったアート活動です。「オリンピックはスポーツと文化・芸術が両輪となって開催されるもの」という理念を知り、これらを何らかの方法で、みなさんに知っていただきたいという思いから発案しました。
名称の「リボーン」とは、不要になったボールに絵を描いてアート作品として蘇らせる意味で、それによってアート作品を創ることから「リボーン・アートボール(Reborn art-ball)」としました。
二人の画家の銅メダリスト
1995(平成7)年12月30日付の朝日新聞に、「ベルリン五輪絵画部門で銅 幻の作品、アトランタへ」と題する記事が掲載されていました。内容は、1936年ベルリン大会の芸術競技で銅メダルを獲得した日本画家、藤田隆治(1907-1965)の弟子である日本画家、笠武(画号:青峰、1936-2014)氏が、戦災で焼失した藤田の受賞作品《アイスホッケー》を、写真を手掛かりに再現し、1996年に近代オリンピック100年を迎えるアトランタで個展を開くというものでした。
オリンピックの「芸術競技」は、クーベルタン男爵(1863-1937)の提唱により、1912年ストックホルム大会から導入され、1948年ロンドン大会までの7大会で開催されました。日本は1932年ロサンゼルス大会から参加しており、ベルリン大会では、日本画家、鈴木朱雀(1891-1972)も作品《古典的競馬》で銅メダルを授与されました。
「芸術競技」は、絵画、彫刻、建築、文学、音楽の5部門があり、優秀な作品にはスポーツ競技と同様、金・銀・銅のメダルが授与されましたが、審査の公平性、アマチュアとプロ、作品輸送などの問題があり廃止されました。そして1952年ヘルシンキ大会からはメダル授与のない「芸術展示」となり、1992年バルセロナ大会からは「文化プログラム」として開催され、現在に至っています。
リボーン・アートボールの誕生と2020オリンピック東京大会
2013年9月、2020年オリンピック・パラリンピックの開催地が東京に決まりました。これを契機として、2020年東京大会の「文化プログラムに参加すること」をミッションとして、その実現化への機会を伺っていました。そうした中、2016年に私が代表者となって申請した、「芸術・体育領域の融合と共同による2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた『スポーツ芸術表現学』創生プログラムの実施」というプランが、筑波大学の「教育戦略推進プロジェクト支援事業」に採択されました。
そこで、2017年、「スポーツとアートの融合」の実現を目指した実践例として、不要になったボールに絵を描いてアート作品として蘇らせる「リボーン・アートボール」を考案しました。そして私が試作したボール作品を筑波大学内で展示しました。その後は、つくば市内の「スタジオ’S」での展示とワークショップを皮切りに、日本スポーツ振興財団と連携して行った東京都・愛媛県・三重県・長野県での展示や、国内各地での自主企画展示、国体での文化プログラムへの参加等へと広がっていきました。
2018年、リボーン・アートボールは「茨城県文化プログラム推進事業」に採択されました。それ以後、茨城県生活環境部が主導し、企画会社と筑波大学の3者がタッグを組んで事業を実施してきました。その結果、2020年東京大会の文化プログラムに認定され、「アートでオリンピックに参加する」という当初の目的を達成することができました。
ワークショップと作品展示からなる「リボーン・アートボール事業」は、皆さんに知られるにつれて、参加申込みが数分でいっぱいとなるようになりました。ワークショップでは、どこの会場でも小学校の授業時間を超える長時間の集中力や、自由で奇抜な発想が見られ、私たちも驚きの連続で、思わず笑みがこぼれました。何よりも子どもたちの制作中の真剣な眼差しと完成後の達成感のある笑顔に、このプログラムを企画し実施してきて良かったという私たちの満足感がありました。そして、「世界に一つのボールを作ろう」「ボールには空気ではなく夢が詰まっている」「アーティストとアスリートのリスペクトのパス交換」といった私たちのコンセプトに共感していただいたことも嬉しい成果でした。特にコロナ禍でも何とか開催できた2021年は、参加した子どもたちや保護者のみなさんから感謝の言葉をたくさんいただきました。
2028年に開催されるオリンピックロサンゼルス大会では、文化プログラムがどのように実施されるか注目したいところです。
(リボーン・アートボールの実施方法等をお知りになりたい場合は、ご遠慮なく下記メールアドレスまでお問い合わせください。問い合わせ先:ota.kei.ft▲un.tsukuba.ac.jp ※▲を@に置き換えてください)
スポーツ芸術ってなに?
スポーツをテーマとした芸術作品のことを「スポーツ芸術」と呼びますが、1995年に「芸術競技」を知った時から、「スポーツ芸術をもっと身近に感じられるものはないか」と考え続けていました。そして2016年に、スポーツに使われるボール、しかも捨てられるボールに絵を描くことを思いつきました。
筑波大学には優れた成績を残しているスポーツクラブが多数あります。その学生アスリートたちが廃棄するまで使ったボールに「リスペクト(尊敬)の気持ち」を持ち、アートの力でリボーン(再生)させようという思いから、廃棄するボールの提供を各クラブにお願いしました。その結果、サッカー、ラグビー、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、テニスボール、アメリカンフットボール、水球等のボールやバドミントンのシャトルコックなどが集まりました。また、この活動を広げようと、サッカーJリーグ、プロ野球、Vリーグ、Bリーグ、その他、民間のクラブチーム、中学や高校にもお願いしたところ多数のボールが集まりました。
ワークショップは、茨城県からの支援を受けながら、筑波大学で芸術を学ぶ学生とともに県内外各地を巡回して実施してきました。生涯学習センターや美術館の他、カシマスタジアムやケーズデンキスタジアム水戸でのJリーグの試合会場でも開催し、試合を見に来たファンやサポーターがアートボール作りに挑戦しました。参加者は年々多様化し、未就学児をはじめ、特別支援学校の児童生徒、高齢者施設やデイケアに通うお年寄り(最高齢93歳)など、誰でも参加できるプロジェクトとして展開中です。
展覧会は、茨城県つくば美術館、茨城県陶芸美術館等の他、文部科学省情報ひろば、茨城県庁ロビー、筑波大学東京キャンパス等で展示をしてきました。2019年の茨城国体では、文化プログラムとして全国スポーツ写真展(日本スポーツ芸術協会主催)と同時に展示しました。
世界に一つのアートボールを作ろう
リボーン・アートボールのワークショップでは、どこの会場でも多くの子どもたちが参加してくれます。合言葉は「世界に一つのアートボールを作ろう!」です。
制作では、基本的に白色の下地用絵具(ジェッソ)を塗ってから、主にアクリル絵具を使用します。アクリル絵具は、水彩絵具と同じ水性の絵具ですが、乾くと耐水性になるので、展示はもちろん、遊ぶこともできます。会場の都合で絵具が使えない時は、ペンタイブの塗料やシール、ビーズ、モールなどを使ってワークショップを実施しました。
ある時、子どもの隣で過剰なほどに手や口を出したり、反対に手持ち無沙汰でいる同伴者がいましたので、「よろしかったら作ってみませんか?」と声を掛けたところ、最初は遠慮されていた方も、次第に夢中になって、まるで童心に返ったように作りはじめました。それを見ていた子どもたちは嬉しそうで、それまで以上に熱中して作っていました。
このように、「一人で作りたい子どもには一人で。共同で作りたい子どもは共同で」と、アートボール制作ではいろいろなスタイルがあります。
完成したボールは個性豊かな、文字通り「世界に一つのアートボール」となりました。そしてワークショップの最後には、「皆さんが作ったボールの中には空気ではなく『夢』が詰まっているんですよ」と話をしています。
私たちは「アートボール作り」というパスを参加者に送っていますが、どの会場でも、子どもたちからは「とびきりの笑顔」という「ナイス・パス」が返ってきます。完成後には、その場で投げたり蹴ったりして本当に嬉しそうでした。そしてひとしきり楽しんだ後はアートボールを大事に抱えて帰宅していきました。
リボーン・アートボールとSDGs
ここで、昨今よく耳にする「SDGs」に着目してみます。これは2015年に国連が採択した、2030年までに達成を目指す「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:略称SDGs)」のことで、世界的な貧困・環境破壊・地球温暖化・人種差別・児童労働などの解決すべき問題を含んでいます。このSDGsに設定された17の目標の中から、「リボーン・アートボール」と関連が見出せる項目を見てみます。
最も関連があると思われるのは【目標12:つくる責任 つかう責任】で、不要になったボールの再利用によるリサイクルや、資源の循環活用が環境問題への意識の向上につながります。この目標は美術史でも確認でき、たとえば「コラージュ」や「パピエ・コレ」の立体版である「アッサンブラージュ」、空き缶や空き瓶などの廃品を集めて作品にする「ジャンク・アート」があります。また身の回りで不要になったものや、海岸や河辺でゴミや漂流物を集めてアート作品にすることも行われてきました。
次に関連が見出せるのは【目標17:パートナーシップで目標を達成しよう】です。リボーン・アートボール事業が、筑波大学や茨城県、民間企業、小中学校、高校、大学、プロスポーツ団体など、実に多くの方々と「協働」し、共に「成長」してきたことが目標達成のヒントとなるでしょう。
以下に、そのほかの目標との関連を考えてみます。
【目標3:すべての人に健康と福祉を】では、アートは人種・性別・障がいの有無に関わらず、誰でも参加でき、心と身体の「健康」や生きる力を与えてくれるものです。仮に作品を作らなくても、アート作品を鑑賞するだけでも心の健康管理にも良いと言われています。
【目標4:質の高い教育をみんなに】で注目するのは、昨今盛んに言われている「STEAM教育」でしょう。その中にある「A」を示すのは「Art」だったり、「リベラルアーツ(Arts)」の「A」だったりします。仮に「Art」であれば、「STEM科目」と連動させた教育を構築すれば、文理の壁を乗り越えたシナジー効果を生み出す力になるのではないかと考えられます。
【目標5:ジェンダー平等を実現しよう】では、アートに「性別は無関係」であり、「平等は当たり前」な世界ですので、アート関係者にとって「ジェンダー平等」の主張は、むしろ別世界の言葉に思えるのではないでしょうか。とはいえ、アートに限らず、名称に「女流」を用いる、「女流画家」「女流小説家」「女流棋士」などの名称は使われている現実があります。これらは、淘汰されることはなくても、使用頻度は減少していくかもしれません。
【目標10:人や国の不平等をなくそう】では、【目標3】の「すべての人」や、【目標5】の「ジェンダー平等」とも重複することですが、古来言われている「スポーツや芸術に国境はない」という認識を再確認していくこともヒントになるでしょう。
【目標16:平和と公正をすべての人に】に対しても、アートとスポーツを、「する」「みる」「ささえる」といった立場で考えると、それらの「力」を複合的に活用するリボーン・アートボール事業は、国境を作ることなく、また国境を意識せずに関われる平和的な創造活動です。
以上のようにSDGsとの関係をみると、直接関与することもあれば、間接的ではあっても、問題解決への糸口やヒント、さらには目標達成への貢献が期待されます。リボーン・アートボール事業を契機として、SDGsを考えるきっかけや、SDGsを考えるためのスタートにすることができるでしょう。
リボーン・アートボールとウェルビーイング
さて、杞憂に終われば良いことですが、すでに進んでいる少子化によって考えられる、国レベルの研究力低下に対応する中で、特に初等教育における図画工作や音楽、中学校の美術や音楽などの授業時間数に影響が出るのではないかと心配しています。その結果、アートに関わる人材が著しく減少することも予想されます。その場合は、課外活動や校外での教育で補うことになるのかもしれませんが、これらの芸術関連の教科や体育・スポーツなど、「生身の人間」の表現活動を軽視しないでいただきたいと思っています。
さらに、多様な人々と社会全体の幸福を目指す「ウェルビーイング」では、まず一人ひとりが心身ともに良い状態を保つことが必要といわれていますが、それに好影響を与えるアートの果たす役割は大きいと考えられます。
以上のとおり、かつて行なわれていたオリンピック芸術競技の新聞記事に端を発した、スポーツとアートとエコが融合した「リボーン・アートボール」。この事業を教育界の多くの方々に知っていただくとともに、子どもたちには実際の制作に参加していただき、日本国内はもとより世界中に広がっていくことを夢見ています。

筑波大学特命教授、学長特別補佐、ヒューマンエンパワーメント推進局長、筑波大学名誉教授。専門分野は日本画。創画展・個展等で日本画を発表。創画会会友、日本美術家連盟会員。東京藝術大学大学院博士後期課程満期退学。博士(芸術学)。日本スポーツ芸術協会理事、筑波大学蹴球部副部長。主な著書に『絵画の教科書』(日本文教出版)、『ニッポンの奇天烈な絵画』(綜合図書)(いずれも共著)がある。