学び!と道徳2
学び!と道徳2
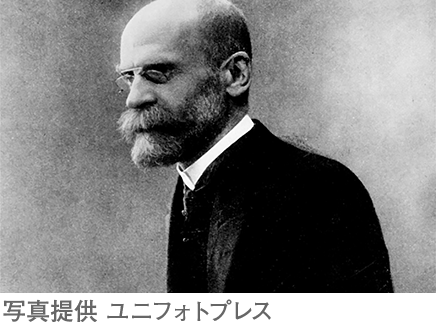
(※2022年6月執筆)
過去に大流行したスペイン風邪などは3年経つと公衆衛生の徹底や集団免疫ができ収まったようですが、新型コロナの感染もようやくピークを越えてきたようです。マスクの着用や海外への渡航制限なども緩和され通常の生活が戻りつつあります。
そのような中、ロシアが突如としてウクライナに侵攻し、住宅・学校・病院などをことごとく破壊し、多くの罪のない一般市民を虐殺するという国際法にも抵触する前時代的な蛮行を行っています。このような行為に対して世界中から非難の声が沸き上がり、ウクライナへの支援が起きていますが、ロシア国内では多くの国民がプーチン大統領を支持し、さらに世界にはロシアの侵攻を認める国もあります。
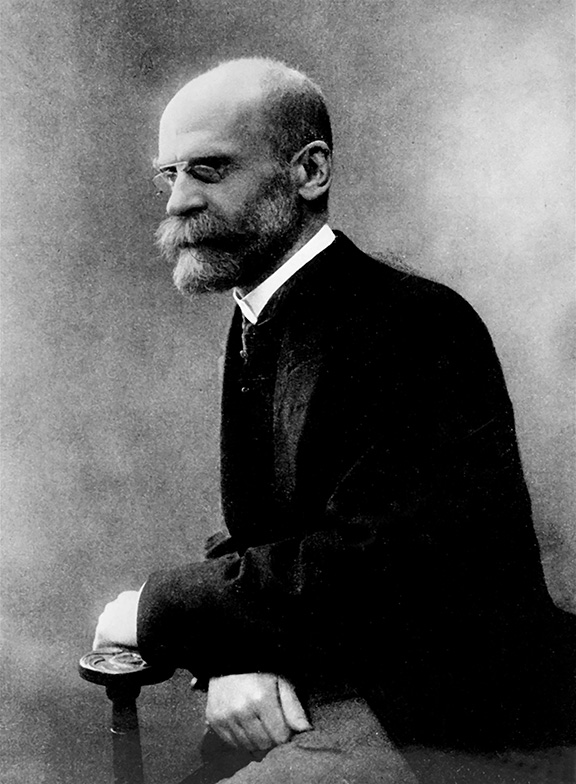 エミール・デュルケム
エミール・デュルケム
写真提供 ユニフォトプレス フランスの社会学者で教育学の分野においても多大な功績を残したエミール・デュルケムは著書『道徳教育論』の中で「過去や現在を問わず、われわれの教育理想は、その細目にいたるまで、じつは社会のなせる業なのである。われわれが則るべき人間像を画いて見せるのは社会であって、社会組織のあらゆる特性は、この人間像のうちにいきいきと反映されているのである。」と述べています。
ロシアの侵攻は国際社会のなせる業であります。我々は、世界平和を具現化するには、人間はどうあるべきか社会を通して考えていかなければならないと思います。
参考までにデュルケムは著書の中で、道徳的な生活の根底をなす基本的なものとして3つの道徳性を上げています。
①規律の精神…………道徳的行為には規則性が認められる。規則には従わなければならない権威があり、人間は自己抑制の義務が必要である。
②社会集団への愛着…道徳的行為は個人を超越した集団目標である。すなわち社会的存在としての活動である。
③自律の精神…………道徳規則には命令性とともに自発性がある。自由意思によって受け容れられることが必要である。
ロシアの侵攻が早く終了して、ウクライナが平和な生活を取り戻すことを、切に願っています!!
さて、今回は前回の中で出てきた教師のファシリテーションの在り方について、実践事例をもとに進めていきたいと思います。
1 ファシリテーション
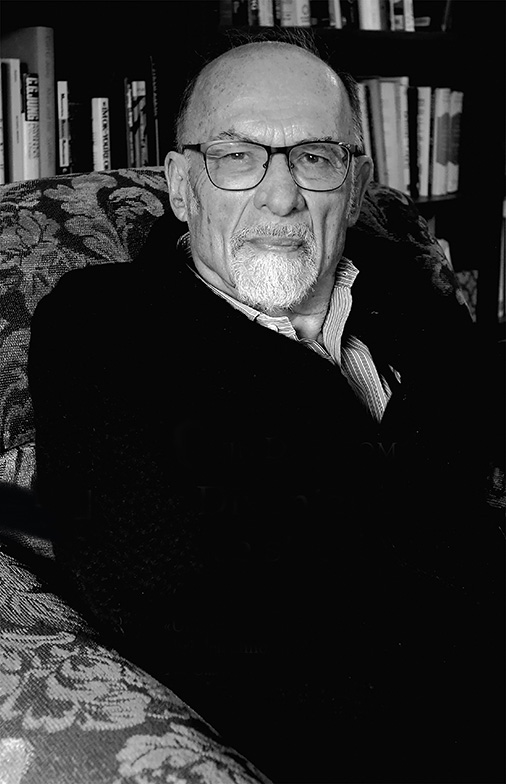 アーヴィン・D・ヤーロム
アーヴィン・D・ヤーロム
写真提供 ユニフォトプレス
1.配慮(支援、受容、関心、賞賛)
2.意味づけ(説明、解釈、枠組みの提示)
3.情緒的刺激(自己開示を迫る、挑発)
4.実行機能(目標設定、時間管理)
この4点で、1と2は徹底するが、3と4は無理強いをしないと述べています。」
2 事例研究
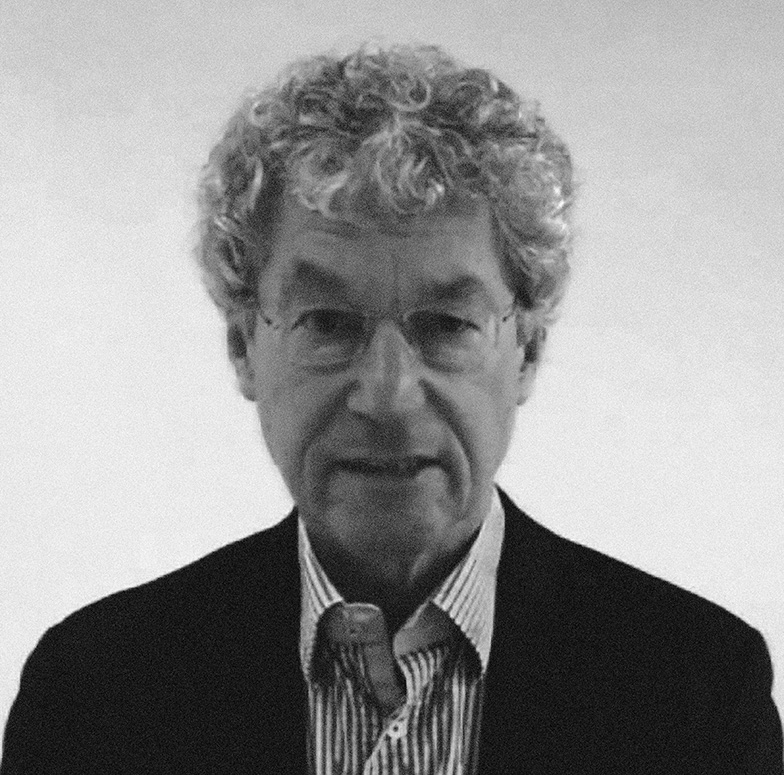 F・コルトハーヘン
F・コルトハーヘン
写真提供 ユニフォトプレス
今回の「ファシリテーション」はいかがでしたでしょうか。多くの先生方は意識せずに行っていることもあると思いますので、一度あらためて授業を振り返ってみてはいかがでしょうか。なお、最後に取り上げたコルトハーヘンの「リフレクション(振り返り)理論」は、教育(評価、教員の授業力の向上など)、看護、保育、スポーツ、企業の人材育成など様々な場面で、より深い、より主体的な学びを引き出す方法として近年活用されています。
【参考文献】
- 「道徳教育論」著:エミール・デュルケム/訳:麻生 誠、山村 健/講談社学術文庫/2010年5月13日
- 「図解 組織開発入門 組織づくりの基礎をイチから学びたい人のための「理論と実践」100のツボ」著:坪谷邦生/ディスカヴァー・トゥエンティワン/2022年2月18日
- 「リフレクション入門」編:一般社団法人 学び続ける教育者のための協会(REFLECT)/著:坂田哲人、中田正弘、村井尚子、矢野博之、山辺恵理子/学文社/2019年1月30日