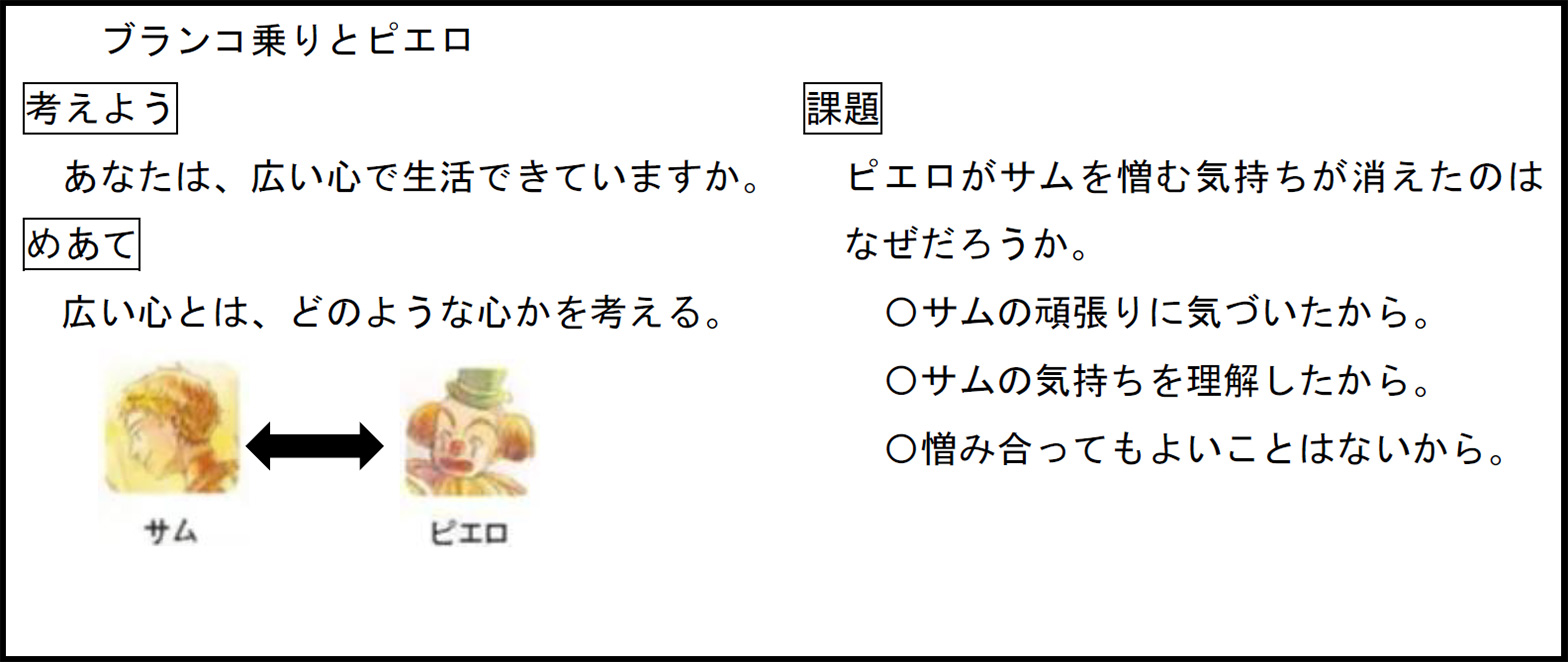小学校 道徳
小学校 道徳

1.はじめに
OECD(経済協力開発機構)はEducation2030プロジェクトにおいて、「エージェンシー(Agency)」を中核的な概念として位置づけ、児童・生徒の主体的な学びについての指針を示している。これを受け、群馬県教育委員会では、第4期教育振興基本計画の最上位目標のキーワードに「エージェンシー」を示し、エージェンシーを発揮する「自律した学習者」を目指し、「自分で考えて、自分で決めて、自分で動き出す」児童・生徒の育成を進めている。
本研究では、道徳科の授業における「自律した学習者」について、「主題を自分ごと化して捉え、対話や交流によって道徳的価値について考えを深め、自分や社会との関わりから、よりよい自己の生き方について見つめ直している児童」と設定した。この児童像の実現に向けて、「話し合い活動」と「課題探究型の授業展開」の2点について工夫をした実践を行った。
本実践記録は、令和7年2月に実施した授業であるが、今回紹介する授業実践は、令和6年度の1年間を通して実践してきたものである。また、「第58回 関東地区小学校道徳教育研究大会 千葉大会」で発表した内容が基となっており、その後に行った授業改善も追記した内容となっている。
2.話し合い活動の工夫
本研究では、話し合い活動をさらにステップアップさせ、児童がエージェンシーを発揮して学びに向かうために、ファシリテーション能力を向上させ、主体的に話し合い活動を進めるための工夫として、以下の3つの手立てを講じた。
 道徳科の授業では、児童のファシリテーション能力を高めるために、3人組での授業形態を採用した。具体的には、机を3つ横一列に並べ、3人組をつくる。3人組のうち、中央の児童がファシリテーターとなり、両端の児童の考えや意見をつなぐように話し合う工夫を行った。これは、ファシリテーション能力を向上させるだけでなく、児童の本音を引き出すことにも有効であると考えた。
道徳科の授業では、児童のファシリテーション能力を高めるために、3人組での授業形態を採用した。具体的には、机を3つ横一列に並べ、3人組をつくる。3人組のうち、中央の児童がファシリテーターとなり、両端の児童の考えや意見をつなぐように話し合う工夫を行った。これは、ファシリテーション能力を向上させるだけでなく、児童の本音を引き出すことにも有効であると考えた。
 先述のトリオ・ディスカッションを行うにあたり、児童の座席を毎時間ランダムで設定した。これまでの授業において、さまざまな話し合い活動の工夫を行ってきたが、人間関係の慣れが生じ、話し合い活動を通した深い学びになっていなかった実態を受け、毎時間ランダムに3人組の座席を設定して授業を行った。これにより、多くの児童がファシリテーターを経験したり、多様な見方や考え方に触れたりすることができる機会となることを意図した。この結果として、固定化された友達関係内での話し合いや班活動における暗黙的なルール(ワークシートを回し読みするなど)が生じず、常にさまざまな友達に自分の考えや立場を伝える必要性をもたせることができた。
先述のトリオ・ディスカッションを行うにあたり、児童の座席を毎時間ランダムで設定した。これまでの授業において、さまざまな話し合い活動の工夫を行ってきたが、人間関係の慣れが生じ、話し合い活動を通した深い学びになっていなかった実態を受け、毎時間ランダムに3人組の座席を設定して授業を行った。これにより、多くの児童がファシリテーターを経験したり、多様な見方や考え方に触れたりすることができる機会となることを意図した。この結果として、固定化された友達関係内での話し合いや班活動における暗黙的なルール(ワークシートを回し読みするなど)が生じず、常にさまざまな友達に自分の考えや立場を伝える必要性をもたせることができた。
 中心発問について児童が話し合いを通して学びを深める場面において、これまでは、ワークシートなどを持参しての話し合い活動を行う授業が多く展開されてきた。しかし、児童の活動を詳しく見てみると、「ワークシートを見せ合うだけ」「友達のワークシートの記述を写すだけ」「ワークシートの記述を読み上げるだけ」になってしまっている様子が数多く見られた。そのために、本実践では、子どもたちにワークシートを持参させない「手ぶらトーク」を導入した。また、手ぶらトークを行う際は、児童の話し合いたい内容などに応じて教室内のフリースペースに「話し合いを行う場」を設定した。この結果、児童が友達の意見をワークシートに書く活動がなくなり、話し合いに集中することができるようになっただけでなく、さまざまな見方や考え方に触れることで、考えを広げたり、深めたりすることができるようになった。
中心発問について児童が話し合いを通して学びを深める場面において、これまでは、ワークシートなどを持参しての話し合い活動を行う授業が多く展開されてきた。しかし、児童の活動を詳しく見てみると、「ワークシートを見せ合うだけ」「友達のワークシートの記述を写すだけ」「ワークシートの記述を読み上げるだけ」になってしまっている様子が数多く見られた。そのために、本実践では、子どもたちにワークシートを持参させない「手ぶらトーク」を導入した。また、手ぶらトークを行う際は、児童の話し合いたい内容などに応じて教室内のフリースペースに「話し合いを行う場」を設定した。この結果、児童が友達の意見をワークシートに書く活動がなくなり、話し合いに集中することができるようになっただけでなく、さまざまな見方や考え方に触れることで、考えを広げたり、深めたりすることができるようになった。
3.課題探究型の授業展開の工夫
 既存の授業形態からの脱却と児童・教師の授業観の転換を図るために、「課題探究型の授業展開の工夫」を行った。この授業展開は、児童が道徳の授業における中心発問を「自ら設定」することで、主題を自分ごと化して捉え、対話や交流によって道徳的価値について考えを深め、自分や社会との関わりから、よりよい自己の生き方について見つめ直す授業への転換を意図して実施した。
既存の授業形態からの脱却と児童・教師の授業観の転換を図るために、「課題探究型の授業展開の工夫」を行った。この授業展開は、児童が道徳の授業における中心発問を「自ら設定」することで、主題を自分ごと化して捉え、対話や交流によって道徳的価値について考えを深め、自分や社会との関わりから、よりよい自己の生き方について見つめ直す授業への転換を意図して実施した。
年度当初は、児童一人ひとりが教材文から「めあて」に沿った学習課題(モヤモヤ)を設定し、学級内で授業を通して深めたい課題(1~3つ程度)に絞り、トリオ・ディスカッションや手ぶらトークを通して各自の納得解を導き出す授業展開を行った。
児童A |
2 |
児童C |
1 |
児童E |
2 |
児童G |
2 |
なぜ、父は噂が広がっても診察を続けたのか。 |
父の姿を見てどんな感情がこみ上がってきたのか。 |
なぜ、自分も病気にかかる可能性があるなか、患者さんを受け入れたのか。 |
なぜ、お父さんは危険なのに診察を続けていたのだろう。 |
||||
児童B |
3 |
児童D |
2 |
児童F |
2 |
児童H |
2 |
なぜ「県内初のコロナ感染者が父のクリニックだ」と噂を立てられたのか。 |
どうして変な噂が立っていても自分がかぜの症状になったとしても諦めずに診察し続けたのか。 |
お父さんはなぜ病気にかかるリスクがあるのに暑い中患者を診察するのか。 |
父はなぜ危ない状況でも診察を続けたのか。 |
||||
年度始めの課題づくりの児童の記述(一部)
しかし、当初は授業時間のマネジメントが不十分であったため、本時で深めたい学びに達していない授業が多くなってしまった。そのため、さらなる授業改善を行った。そこで取り入れたのが、教材文に対する中心発問を児童一人ひとりが考えて絞り込むのではなく、トリオ・ディスカッションを活用した中心発問づくりである。課題づくりの授業を通して、児童一人ひとりが課題をつくる力が十分に身についてきたことから、トリオ・ディスカッションで課題づくりを行う際においても、児童一人ひとりが自分の考えをもちつつ、友達と話し合い活動を行うことで、よりよい洗練された課題をつくることができると考えたためである。
|
|
1班 |
6班 |
九十四歳になってまで、なぜ卒業することを諦めなかったのか。 |
なぜ、そんなに小学校を卒業したいと思ったのか。 |
2班 |
7班 |
校長先生に励まされたゴゴは何を思って学校にまた通いはじめたのか。 |
なぜ、ゴゴは試験に落ちたけど諦めきれない気持ちがあったのか。 |
3班 |
8班 |
なぜ、九十四歳で学校に通おうとしたのか。 |
なぜ、九十四歳になってから学校に通ったのか。 |
4班 |
9班 |
九十四歳になっても学ぼうとする気持ちを支えているものはなんだろう。 |
なぜ、卒業試験で数点足りなかったのに諦めずに学校に戻って勉強することを続けられたのか。 |
5班 |
|
ゴゴはなぜ卒業するのを諦めなかったのか。 |
|
年度末の課題づくりの児童の記述(一部)
ここで、課題をつくる際における児童のよりどころになるのが、教材文における「主人公(登場人物)の心情の変化に着目する」ということである。教師が、教材研究を行う際の視点をあえて児童に示し、考えさせることにより、「課題を見いだす力」を伸長させるとともに、自ら見いだした課題を自分たちの力で解決しようとする「主体的に学習に取り組む態度」の育成につなげ、「自律した学習者」の育成を図った。
4.実践報告
(1)主題名
広く受け入れる心
(2)教材名
ブランコ乗りとピエロ
(3)教材について
本教材では、サーカス団の2人の登場人物(ブランコ乗りのサム、ピエロ)の心情の変化を通して、自分とは異なる他者の気持ちや考え方を受け入れる方法を考えることができる。また、助け合いや協力し合える人間関係の形成についても深く考えることができる。
児童の学齢を考えると、少しずつ他者の考えを受け入れたり、理解しようとしたりする気持ちが芽生え始める時期である。しかし、人の心の弱さに着目すれば、自分が他者より優位に立ちたい気持ちをもったり、自己中心的な言動や行動をしてしまったりすることを自覚したうえで、どのように行動するのがよいのかが求められる。その際、相手や他者の立場、周りの状況などを総合的に判断したうえで、自分と違う考えや思いとの折り合いをつけたり、新しい解決策を見つけ出したりすることで、よりよい人間関係が形成されることに気づかせたい。
(4)本時のねらい
サムとピエロの気持ちや考え方の違いについて捉え、相手を広い心で受け入れたり、理解したりして、異なる考えをもつ他者と相互に理解し合うことが、考えや価値観を広げることにつながることに気づかせ、自分と異なる考え方について寛容な気持ちで受け入れようとする意欲を育てる。
(5)展開例
学習活動 |
◇教師の支援 ☆評価(方法) |
|
|---|---|---|
導 |
1.自分自身について考える。 |
|
○あなたは、広い心で生活することができていますか。 |
◇トリオ・ディスカッションで具体的なエピソードを引き出し、ファシリテーターの児童がファシリテートできるよう、「例えば」「具体的には」などの話型を示す。 |
|
展 |
3.教材文の範読を聞く。 |
|
4.教材文に対する課題を考える。 |
◇範読後、すぐにトリオ・ディスカッションで課題を考えさせ、ICT機器を活用して学級内で共有する。 |
|
6.絞り込んだ課題について、トリオ・ディスカッションで話し合う。 |
◇課題解決のためのトリオ・ディスカッションや手ぶらトークをしている児童に対し、必要に応じて、多面的・多角的に考えたり、見方や考え方を広げたりすることができる補助発問を行う。 |
|
8.意見を共有する。 |
||
|
||
終 |
9.教師の説話を聞く。 |
◇教師自身の体験談(仲違いしたエピソードなど)を簡潔に紹介し、その時の失敗や解決策を話す。 |
(6)板書計画
5.考察とまとめ
本実践における児童の振り返りでは、「今まで広い心というのはただ優しい、ただ何でも許してくれるだけの人だと思っていたけれど、広い心は自分のことだけを優先して相手のことをしっかりと知らないまま勝手に妄想して叱るのではなく、相手のことを知り、理解したうえで相手にしっかりと自分の気持ちを伝えることが大切なのだと思いました。」や「広い心について考えてきて、自分は今まではすぐ怒ったりしていたけど、この授業を通して友達とけんかしてもすぐ怒るんじゃなく、落ち着いて話したいと思いました。」「友達に対して広く受け入れる心をもっていきたい。100%は難しいかもしれないけど70%くらいは受け入れられるように生活していきたい。」「これまでは広い心というものがあまり分からなかったけど、広い心とは、自分の非を認めたり相手が頑張っていることを褒めたりして、優しく接する心のことなんだなとこの授業を通して思った。」「今までは、広い心は何でも受け入れてくれるだけの人だと思っていたけれど、この授業を通して、自分のことも相手のことも認めてあげることが大切だと思った。認めてあげるには、まず相手のいいところを探してみるのもいいと思いました。」などの記述が見られた。児童は、相互に理解し合うことのよさに気づくことができていただけでなく、今後の生活において、児童自身がどのような態度で生活していきたいかについても記述することができていた。
本研究における自ら課題を設定する活動は、4月より道徳の時間を中心に繰り返し行ってきた。道徳の授業においては、課題をつくるだけで授業時間が終わってしまうことが年度始めではしばしば見られたが、徐々に課題をつくる時間が短縮され、本実践時においては、3分間のトリオ・ディスカッションで、ほぼ全ての3人組が課題をつくれるようになった。また、めあてを意識させることで、教師の想定している中心発問からも大きく外れることがなく、教材文を一度範読するだけで課題をつくることができるようになった。
本実践においては、めあてを意識した課題づくりを児童が行ったことで、想定していた中心発問が児童から出てきた。また、課題を絞り込む場面では、ピエロの気持ちを理解することは容易であると児童が判断し、「ピエロは、すぐ分かる」とのつぶやきをしていたことから、サムの気持ちの変容についての課題を本時の中心発問として絞り込むことができた。
本実践では、これまでの道徳の授業に対する問題意識を打開するための方法として、課題(中心発問)づくりを通した児童の主体的な学びのスタイルをデザインしてきた。課題づくりを授業に取り入れることに対して、多くの先生方は「難しすぎる」「授業がめちゃくちゃになってしまい、ねらいから外れてしまう」「一部の訓練された学級で行った取り組み」と感じられるかもしれない。本実践は、公立小学校の平均的な学級での取り組みであり、令和6年度の指導のみで、児童が成長し実践できたものである。本実践を通して私が、最も大切だと感じることは、いかに子どもたちの可能性を教師が信じ、任せることができるかということである。子どもたちは、もともと「自律した学習者」になるだけの素質を一人ひとりがもっており、私たち教師はその素質を引き出すための手立てを勇気をもって講じていくことが求められているのではないかと思う。
※本実践は、令和6年度に筆者が前任校である「みなかみ町立古馬牧小学校」で実践したものである。