 |

 |
| 1.はじめに |
国際教育到達度評価学会(IEA:International Association for the Evaluation of Educational Achievement)が実施した学力調査によると,1964年から1995年までの我が国の国際順位は第1位〜第3位であったが,1999年および2003年の調査では第3位〜第6位に下降している(※注1)。これらの調査からは,我が国の生徒たちの学力水準が世界レベルでは低下傾向にあるといわざるを得ないことになる。このような報道をもとにして,若い世代に期待される「学力」の水準が,社会のエリート階層だけの関心事ではなく,広く国民世論の注目する対象になってきている。
一方,学力が低下しているのは我が国の高校生や大学生だけではない。アメリカ合衆国では1980年代に子供たちの学力不足が社会的な問題となり,「アメリカ国民が常識として知っておかねばならぬ事柄を教える教養科目を初等・中等教育の根幹に据えるべきである」との立場から,いわゆる教養リテラシー(Cultural Literacy)の重要性をHirschが多面的に立証している(※注2)。そこでは,具体的な方法として「アメリカの基礎教養5000語」と題したリストを公表している点がアメリカの国情を反映しており斬新である。
我が国では,個性を尊重する教育が必要だとの方針で,いわゆる「ゆとり教育」が1996年から導入された。さらに,2000年には「21世紀日本の構想」懇談会が公表した報告書(※注3)において,義務教育の教科内容を5分の3にまで圧縮するという小中学校の週3日制を提案していた。しかし,大学教員による学生の学力不足を指摘する告発書(※注4)である『分数が計算できない大学生』の書名とともに学力問題が広く社会的に認知されるようになり,何らかの具体的な対策が必要だとの世論が形成されてきた。そして,国際数学・理科教育動向調査TIMSS2003報告(※注5)およびOECDによるPISA2006の結果(※注6)を踏まえて,2008年2月に文部科学省は2011年度から3%〜6%の授業時間数増大を指示し,理数系の科目については2009年度から15%の時間数増を指示する学習指導要領(※注7)を発表している。
もちろん,この間の議論は平坦ではなく,極端な意見としては,「大学生ですら間違えるような分数計算は小学校の算数から外せ」とか「実生活では二次方程式の解法など使わないから教えなくても良い」という暴論まであった。このような「難しいから外す」とか「難しいものは教えない」という論理には歯止めがきかず,「難しいから中学校や高等学校からも外す」となる。さらに,「難しいものは外す」の対象を広げると,「算数・数学は難しいから教えない」となる。また,「英語も古典・歴史・社会も,難しいから教えない」という結果になる。これは,「知の営み」を放棄することにつながる。
|
|
|
 |
| 2.科学リテラシー |
一般に,学力を調査するときには,小学生から高校生まで(最近では大学生も含む)の集団を対象として,生徒たちが到達していると推定できる学力の実態を実証的なデータとして収集している。国際的な学力の比較をするとき,多くの場合には,数学や理科を対象に調査が実施されるのであるが,それはつまり,「数学リテラシー」および「サイエンス(理科)リテラシー」を調べていることになる。
そして,アメリカ国内においては,生徒たちの習得している理数系の知識が国際平均を大きく下回っていることが問題になっている。また,その原因が教員の学力不足や一般社会人の科学リテラシー不足にあると指摘されている。すなわち,多くの学生は科学(サイエンス)や数学の学位を持たない教員の授業を受けており,大半の小学校の教員は大学レベルの科学さえ履修していないといわれている。そのような状況を改善する具体的な活動をしているレオン・レーダーマンは次のように述べている。『学校が世に送り出すべきなのは,変化に対応できる人材であり,科学に基づいた技術で鍛えあげられた人材である(※注8)。』
実際,全米科学振興協会(AAAS)は,アメリカ全体の科学リテラシー向上を目指す「プロジェクト2061(※注9)」を1985年にスタートさせている。これは,すべてのアメリカ人が高校卒業までに身に付けるべき科学技術・数学の知識・技能・態度(科学リテラシー)を検討した上で,それを実現するためのカリキュラム改革や教育支援態勢を整備しようというものである(※注10)。
我が国にも科学リテラシーの教育を推進し,その定着を進めようという運動がある。それは,「二十一世紀の科学技術リテラシー像〜豊かに生きるための智プロジェクト」とか「科学技術の智プロジェクト」と呼ばれている(※注11)。そこでは,我が国のすべての人々が,年齢や性別・就学歴にかかわらず,成人するまでに身に付けてほしい科学リテラシーを検討し,その普及を目指そうとしている。ここで,科学リテラシーとは,これから育っていく世代が成人となる2030年以降の時代を想起し,すべての人々が様々な職種・年齢などの相違を超えて協働して,さまざまな国際的課題にも取り組み,心豊かで健康的な社会を作っていくために,共有すべき知恵をまとめようとしたものといえる。
この「科学技術の智プロジェクト」のメンバーである渡辺正隆は,次のように述べている。『科学リテラシー教育とは,単なる知識の暗記ではない。知識だけならば,必要に応じて百科事典や教科書,場合によってはインターネットも活用して情報を収集できる。大切なのは,習得した知識を活用し応用できる柔軟性である。一般に,予期せぬ状況での多くの事故は,ちょっとしたリテラシーの活用で予防できることも多いのである。そのような科学的な知恵が,科学リテラシーなのである。』
(1)科学的な見方や考え方
さて,「科学的な見方」とか「科学的考え方」のポイントはどこにあるのであろうか。ノーベル物理学賞を1965年に受賞した朝永振一郎は,科学教育についても明快な考え方を示している。朝永振一郎の有名な色紙(※注12)には次のように書かれている。
『ふしぎだと思うこと,これが科学の芽です。よく観察してたしかめ,そして考えること,これが科学の茎です。そして最後になぞがとける,これが科学の花です。』
また,次のように科学の特徴を説明している。『科学というものは,いつの時代においても,その前の時代の科学を踏まえて進められ積み重ねられてだんだんにできてきたものです。あるときは前の時代の考え方を踏襲しつつそれをより堅固に密度高く仕上げ,あるときは前の時代の狭隘な考え方を打破することによって新天地を開いていく,科学とはこうして変化していくものです(※注13)。』
ところで,我が国の「科学技術の智プロジェクト」では,「科学技術」という用語が用いられているが,それを「科学を応用した技術」というように早合点してはいけない。一般的な用語として,「科学」と「技術」とは全く別の概念であり,むしろ正反対の方向性をもつものだからである。旧総理府には「科学技術庁」という役所(※注14)があったので,そのような誤解が生じたのかもしれないが,役所名の英文表記は「科学」と「技術」がandで併記されており,「科学と技術」という意味で正しい表記となっていた。実際,「科学」は学問の体系という意味であり,その基本は「観察と考察」にある。人類社会で発見されてきた知識の集積を意味しているのである。他方,「技術」は人間が生み出したものであり,人間の知識を基礎に置いたものとなるのは必然であり,技術には価値が付随する。
(2)計算機リテラシー
アメリカの「プロジェクト2061」における「科学リテラシー」の一つとして,「計算機リテラシー」をどのように位置付けているか検討してみよう。まず,コンピュータで扱う情報については,次のように述べている。『いかなる情報も二項選択ビットの列として符号化できる。』この記述は極めて明快であり,誤解のおそれもないといえよう。
また,コンピュータの動作についても明快である。『コンピュータは本質的に,論理演算を行えるような方法で接続された非常に大規模なオン/オフ・スイッチの列である。コンピュータは極度に複雑又は反復的な演算指示を,人間が行う数百万倍もの速度で実行することができる。』すなわち,コンピュータが「大規模なスイッチの列」であるとの説明が,ここでは本質的なのである。
また,われわれ人類の歴史をさかのぼってコンピュータの発明がどのような位置づけになるかを確認しておくことも重要である。その意味では,我が国のプロジェクト報告書において,いまだに世界最初のプログラム内蔵式コンピュータがENIACであるとの記述が残っているが,このような誤解は早急に訂正されるべきである(※注15)。また,同報告書に含まれている,プログラム内蔵というアイデアの考案者がノイマン一人であるかのような記述は,更なる誤解の原因ともなりかねないのであり,歴史的な検証報告などを参照し誤った知識の流布を防止する必要がある(※注16・17)。
|
|
|
 |
| 3.教科「情報」と科学リテラシー |
我が国の後期中等教育(中学校,高等学校など)においては,2003年度から教科「情報」が新設され,必修科目として実施されている。そして,文部省(現文部科学省)による高等学校学習指導要領では,「科学的な見方や考え方を養う」ということになっている(※注18)。つまり,「科学リテラシー」の一部としてこの科目を位置付けていることになる。したがって,適切な指導を行うためには,単にコンピュータのハードウェアに精通しているとか,特定のソフトウェアに習熟しているだけでは不十分であり,「科学」および「技術」に基づいた「科学リテラシー」の準備が必要だといえる。学校現場においては,生徒達にコンピュータの操作を教えるだけでなく「科学的理解」を促進するための工夫が望まれている。指導要領の解説によれば,科学的理解とは,「情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と,情報を適切に扱ったり,自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解」となっているのである。そこで,科学的理解を構築するために教科「情報」ではどのような工夫が可能かを具体的に考えてみよう。ここでは,科学の芽として「ふしぎだと思う」という視点から検討する。
(1)ハードウェアの科学的理解
まず,最近の大学生や高校生が日常的に利用している情報機器として,携帯電話やテレビ受像機・ディジタル撮像機・携帯音楽再生機,さらにはプリンタや腕時計・電子辞書などがある。そして,これらの情報機器については,多くの場合にその機能が単純明快であり,それらの働きに対して,「ふしぎだと思う」機会は少ないのかもしれない。例えば,腕時計の場合,太陽電池によって駆動される電波制御の時計であれば,その表示方式がアナログ方式であれディジタル方式であれ,現在時刻を読み取る訓練は小学校の低学年で完了している。海外旅行をしたときに現地時間を表示する機能を使えるか否かが問題になるぐらいであろう。しかし,そこにはボタンが2〜3個装備されており,その適切な操作方法をマニュアルから読み取り,理解するにはその制御ソフトウェアについての素養が必要になる。
コンピュータは電子装置であり,データ入力部分は機械的道具を応用している。キーボードは典型的なスイッチの並びであり,その動作自体は,日常生活などでよく理解されている。スイッチをオンにすれば,該当する機器の電流が制御され,その反応が現象として確認できる。しかし,キートップに配置された英字の配列が国際規格ではQWERTY方式となっている理由を理解するには,適切な解説書(※注19)の助けが必要になる。この配列は手動タイプライタの時代に発明された方式ではあるが,当時の機械的な制約が原因となって高速タッチを妨げるような配列になっていたというデマなどに惑わされてはならない。
(2)ソフトウェアの科学的理解
一方,ソフトウェアの働きは「ふしぎ」の宝庫といえよう。自宅の机上にあるノートパソコンを使って,電子メールの送受信をしたり,インターネットブラウザを使って様々な検索をしたり,ワープロソフトを使ってレポートの原稿を作成し,プレゼンテーション用のファイルを作成したりするなど,色々な作業を同一のコンピュータで実行できるのである。
携帯電話のようにメール専用であるとか,ディジタルカメラのように撮影専用であれば,そこに専用のソフトウェアが実装されていて,ハードウェアを制御していること自体は理解しやすいためか,中学生や高校生などが,色々なボタン操作に習熟する早さには感心させられる。それらのソフトウェアを構築する仕組みをある程度まで理解しておくことが望まれるのであるが,その科学的理解が課題になっている。
|
|
|
 |
| 4.おわりに |
我が国の高校普通科において,教科「情報」が必修科目として導入されてから5年が経過している。すなわち,大学生の3年次生まではその大半が高校で「情報」の授業を履修してきていることになる。ところが,一部の高校現場では,ワープロやブラウザの操作を練習するだけになっていて,本来の情報教育から程遠いものになっているとの心配がある(※注20)。実際,コンピュータを操作して,データを加工するだけならば,誰でもできる。しかし,ソフトウェアの仕組みを理解し,さらにはソフトウェアを設計するには,相当の修練および修行が必要である。
本報告では,「科学リテラシー」という視点から,教育現場で課題になっている学力不足(※注21)や「智の営み離れ」の対策を検討してきた。しかし,このような現状をもたらした要因は,主として我々自身の社会にあるということも事実である。従来の教育は,単に知識を伝達することで知的権威を保つものであって,「知の営みの結果を伝える教育」が中心となっていて,知的権威の継承や次代の権威者の養成にすぎないといわれる(※注22)。ところが情報時代といわれる現状では,インターネットをはじめ様々な媒体によって,情報が一般の人々に開示されるようになり,本来の学問のあり方としての「学生とともに知の営みにあずかる教育」が必然的に可能になっている。
|
|
|
 |
| |
|
 |
 |
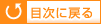 |
|
 |
 |
 |