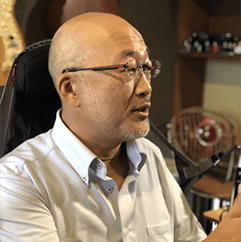学び!と美術
学び!と美術
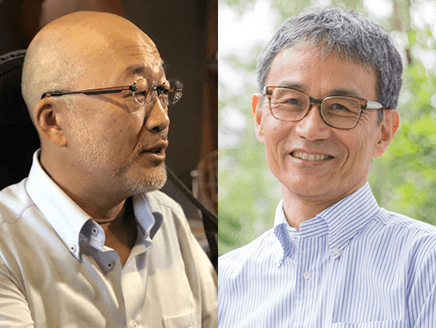
前回は、「アートの生存価がある」という話と、「教育実践を主客不分離にとらえる」ことについて考えてみました。今回、引き続き有元先生がご登場いただき、事例を通して「教育実践をどのように眺めるか」まとめてみたいと思います。
授業はグループワーク

まず、鈴木先生は、「私は途中で『いろいろな用具も使ってみる?』と声をかけることができませんでした」と語っています。たぶん鈴木先生は「声をかけてはいけない」と直感的に察知したのでしょう。「K君に、いろいろな用具は今必要ないと思った」と述べていますが、それは察知した後に考えたことで、声をかけなかったのは、むしろ集中して製作する子どもの姿を我が事のように感じた自然な態度だろうと思います。
一方で、積極的に子どもに主題や理由などを尋ねる場面もあります。鈴木先生は「何を感じているのかな。どんなイメージが広がりつつあるのかな」など子どもの発想や構想を知るのが「何より楽しみ」だからです。「楽しみ」とは、教師と子どもが同じ位置にいる感覚から生まれる言葉だと思います。また「尋ねる」は、発想や構想という訳のわからないものを、お互いに可視化する行為です。
「声をかけない」からこそ子どもに能力の発揮が保障される。一方で「声をかける」ことで子どもとイメージを共有し、発想を確かにする。どちらも等しく「子どもの能力」を実現させていて、それを一緒に達成する共同実践者が子どもと教師です。
難しい学校も拝見するのですが、少なくとも授業が成立していることは、まずもって、そこにいる多くの参加者に「共同の意思」が「共有された事態」です。授業では、子どもたちが「そこにいること」をしていて、「出ていくことをしない」のです。同様に「手をあげること」をしたり、「頭を使うこと」をしたり、「話してる子を見ること」をしたりします。また、「ロッカーにしまったカブトムシの世話をしに行くことをしないこと」をしたり、「立ち歩くことをしないこと」をしたりしています。街角の「雑踏」にはこれほどの「共同の意思」はないです。
あたりまえの授業が素晴らしい
教育を皆が共同で発達する実践だ、と読み替えていきたい。
教育はみんなで唄う歌のようなものだ。歌は誰かの声が歌なのではなく、個々の声の総和以上の全体が歌だということだ(※3)。教師と児童生徒は、拍手における右手と左手である。拍手の音はどちらの手のひらから出ているか?今その場で、拍手をしてみて、確かめてもらいたい。よく見て、よく聴いて、何度も繰り返して、確認してみよう。拍手の音声は右手からも左手からも鳴ってはいない。拍手の音声は右手と左手の関係の効果として一体として空気を震わす。水がその構成要素である酸素そのもの、水素そのものとは異なる性質を持つように、全体は部分の総和をこえている。ヴィゴツキーは共同作業の意義について以下のように記した。
集団を形成した一人一人の子供は、ある種のより大きな存在と同化することで、新たな質と特殊性を獲得した。集合的活動(コレクティブ・アクティビティ)と協同の過程において、かれの水準は高められる。前からそこにあったというわけではなく、まさにグループづくりのその過程において、新たな形の生き方(人格)があらわになるのだ。(Vygotsky、2004、p.211) 社会の縮尺図である教室は、個々の要素の足し算を超えている。できる−できない、うまい−下手、関与−無関与、初心−熟練、そうした多様な要素が混じり合って全体の効果をつくりあげるアンサンブルであり、その意味で社会の小宇宙だと言える。教科を学ぶだけではない。教科を学ぶことを通して、社会生活の基礎である「一緒に生きる技術」(※4)を、教科で学んでいる。
「編み続けたい」なんですよね。子どもも教師も、絵も、土も、主題も……。授業におけるすべてを並置された資源としてとらえ、それを編み続けるのが「授業だ」というとらえ方なのでしょう。
鈴木先生の連載の題名を、あらためて見ると「ともにかなでる図工室」なんです。子ども、先生、材料や用具、窓や光など、それらすべてがアンサンブルするインプロビゼーションの現場、それこそが「教育実践の基礎としての人間の弁証法的理解」なのかなと思いました。
2回にわたった対談、多くの知見を得ることができました。有元先生、ありがとうございました。
※1:「ともにかなでる図工室 第四回 データの海」
https://www.zukonomikata-nichibun.net/tomonikanaderu04/
※2:香川秀太、有元典文、茂呂雄二著『パフォーマンス心理学入門—共生と発達のアート』pp.12-15、2019、新曜社
※3:「全体は部分の総和に勝る」アリストテレス The whole is greater than the sum of its parts.
※4:「教育において殻を破り自分を広げるべきは誰か?:いっしょに生きる技術としての発達の最近接領域(ダンスがひらく 学びの世界:殻を破る・自分を広げる)」『女子体育 59(6・7)』pp.12-15、2017、日本女子体育連盟
※5:「ともにかなでる図工室 第五回 大地はなぜ命を生み出すのだろう」
https://www.zukonomikata-nichibun.net/tomonikanaderu05/
※6:前掲註3