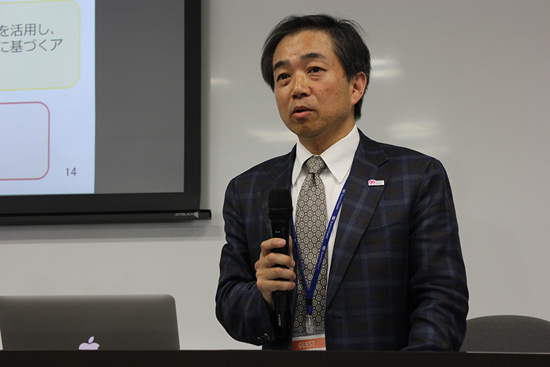読み物プラス
読み物プラス

~大学におけるアクティブ・ラーニングの実践~
【特集】ICT教育 NEXT 02

1.アクティブ・ラーニングで求められる倫理的、社会的能力の育成
2015年8月26日教育課程企画特別部会は論点整理を行い、次期改訂の視点として、「子供たちが『何を知っているか』だけではなく、『知っていることを使ってどのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか』ということであり、知識・技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力や人間性など情意・態度等に関わるものの全てを、いかに総合的に育んでいくかということである」として、新しい学習指導要領におけるアクティブ・ラーニングの重要性を改めて示した。
またアクティブ・ラーニング(課題の発見と解決に向けた主体的・協働的な学び)については、発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等が列記されており、実践者の自由なアイデアを求めている。アクティブ・ラーニングの指導方法を一定の型にはめることで、教育の質の改善のための取組が、狭い意味での授業の方法や技術の改善に終始するのではないかといった懸念からである。
ここで改めて文部科学省が示したアクティブ・ラーニングの定義について確認すると、「学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る」とある。案外見過ごしがちであるが、倫理的、社会的能力育成の視点が、アクティブ・ラーニングによって教育の質そのものを改善していこうとする趣旨からすると最も重要な観点ととらえたい。
2.ネオ・デジタルネイティブの特性を生かしたアクティブ・ラーニングの実践
そこで保育士、幼稚園、小学校教員をめざす学生を対象としたアクティブ・ラーニングの実践について報告する。アクティブ・ラーニングは、能動的な学びが基本であるため学生が取り組む意義を実感できる学習の状況の設定が何より重要である。さらに倫理的、社会的な能力に留意するとなると、学習者のよさを生かすことが基本となる。ネオ・デジタルネイティブ世代である大学生は、映像の目利きであり、iPad等のタブレット端末を使いこなしている。何より大学で幼児教育、教育におけるデジタルの可能性について最新の知識と技能を学んでいる。そこでその活動そのものを、教員研修の一環とするという発想で臨んだ。結果、子どもたち、先生方、学生のみんなが学び合える場となった。
授業名は、「マルチメディア教材論」で履修学生は3年生60名。幼児教育におけるデジタルの可能性を、iPadを活用する実演を通して提案する。それに対して各グループ(学生は1班3~4人)についた幼稚園の先生方から個別に指導を受けるという流れである。学生は、自作のプログラミンによるオープニング、iPad用デジタル導入教材、保育アプリの活用、活動の振り返りムービーの作成実演など30分間の実演を行った。その様子は同日のNHK首都圏ネットワークや各種メディアにも採りあげられ学生にも大きな自信となった。実演は、幼稚園の先生方にとっては教員研修の一環である。学生にとっては、自分たちも研修の講師であるというプライドが、倫理的な取り組み姿勢を促進した。「自分は高校の時強いクラブに所属していましたが、幼稚園での実演当日は準備して自信をもって試合に臨んだ時のような気持ちの高まりがありました」との学生の自己評価が印象的であった。目指す人物像、教師像の視点から発想し、それにふさわしい資質・能力を要求しても人材は育たない。自分たちでもそこそこできるんじゃないか、自分たちも新しい教育をつくれるかも、という手ごたえを実感できる場を提供したい。ネオ・デジタルネイティブとアクティブ・ラーニングの接点をひとつ発見した気持ちである。
地元の先生方との勉強会や幼稚園でのミニ実演で新しく作ったデジタル教材のクオリティを高めます。 |
|
 子どもたち、先生方、学生のみんなが学び合える場となったiPad実演(集合写真:越谷市私立大袋幼稚園) |
|
|
今田 晃一(いまだ こういち) |