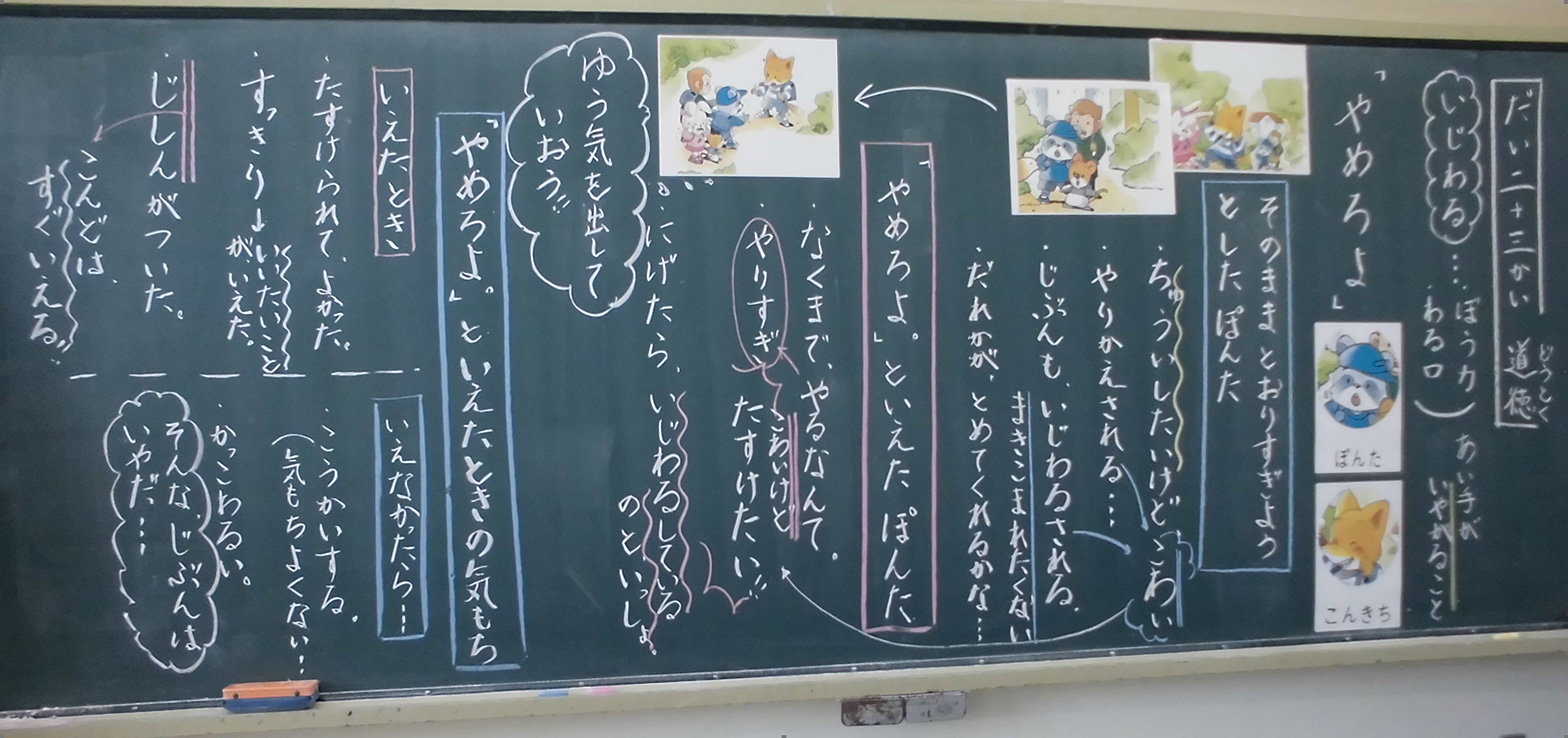小学校 道徳
小学校 道徳
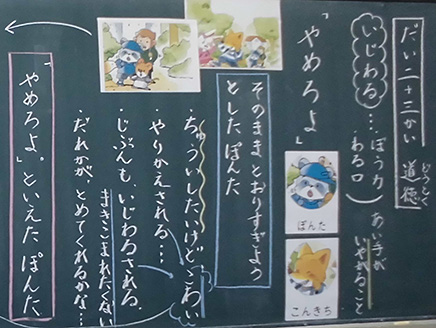
1.はじめに
道徳が特別の教科として出発して5年が経過した。教科化には、道徳授業の質的改善だけでなく、いじめなどの問題に対応できる児童の資質・能力を育むことも期待され、それをねらいとした教材も多く開発されてきている。道徳の授業では、このような教材を通して、人間の強さや弱さを見つめ、自分ごととして理解し、児童がよりよく生きるための力を養っていくことが求められている。
本教材も、いじめを題材にした教材である。「いじわるはよくないことです。」と児童に模範解答を求めるような授業にならないように、教材にしっかりと自我関与し、自分ごととして生活を振り返ることができるような発問を工夫することが大切である。また、友達の思いや考えに耳を傾けながら自分の考えをつなげ、さらに深めていくことを目指した授業を構想しなければならない。
2.教材について
ぽんたたちは学校の帰り道で、ぴょんこに意地悪をするこんきちと会う。注意をしようか悩みながらも、ぽんたたちは一度通り過ぎようとする。しかし、ぴょんこが泣き出しても意地悪を続けるこんきちに、ぽんたは勇気を出して「やめろよ。」と言うことができた。
正しいことをすることに悩むぽんたに自我関与しながら、人の心の弱さにも触れ、どんなときも正しいことを進んで行おうとする態度を養う。
3.実践報告
(1)主題名
正しいことを、ゆうきを出して A[善悪の判断、自律、自由と責任]
(2)教材名
「やめろよ」
(出典:日本文教出版 令和2年度版『しょうがくどうとく いきるちから1』)
(3)本時のねらい
ぽんたの行動や心情を通し、正しいと思うことができたときとできなかったときの気持ちを理解し、正しいと思うことをすすんで行おうとする態度を養う。
(4)展開例
学習活動 |
◇指導上の留意点 ☆評価 |
|
|---|---|---|
導 |
1 ねらいとする価値への導入を図る。 |
◇意地悪について考えることで、ねらいとする価値への導入を図る。 |
展 |
2 教材を読んで考え、話し合う。 |
◇場面絵を提示して、登場人物を確認できるようにする。 |
◎どんな考えから、ぽんたは「いじわるは、やめろよ。」と言えたのでしょう。 |
◇どんな考えから、「やめろよ。」と言えたのか、児童の意見をつなげたり、問い返したりして、多面的・多角的に考えを深められるよう工夫する。 |
|
○「やめろよ。」と言えたとき、ぽんたはどんな気持ちになったでしょう。 |
◇役割演技をしながら、「やめろよ。」と言えたときのぽんたの心情から、正しいことができたときの気持ちについて考える。また、言えたときだけでなく、言えなかったときの気持ちについても迫る。 |
|
展 |
3 自分を振り返る。 |
◇本時の学習を振り返り、道徳ノートに自分ごととして考えたことをまとめ、学びを確かなものにする。 |
終 |
4 教師の説話を聞く。 |
○正しいことを行うことのよさについて、説話をする。 |
4.授業記録
【導入】
T 意地悪って、どんなことですか。
C 暴力。
C 悪口。
C 相手が嫌がること。
T では、意地悪している人を見ると、どんな気持ちになりますか。
C いやな気持ち。
C やめさせる。
(考察)
いじめや意地悪は、当たり前のようにいけないことで、いやな気持ちになったり、止めようとしたりすることが一般的であることを確認する。
【展開前段】
T ぽんたがそのまま通り過ぎようとしたのは、どんな気持ちからでしょう。
C 注意したいけど、怖い。
C やり返されたら、どうしよう。
C 自分が意地悪されるようになるかもしれない。
C 巻き込まれたくない。
C 誰かが、止めてくれるかな。
(考察)
やめさせることが正しいことだと分かりながらも、できない人の心の弱さにしっかりと触れさせたい。すぐに言えなかったことについて、その理由について自我関与させながら考える。
T どんな考えから、ぽんたは「いじわるは、やめろよ。」と言えたのでしょう。(中心発問)
C 泣くまでやるなんて、ひどい。
C やりすぎ……。
C 怖いけど、助けたい。
C 怖いけど、やめさせなきゃ。
C 逃げるのは、意地悪しているのと一緒。
C そんな自分になりたくない。
C 勇気を出して、言おう。
(考察)
正しいことを行うことが、周りの人だけでなく、自分としてもどういう意味があるのか、多角的に捉えさせたい。また、通り過ぎようとしていたとき、どのように考えが変容したのか、児童の発言をつなげながら、深めさせる。
T 「やめろよ。」と言えたとき、ぽんたはどんな気持ちになったでしょう。
C 助けられてよかった。
C (できて、言えて)すっきりした。
C 言えなかったら、後悔する。
C (言えないと)格好悪い。
C 自信がついたから、今度はすぐ言える。
(考察)
「やめろよ。」と言えたときの心情に触れ、正しいことを進んで行えたときの気持ちを問い、正しいことができたときの喜びやよさを確認し、後段の自己への振り返りにつなげた。
【展開後段】
T 正しいと思うことができたとき、どんな気持ちになりますか。
C 気持ちがいい。
C すっきりする。
C できなかったら、ずっと気になる。
C できた方が、自分のためにもなる。
C 自信をもって行動できる。
(考察)
生活経験が少ない低学年において、後段の自己への振り返りは課題の一つである。一学期から意識をもって関連する場面を取り上げて考えることを通して、後段での発問に関する経験が思いつかない児童には、「あのときは、どうだったかな。」と、学級共有の経験について振り返ることができるよう声を掛ける。
【終末】
主題やねらいに沿った教師の説話
6.授業への工夫など
場面絵だけでなく、教材の人物の絵を掲示することで、話の内容を正しく理解できるようにした(教材への導入など)。また、児童の発言について、関連している意見をまとめたり、線でつないだりすることで、考えを深められるように板書した。
「いじわるは、やめろよ。」と言えたときの心情について、自我関与しながら考えられるように、役割演技を行った。言えたときだけでなく、通り過ぎようとしていた場面からぽんたの気持ちを考えさせ、それらを対比させることによって心情の変化を捉えやすくした。
7.考察
○ねらいを「正しいと思うことを進んで行おうとする態度を養う。」としたため、中心発問では心情ではなく、考えを問うことにした。そのうえで、正しいと思うことを行うことができたときの心情を重ねて確認することで、そのことのよさについて、さらに感じられるようにした。
○善悪の判断について、低学年の発達段階では他律的に捉える児童が多い。そのことから、発言を問い返したり、ときには揺さぶったりすることも必要となる。本授業においても、教材を通して、正しいとわかっていても迷う心の弱さについて十分に触れ、他者ではなく自分としてはどうなのかを考えられるようにした。
○自己の振り返りで、経験があまりなく悩んでいる児童も見られたが、学校生活を振り返り、同じような場面を想起できるよう声掛けを行った。