中学校 美術
中学校 美術
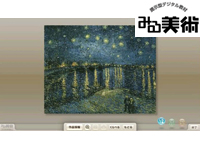
提示型デジタル教材『みる美術』を使って
※本実践は平成20年度版学習指導要領に基づく実践です。
1.基礎データ
|
題材・単元名 |
「絵画鑑賞へのいざないⅢ」~作者は何を感じたか~ |
|
|---|---|---|
|
時間数 |
3時間(3/3) |
|
|
題材・単元の |
クイズ形式を取り入れることにより,自然な流れで生徒に絵画作品を観察させ,グループ活動で様々な鑑賞の視点を学ばせながら,絵画鑑賞へ生徒をいざなう。 |
|
|
授業環境 |
活動環境 |
美術室 |
|
人数 |
教師1名 生徒数39名 |
|
|
教材や用具 |
教師:鑑賞用絵画(A4版に印刷),鑑賞用絵画(一部分拡大したもの),ワークシート |
|
|
コンピュータ |
使用デジタル教材 |
提示型デジタル教材『みる美術』 |
|
OSバージョン |
Windows Vista |
|
|
使用周辺機器 |
プロジェクター,パソコン(パワーポイント) |
|
2.活用事例および展開
①ねらい
絵画作品をクイズ形式で鑑賞したり,描いてあるものを分析的に観察しながら,生徒の興味関心を絵画作品の鑑賞へと導く。作品が描かれた時代背景や表現方法の変化などにも着目し,基本的な知識を身につけたうえで,自ら進んで鑑賞し,その表現の工夫や特徴をとらえ,作者の心情や表現意図について考えようとする態度を養う。
②提示型デジタル教材『みる美術』利用の意図
この授業では印象派における風景画を鑑賞させることを考えた。風景画作品は描かれているものが明確である場合が多く,作品を分析的に見せるための視点の設定が容易である。また,印象派の絵画は歴史上のそれまでの絵画と比較すると劇的に色使いや描かれ方が変わっていく時代の絵画でもある。様々な色使いや筆のタッチなどに着目することにより,作者の気持ちを考える,または想像する,表現意図を考えるというねらいに近づくために使用しやすい題材であると考えた。提示型デジタル教材『みる美術』は「印象派の風景画」などのように検索したいジャンルを指定することですぐに作品を探し出すことができる。また作品の部分拡大を容易にすることができ,非常に詳細に作品を観察することができる。そのため,授業で使用する絵画作品を選び出すことや部分拡大を見せて描かれたものを想像させるという展開を比較的容易にすることができた。
③評価について
◆美術への関心・意欲・態度
絵画作品に関心を持ち,自他の視点をもとに,積極的に作品を鑑賞し,作品に対する見方を広めようとする。
◆発想や構想の能力
画面構成や色彩の効果など,作者の意図について想像し,考えをまとめる。
◆鑑賞の能力
鑑賞を通して表現の工夫や制作意図を感じ取る。
④指導計画
|
学習活動の流れ |
指導上の留意点,評価方法 |
|
|---|---|---|
|
「絵画鑑賞へのいざない」 |
<留意点> |
|
|
「絵画鑑賞へのいざないⅡ」 |
<留意点> |
|
|
「絵画鑑賞へのいざないⅢ」 |
<留意点> |
|
3.本時の展開
①目標
・風景画の作品を様々な視点で分析的に観察し,作品から感じ取られることを言葉で表現する。
・作品の部分拡大を鑑賞することにより,その表現の工夫や特徴をとらえ,作者の心情や表現意図について考える。
・作品から感じたことに自分なりの理由付けをしながら感想をまとめる。
②提示型デジタル教材『みる美術』を利用した授業の展開
|
|
時 |
学習活動 |
◎主な支援 ●評価〈手だて〉 |
|---|---|---|---|
|
導 |
5 |
1 本時の課題を把握する。 |
◎制作者が作品を作り出すときの気持ちに着目するよう伝える。 |
|
様々な視点から,絵画作品を鑑賞し,感じたことをまとめよう。 |
|||
|
展 |
5 |
2 作品を鑑賞する。 |
◎作品の一部分を拡大して見せることで,筆のタッチや色使いに着目させる。 |
| 15 |
○「暗い青が塗られているので夜空のようです。」 |
◎絵の具の塗り方,筆が動いた方向,絵の具の厚さなどにも着目させる。 |
|
|
○「様々な色は縦横に荒っぽく塗られています。何が描いてあるかは全然分かりません。」 |
◎縦横に塗られている絵の具,筆の動き,どんな色が塗られているかなどに着目させる。様々に考えさせた上で「わからない」ということも一つの答えとして認める。 |
||
|
○「細かいたくさんの点で描かれています。遠くに見える水平線のようです。 |
◎点描で描かれていることに着目させる。細かい点の集まりがどんな風景になるのかを考えさせる。 |
||
|
○「淡い色が重なって塗られています。青い色が薄く見えるので空の雲を描いたものだと思います。 |
◎淡い色の重なり方に着目させる。 |
||
|
(2)鑑賞の視点をもとに作品全体を鑑賞し,感じたことをまとめる。 〈鑑賞の主な視点〉 |
◎作品をより分析的にまた,自然に鑑賞ができるよう鑑賞の視点を与える。 ●「ゴッホの絵の季節はいつ頃でしょう。」 ●「スーラの絵の季節はいつ頃でしょう。」 ◎一部分を見て感じたことと作品全体を見たときの感じ方の違いにも着目させ,感じたことをまとめさせる。 ◎表現から作者の気持ちや考えを想像させる。 ●作者の心情や制作意図などを自分なりに考えることができたか。 <生徒の作文(鑑賞文)> |
||
|
展 |
10 |
3 鑑賞したことを発表する。 |
◎自他の感じ方,考え方の違いを捉えさせる。 |
|
10 |
(2)各班の発表を聞く。 |
◎学級内での発表を通し,より多くの考え方に触れさせる。 |
|
|
ま |
5 |
4 グループでの話し合いや学級での発表をもとに授業の感想をまとめる。 |
●自他の感想をもとに作品鑑賞の様々な視点を知り,自分なりの感想を持つことができたか。 <授業後の生徒の感想> |
③指導のポイント
・クイズ形式など遊び感覚を取り入れ,自然に作品を鑑賞させる。作品や作者に関する知識はできるだけ与えず,感じたことを自由に話せる雰囲気を大切にする。
・作品の一部分が拡大されることで見えてくるもの(筆のタッチ,色使いなど)は生徒にとっても新しい発見である。必要に応じて生徒が詳しく観察したいと思う場面を取り上げ,プロジェクターなどを使用し生徒全体に見せ,様々な意見を生徒から集める。
・多くの生徒に自分が感じたこと,考えたことを発表させることで価値観の交流を図り,作品を見る視点を自然に身につけさせる。作者の気持ちや表現意図を意識させることで作品の奥深さを感じさせる。
4.感想等
今回の授業では提示型デジタル教材『みる美術』の部分拡大の機能を利用したが,生徒の興味,関心を高める導入,展開をすることができた。拡大することで絵の具の塗られ方,絵の具の盛り上がりや塗り重ね,筆のタッチなどが確認でき,生徒は「何が描いてあるか分からない」ということを言いながらもグループ活動ではそれぞれの考えを出し合いながら何が描かれたものかを探る様子が見られた。また,部分拡大を見せた後に作品全体を見せたことにより,拡大部分は全体の中のどの部分だったのか,他の部分にはどのように何が描かれているのかということを興味深く観察する様子が見られた。今後は作品を分類したり,比較したり,作品の情報を見たりするなど,他の機能も利用していきたい。生徒が自ら興味を持った作品を検索し,鑑賞できる授業展開を考えていきたい。







