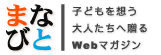大濱先生の読み解く歴史の世界-学び!と歴史
尼将軍 政子
一夫一婦の感覚をもった中世の強き女性女としての器量
政子は、北条時政の娘、平治の乱に敗れ伊豆に流されていた源頼朝の妻となり、頼朝亡き後の鎌倉幕府を支え、北条執権政治への道をきり拓いた女性です。政子の生涯は、保元2(1157)年から嘉禄元(1225)年、慈円が『愚管抄』で「武者の世」になったといった時代を馳せぬけた生涯といえます。
政子は、父時政が京都大番役の留守中に頼朝との関係ができたため、父の怒りを買い、平氏の代官である伊豆目代の山本兼隆に嫁がせようとされましたが、頼朝のもとにはしります。政子と頼朝は「暗夜をさ迷い、雨をしのいで」逃げ込んだ伊豆山権現(伊豆山神社)に匿われ、やがて時政に結婚を認めてもらいます。ここに頼朝は、時政の庇護を受け、平氏を討つべく挙兵、関東を制圧、鎌倉に幕府を開き、「鎌倉殿」となり、政子は「御台所」と呼ばれることになります。
頼朝は、政子が後の二代将軍頼家を妊娠中、亀の前を寵愛して通います。政子は、この頼朝の行為に激怒し、時政の後妻牧の方の父牧宗親に亀の前が住む伏見広綱邸を襲撃させ、伏見広綱を遠江に流罪させます。この事件は、政子の嫉妬深さ、気性の激しい「悪妻」の証として世に語られてきました。政子の激怒は謂われなきことなのでしょうか。
政子は、文治2(1186)年に鎌倉に送られてきた義経の愛人静御前が、頼朝の求めに応じ鶴岡八幡宮で白拍子を舞い、「吉野山峯の白雪ふみ分けて 入りにし人の跡ぞ恋しき」「しづやしづしずのをたまきをくり返し 昔を今になすよしもがな」、と義経恋しと歌ったのを頼朝が激怒した時、頼朝に流人時代の二人の仲を思い起こさせ、挙兵の日の不安を語りかけ、義経を今も慕う静の心に思いを馳せさせたのです。ここに頼朝は、その怒りを鎮め、静に褒美を与えます。ここには、一人の女として、政子の器量の大きさがうかがえます。
一夫一婦の感覚
こうした政子の言動は、土地に命をかけた武士の原点、当時の村の営み、村の文化を体現したものに他なりません。農業を営む村では、男も女も共に働き、ある対等な関係をもつことができました。政子は、まさに武家の女である前に、大地を生きた子であったといえましょう。頼朝は、政子と対極にいる人間、都の公家の気風を一身に受けて育った人物です。それだけに妻問いの感覚はきわめて自然といえましょう。政子には、こうした頼朝の姿が許せない、一夫一婦の感覚、村の女の意地があったのではないでしょうか。
一夫一婦のモラルは、キリスト教世界がもたらしたと説かれていますが、鎌倉時代にすでに見ることが出来ます。『北条重時家訓』には次のような一項があります。
人の妻をば心をよくよく見て、一人をさだむべし。かりそめにも其外に妻にさだめて、かたらふ事なかれ。ねたましき思ひ積もりて、あさましくあるべし。されば其罪にひかれて、必地獄にもおちぬべき也
重時(1198-1261)は、二代執権義時の三男、三代執権泰時の弟で、六波羅探題、連署として幕政を支えた一人。その家訓は「六波羅殿御家訓」と「極楽寺殿御消息」の二種があり、ここに引用したのは重時出家後の「極楽寺殿御消息」にあるものです。「御消息」は、日常道徳を仏教と結びつけ説き、神仏の照覧をうけるためにも人間として正直でありたいとの思いを述べています。ここには「一夫一婦」の道が説かれております。
こうした感覚は、村の営みを支えたもので、武士のなかで広く共有しうるものでした。しかし、時代とともに武士が治者として村住の感覚を失い、家の継承が第一義となるなかで、やがて妾の存在が広くみられるようになり、「一夫一婦」ともいうべき男女の関係に亀裂が生じたといえましょう。
時代を体現して
政子はこうした「御消息」が説く世界を一身に体現して生きた女性にほかなりません。当時の女性をめぐる状況は、幕府法である「御成敗式目」のなかに、女子に譲与したものを悔い還せない(所有権の移転が行われた後に、本主が権利の移転を否定して自己に取り戻す行為を許さない)という原則をめぐり、女子をめぐる規定が「夫の罪過によつて、妻女の所領没収せらるるや否やの事」「夫の所領を譲り得たる後家、改嫁せしむる事」等々おおく見られます。ここには時代をたくましく生きる女の姿が読みとれます。まさに政子は男とともに武士の世を馳せぬけた女でありました。「悪女」なる呼称は江戸時代の儒者の言です。
慈円は『愚管抄』で政子の権勢を「女人入眼の日本国」と評し、『承久記』が「深い悲しみを持つ者」と描いております。まさに鎌倉幕府草創期を生きた政子は、北畠親房が『神皇正統記』に位置づけたように、「後室の尼公」政子の計らいをふまえた執権泰時によって天下が治まったのです。尼将軍政子は、村の慣習を己の道となし、女として男に対峙し、男の野望を全身で包み込んで生き抜くことで時代をきり拓いたといえましょう。