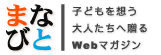大濱先生の読み解く歴史の世界-学び!と歴史
天皇という存在をどのように問いかけますか
結婚50年・在位20年という秋
2009年という年は、天皇が1989年1月7日第125代天皇として即位してより20年、1959年4月10日に民間出身の正田美智子が皇太子妃となってより50年、天皇、皇后両陛下が金婚式を迎えられた年になります。そのため即位20年、御成婚50年の奉祝行事が多様に企画されているようです。
天皇は、50年の歩みを、4月9日の記者会見で「310万人の命が失われた先の戦争から日本国憲法のもと自由と平和を大切にする国として立ち上がり」、産業の発展による国民生活の向上を想起し、公害問題や沖縄復帰に想いを致し、「私どもはこのように変化してきた日本の姿と共に過ごしてきました」、と問い語られました。
ここには、日本国憲法に規定された「国民の象徴」たり得る君主たろうとして歩んできた天皇の率直な気持ちが吐露されています。
 皇后は、民間から皇室に入った日々の苦悶をふまえ、「伝統と共に生きるということ」の意味を問い質し、「伝統があるために国や社会や家がどれだけ力強く豊かになれているかということに気付かされる」一方で、「型のみで残った伝統が社会の進展を阻んだり、伝統という名の下で古い慣習が人々を苦しめていることもあり、この言葉が安易に使われることは好ましく思いません」と述べています。
皇后は、民間から皇室に入った日々の苦悶をふまえ、「伝統と共に生きるということ」の意味を問い質し、「伝統があるために国や社会や家がどれだけ力強く豊かになれているかということに気付かされる」一方で、「型のみで残った伝統が社会の進展を阻んだり、伝統という名の下で古い慣習が人々を苦しめていることもあり、この言葉が安易に使われることは好ましく思いません」と述べています。
美智子妃を迎える皇室には、良子(ながこ)皇后(香淳皇后)をはじめ秩父・高松両宮妃、秩父宮妃実母松平信子らが民間妃に反発していました。その一端は、婚約直前の1958年10月11日に「東宮様の御縁談について平民からとは怪しからんといふやうなことで皇后さまが勢津君様(秩父宮妃勢津子)と喜久君様(高松宮妃喜久子)を招んでお訴えになつた由」と、入江相政侍従長が日記に記しております。旧皇族梨本宮守正王妃伊都子は、「朝から御婚約発表で埋めつくし、憤慨したり、なさけなく思ったり、色々。日本ももうだめだと考えた」と、婚約発表の記事に反応しています。
美智子妃は、こうした気分に彩られていた世界に入ったわけで、いわゆる「ミッチーいじめ」の集中砲火にさらされ、見る影もないほどに心身を害されました。「伝統」という言葉が「安易に使われることは好ましく思いません」と断言した中には、美智子皇后にとり、天皇とともに新しい皇室像を生み育ててきたとの想いがこめられています。
時代を体現した天皇像
天皇は、「日本の姿と共に過ごしてきました」と己を位置づけることで、昭和天皇に距離を置き、己の君主像を語ろうとしています。
思うに明治天皇は、「大日本帝国」として欧米列強に互しうる新しい国家の造形を一身に体現する「大帝」たろうとし、大元帥陛下として明治の栄光を担いました。この軍事指導者としての天皇像は軍国日本の姿にほかなりません。
しかし大正天皇は、明治天皇とことなり、漢詩の造詣が深い文人肌の君主として軍事よりも精神文化や芸術を守り、皇太子裕仁、後の昭和天皇をヨーロッパに外遊させます。
昭和天皇は、ヨーロッパで見聞した戦争の惨状をふまえ、立憲君主たる場をいかに具体化するかに苦闘されます。昭和天皇は、立憲君主として己を律しようとしながらも、時代の奔流にのみこまれ、軍事指導者たる大元帥陛下にして現人神としてふるまいます。この存在は、戦後に「五箇条の誓文」をよりどころに「民主主義」の先導者と己を位置づけ、日本国憲法による立憲君主たろうと努めました。
 現天皇は、父昭和天皇の姿を見つめ、立憲君主のありかたを美智子皇后とともに模索しております。この想いは、結婚した1959年という年が4月10日の結婚式と「世紀のパレード」の5日後、15日から日米安全保障条約を阻止する第一次統一行動の幕が開き、まさに60年安保闘争という熱い政治の季節が天皇の新婚生活と重なっていたことに無縁ではありません。このことは、天皇皇后にとり、日本の国のかたちを読み解くうえで、大きな意味をもったのではないでしょうか。
現天皇は、父昭和天皇の姿を見つめ、立憲君主のありかたを美智子皇后とともに模索しております。この想いは、結婚した1959年という年が4月10日の結婚式と「世紀のパレード」の5日後、15日から日米安全保障条約を阻止する第一次統一行動の幕が開き、まさに60年安保闘争という熱い政治の季節が天皇の新婚生活と重なっていたことに無縁ではありません。このことは、天皇皇后にとり、日本の国のかたちを読み解くうえで、大きな意味をもったのではないでしょうか。
こうした時代の嵐こそは、沖縄やサイパン行脚にみられる様に戦争の惨禍を凝視し問い質すなかに天皇たる己の場を築き、日本国憲法が理念とする平和への思いを心に刻み、己の規範となし、皇后と共に歩ましめた原点なのです。
この思いは、沖縄県慰霊の日(6月23日―日本軍の第32軍司令官牛島満中将・同参謀長勇中将が糸満の摩文仁で自決し組織的戦闘が終わった日)、広島(8月6日)・長崎(8月9日)に原爆が投下された日と8月15日の「終戦」の日の四つを祈りの日となし、如何なる時と場にあっても祈りを捧げられてきた姿に表れています。「天皇制」といわれる日本における君主制のあり方は、このような時代の課題と君主たる天皇と皇室がどのように向き合い、己の場を問い質してきたかを時代に位置づけることではじめて読み解けるのではないでしょうか。
歴史への眼
日本の歴史における天皇の存在は、「天皇制」という概念で照射して解釈すればこと足りるのではなく、時代の相貌をふまえて天皇という磁場を読み解かねばなりません。この作業は、日本人が天皇との距離関係で己の存在を計り、己の場を位置づける心理にとらわれていることを自覚的に問い質すことから始まります。この営みでは、天皇という外的権威に自己を託して生きるのではなく、己の中にどのような内的権威を構築しうるかということが常に問われるでしょう。そこでは、「万世一系」の皇統に己の優越感を抱くか「血塗られた天皇制」と「呪詛」して語るしかない「天皇制」の歴史ではなく、等身大の天皇を時代に位置づけ、天皇に託してでしか己の存在を問い語れない日本国民の姿を、どれだけ描いていけるかが課題となります。
日本の歴史を生きざるを得ない民が、どれほどに天皇という存在に囚われてでしか己の存在を問い語れないかに想い致し、その深淵に潜む時代の闇を抉摘する営みこそが歴史学に新地平をもたらすのではないでしょうか。
この問いを解くためにも日露戦争後の日本を鋭く告発した河上肇の「日本独特の国家主義」(明治44年)を読んでみませんか。