学び!と美術
学び!と美術

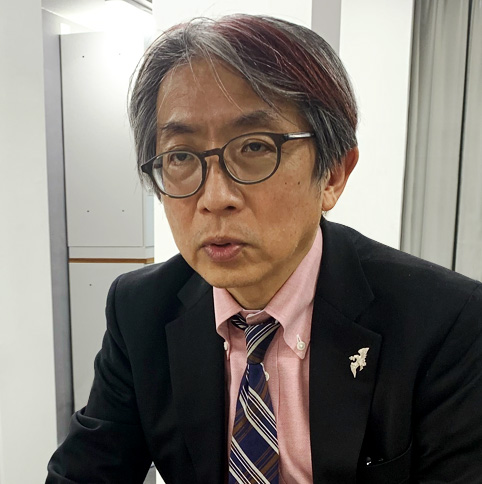 株式会社MAGUS 代表取締役
株式会社MAGUS 代表取締役
上坂真人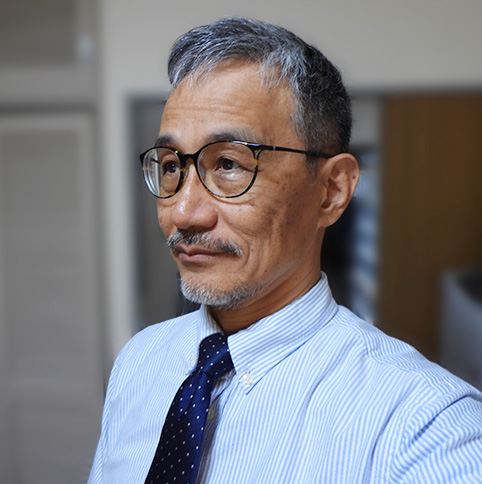 筆者
筆者
2015年のことです。ある人が突然「美術鑑賞の話が聞きたい」と大学に訪ねてきました。広告制作や写真素材を提供する企業アマナの上坂さんです。語り合ううちに美術の現状や問題意識など、すっかり意気投合しました。ビジネスと美術について語るには最もふさわしい方だと思いますので、今回ご登場いただき、上坂さんの話を通して2010年以降のビジネスと美術鑑賞の関係について見ていきましょう。
アートをもっと「動き」に
その活動の中で、日本精神科看護協会の末安民生会長が「アートには効用がある」と話していて、じゃあ「アートが心を静める効果を数値化し、医薬品企業を巻き込んでセミナーをやったら面白い」と思いついたのですが、その時、奥村さんの本が目に飛び込んできました。
でも、奥村さんの話は「アートが心を静める」というよりも、むしろ「脳を活性化させる話」でした。期待とは正反対だったのです(笑)。でも、面白かったので今もお付き合いを続けさせていただいているというわけです。
アートのある生活
 ©Shinichi Ichikawa
©Shinichi Ichikawa
『フェスやフェア』では、世界8カ国から作家が参加する『浅間国際フォトフェスティバル』を行いました。長野県の東、浅間山麓の御代田町に、旧メルシャン美術館跡地がありますが、PR活動なし、ほぼ一か月半で2万人来場しました。視察に来た企業はANA、資生堂、電通、博報堂、ヤフー、ソニー、パナソニック、野村不動産、三菱地所、三井住友銀行、三菱商事、第一生命保険など70社ほどです。企業側にも、スポーツや音楽のようにアートを企業戦略として「活用する」風潮が見えてきたのかなと思います。
アートフェスやイベントを行う自治体は多くありますけど、そのほとんどは人口減少に歯止めがかかってません。ただ北海道の東川町だけは例外で、「東川町国際写真フェスティバル」「全国高等学校写真選手権大会」「高校生国際交流写真フェスティバル」というイベントをきっかけに1994年に6973人だった人口は2018年には8216人まで増加しています。もちろん、アートだけが原因ではないのですが、自治体にちゃんと貢献しているかとか、アートの自己満足で終わってはいけないとかは大切な視点だと思います。
アートとビジネスの新しい動き
2019年度から文化経済戦略に基づいた「文化経済戦略推進事業」というのも行われているんですが(※2)、そこでは「アーティストと企業の共創事業」「アーティストによる企業向けワークショップ」「アーティストと企業・起業家のネットワーク」「文化芸術への投資の測定・評価」「アーティストとの交流が企業にもたらす好影響」「文化を源泉としたビジネス課題解決」「民間企業の美術品コレクションの形成と活用」などが提案されています。一昔前を考えれば、アートのとらえ方はずいぶん変わったと思います。
美術教育だけを見ていると、このような動きは中々見えません。でも教育はあくまで社会の一部ですから、できるだけ物事を広く見ていく必要があると思います。私にとって上坂さんは教育以外の視野を獲得する大事な出会いでした。
ただ、2018年あたりからは、はっきりと流れが変わり始めました。私たちのところに、商業施設がから「アートのコーナーを作りたい」という話が次々と来るようになりました。彼らも、もうグルメやファッションでは差がつかないことに気付いたのでしょう。
でも、「アートだったら、なんでもいいので」みたいな感じもあって、まだまだ抽象的な依頼です。アートを日常にするシナリオに欠けるというか、消費者構造を変革する前提に欠けています。「アートは社会問題の表出物」であり、「アーティストと語ることを通して生まれるものがある」という観点もないですし、自国のアーティストを育てようとする意識もありません。
海外では金融機関が膨大な調査を発表していて、アートが産業化する基礎ができています。富裕層はほぼ全員がアートコレクターなんですが、そこにアプローチする意識も明確です。アートの専門教育では、アートに関わるディベート、マーケット調査、契約実務、プレゼンまで行っています。そのあたりも世界とのギャップでしょうね。
企業がアートを支えるのは、確かな企業戦略が必要で、一般的な消費者だけでなく、富裕層も含めてビジネス的意義と社会的意義をしっかり見つめていかないといけないと思います。
※1:学び!と美術<Vol.75>「写真は地域社会を変える?」
https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/art/art075/
※2:文化経済戦略推進事業
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/bunka_keizai/92916901.html