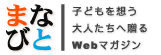大濱先生の読み解く歴史の世界-学び!と歴史
8月15日に想う
戦争の時代を問うのに求められること
戦死やあわれ
昭和天皇は1945(昭和20)年8月15日正午ポツダム宣言を受託し戦争を終局させるという「終戦」詔書を放送(玉音放送)、ここに長い戦争の時代は終わり、日本政府は9月2日に米艦ミズーリ号上にて降伏文書に調印しました。その後日本は、世界各地で起こっている内乱・戦争を「遠い戦争」とみなし、現在までの60余年「平和」を享受してきました。この「平和」は戦争で生命を奪われた死者によって築かれたものです。しかしその死はどれだけ直視されてきたでしょうか。戦死とは何なのでしょうか。現在問わるべきは、戦死者を国家の栄誉で位置づけることではなく、戦争の死と向き合い、あるべき明日をひとり一人が想い描くことではないでしょうか。そのためには、死者によせる母や妻の声に耳傾け、その眼差しから戦争の時代を問い質さねばなりません。戦死とはどんな死か竹内浩三の『骨のうたう』から読み解いてください。竹内は、伊勢松阪の出身、日本大学専門部映画科在学中に中部第38部隊へ入隊、ヒィリピンにて戦死、23歳でした。
戦死やあわれ 兵隊の死ぬるや あわれ 遠い他国で ひょんと死ぬるや
だまって だれもいないところで ひょんと死ぬるや
ふるさとの風や こいびとの眼や ひょんと消ゆるや
国のため 大君のため 死んでしまうや その心や
白い箱にて 故国をながめる 音もなく なんにもなく
帰っては きましたけれど 故国の人のよそよそしさや
自分の事務や女のみだしなみが大切で 骨は骨 骨を愛する人もなし
骨は骨として 勲章をもらい 高く崇められ ほまれは高し
なれど 骨はききたかった 絶大な愛情のひびきをききたかった
がらがらどんどんと事務と常識が流れ 故国は発展にいそがしかった
女は 化粧にいそがしかった
ああ 戦死やあわれ 兵隊の死ぬるや あわれ こらえきれないさびしさや
国のため 大君のため 死んでしまうや その心や
生まれた時がら、オレの子どもでながったのス
戦死は、「国のため 大君のため 死んでえしまう」「遠い他国で ひょんと死ぬ」ことで、故国の母、妻、恋人などに深い喪失感をもたらします。遺された者は、この死を確かな歴史的事実として受け止めたとき、そこで時間が止まり、死者と一体となって生きることで己が生命を全うします。高橋セキ、岩手県和賀郡の農婦は、1944年11月にニューギニアで戦死した一人息子の千三の「霊(ホドゲ)に手ッコ合わせることだげァ生甲斐(イギゲエ)なのス」と語る母でした。千三が1942年に召集された時、村長に次のように言ったとのことです。
これまで、千三をオレの子どもだ、オレの子どもだ、と思っていたが、間違いだったス。兵隊にやりたくねえど思っても、天皇陛下の命令だればしかだねエス。生まれた時がら、オレの子どもでながったのス
千三と駅頭で別れたセキは、「ハラワタしぼられるようで、骨だがどこだが、ギクッ、ギクッとなるもんだけなッス」と、その時の悲痛な気持ちを語っています。息子の遺骨が来たとき、「本当にムスコだべが?そうだんべが…と思って、その骨コナメでみだス」「千三の味も匂いもしねえ」かったそうです。「牛(ベゴ)や犬の死んだようにしたくねえと思って」、少しづつためていたお金で「人通りの多い道ばたに」墓をたてます。
その道を通った人たち墓石みで、戦死したムスコの千三を思い出してける(くれる)ベエ。お念仏もとなえでくれる人もあるべし、知らねえ人でも、戦死者の墓だと思えば、戦争を思い出すべなス。お念仏をとなえでくれる人もあるがも知れねえと思ってなス。そうすれば供養になるし、千三のためや自分(ワレ)のためになるばかりでなぐ、お念仏の願力で念仏となえだ人たちも、すくわれるから、世の中の人のためにもなると思うのス。
この母の想いには、「戦争の苦しみに、二度と誰にもあわせたくねエなス」と語るように、戦争を忘却することで世を謳歌する時代が来ることを見ぬき、人間が人間として生きて在るとは何かが説かれています。
死者によせる想い
日本の母は、お国のために子を育て、天皇に捧げねばなりませんでした。第5期国定教科書『初等科国語』六(昭和18年)所収の「姿なき入場」はこうした日本の母像を謳いあげています。ビルマ(現ミャンマー)ラングーン上空で戦死した子に語りかける母の想いが読み取れます。
いとし子よ、ラングーンは落ちたり。いざ、汝も勇ましく入場せよ、姿なく、声なき汝なれども。(略)
いとし子よ、汝、ますらをなれば、大君の御楯と起ちて、たくましく、ををしく生きぬ。
いざ、今日よりは母のふところに帰りて、安らかに眠れ、幼かりし時 わが乳房にすがりて、すやすやと眠りしごとく。
この母と子の物語は、天皇の国に生きる母が負わねばならない定めを説いたもので、日本の国民精神を規定したものです。それだけに遺された者は、死者への想いを、河原の石ころに、墓石に問い語ることで生きて在る己の場を確かめ、亡き子や夫、愛しき者と共に生きることで世間の風浪に耐えていきます。その想いは、京都駅頭に「髪と爪のこして征途にのぼる日」で時間が止まり、残された日々を生きねばならない心を歌った近藤菊枝の「帰り来ぬ夫に捧げて」にも読みとれます。
十八年還らぬ人を待ちわびつつ身だしなみして老いづくわれか
帰り来て必ず召しませ君が足袋ほほにあてて祈るみ冬に入る日
帰りなば召しませと夏ころも風とほしつつここらはもとな
神のごとき夫に仕へし十八年かみしめかみしめ生きてしゆかむ
戦争の時代を問うには、死者の想いに我が思念を重ね、遺された者の慟哭を読み解くことが求められます。ここに描き出された世界こそは、戦争の時代が遠い過去ではなく、現在も息づき、国家の在り方を問い質す場を提示しています。この場から歴史の闇を解き明かしたいものです。