学び!と美術
学び!と美術

 早稲田大学 教授 大泉義一 先生
早稲田大学 教授 大泉義一 先生 東京都目黒区立五本木小学校
東京都目黒区立五本木小学校
主任教諭 鈴木陽子 先生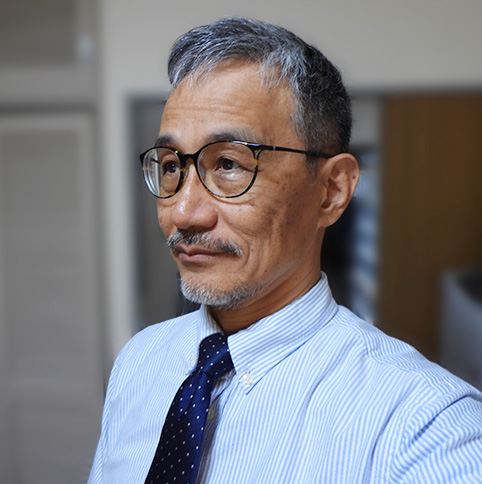 筆者
筆者
描き方、技法、技術など技能に関する内容はけっこう誤解されがちで、中には創造性の敵のように語る人もいます。でも、子どもにとっては、技能は喜びだったり、発想のもとになったりしています。今回は、そんなお話です。
技術と技能は分けて考える
そこで、「技術を学んでるけど、学んでいるのはそれじゃないな」と思いました。例えば、喜びとか意欲とか?すると、学校にいる子どもたちは毎時間、毎日、何か新しいことを学んでるわけですよね。「うれしいだろうなあ」と思って、じゃあ「技能」って何だろうなと、それで、鈴木先生と大泉先生に教えてもらおうとなった次第です。
でも実際は区別していない人が多いんじゃないですか?「この技法を教えたら、子どもの発想を制限してしまうんじゃないか」とか「この描き方を教えたら、○○式のように同じ絵が並んでしまうんじゃないか」とか。私もよく質問されて、答えに困ることが多いです。また、「絵の描き方を教えてほしかった」みたいな発言に代表される「何か技法を教えたら、身につく」という単純な「因果」として「技能」をとらえている人も多いと思います。
技能は子どもが生み出す
例えば、先週、2年生の「ローラー・あーと」という授業をしました(※1)。絵の具とローラーを使っていろいろ試しながら、そこで生まれてくる形や色などから思いついて絵に表すものです。まず、導入では、絵の具の色が重なって新しい色が生まれることや、ローラーで予想外の形が生まれてくることなどを、教師が簡単にやってみせます。絵の具の性質とかローラーの使い方とかは大泉先生の言う「テクニック」でしょう。でも、そこから発揮されるのは子どもの「技能」ですよね。
Kさんは、横長の画面下から上へと繰り返し色を重ねていました。いろいろな色味を塗っては、その上に白を重ね、また色を重ねては白を重ねていくのです。でも、コロコロと転がす感じではありません。両手でしっかりとローラーの柄を握って、腰をかがめながら、ぐっと力を込めてゆっくり下から上へローラーを押し上げていくのです。ローラーがぶれないようにゆっくりと慎重に動かしているんですね。
そして、時々、絵の具缶に入っている筆で画面にすっと線や点を置きながら、また両手でローラーで色を押していきます。ずっと立ったまま(!)で2時間つくり続けていて、まるでKさんの身体とローラーが一体になっているようでした。
Kさんに尋ねてみると、「力を入れてローラーで絵の具をぬると、段ボールのもようが出てくる。それが面白くてこうしてローラーを使った」と言っています。確かに、Kさんが力をこめた画面は、へこんでいました。
基底材として、片面に白い紙が貼ってあるW板段ボールを用いたのですが、堅牢なのに、程よく紙に絵の具がのっていくし、水分も適度に吸収してくれるので、子どもが色を重ねると段ボールが応えてくるような感じが持てるのだろうと思います。
私は、画用紙、ローラー、絵の具などの中で、この活動を繰り返すKさんの姿こそ「技能」を発揮している姿だと思います。同時に、技能を生み出していること自体がKさんにとって「つくりだす喜び」でもあると思います。
でも、それは結果論でしかなくって、実際は鈴木先生が紹介してくれたように、材料や用具などと呼応しながら「技能」を生み出す過程そのものに「つくりだす喜び」があるんだと思います。そこには、一人だけでなく、子どもたちの共同性も働いているし、先生がテクニックを教えることも含まれているので、みんなで「つくりだす喜び」をつくりだし、感じ合っている縁起があるのだろうと思います。
例えば、初めての個人用水彩絵の具を使う題材があります。2年生の一番最後から「絵の具となかよし」という活動です(※2)。 絵に表すというより、色や水を混ぜて自分の色をつくり、思いのままにぬったりかいたりすることを楽しむものです。
 Uさんの作品:無題(画用紙 15×21cm) Uさんは写真のような作品をつくっていました。そこにIさんがやってきて、Uさんがつくっている色を見て「きれい!どうやってつくったの」と聞きます。すると周りの友だちも集まってきます。まず、ここでUさんの技能は多くの友達から認められていますよね。
Uさんの作品:無題(画用紙 15×21cm) Uさんは写真のような作品をつくっていました。そこにIさんがやってきて、Uさんがつくっている色を見て「きれい!どうやってつくったの」と聞きます。すると周りの友だちも集まってきます。まず、ここでUさんの技能は多くの友達から認められていますよね。
そして、Iさんは、Uさんのつくりかたをもとに色をつくり始めるのですが、なかなか同じ色にはなりません。そこでIさんは自分のパレットを持ってUさんのところに行くのです。
すると、Uさんは、「えーっ!Iさんのこの色すごくきれいだ」と言います。それがうれしくなったのか、Iさんは色味を変えながら色をつくることにますます夢中になりました。つまり、Iさんの「技能」はUさんから認められたことによって、さらに進化するわけです。
その頃、Uさんの隣にいたKさんは、筆洗用の水入れの中をずっとのぞき込んでいます。「なんだろう?これ、きれいだなあ」と言っています。それに気づいたUさんは、「どうやったの!」と尋ねますが、Kさんは「わからない」と答えました。
そこで、Uさんは自分の筆洗用の水入れに色を落としたり、混ぜたりしてます。しばらくすると、「わかった!!暗い色水をつくって、白をつけた筆を、こう、ゆらゆら動かすとできるんだ。オーロラだ!」と声をあげ、その興奮は教室中に広がりました。
このように、子どもたちが、もの、ひと、ことに働きかけ、働きかけられながらつくっていることを見失ってはならないと思います。そこで「技能」も生まれているのです。
「技能」には、教師の「観」が大事
まあ、結局、幼児の粘土遊びを理解するためには、私たちが粘土遊びをするしかないですけどね。一方で、授業研究会を見ていると、授業の「指導技術」は協議しているんだけど、教師の見方とか、考え方などは検討していないですね。肝心の教師の「観」は置き去りと言うか……それが気になって、今、教師が自分の「観」に自覚的になるプロジェクトに取り組んでいるんです。
例えば、先生の「これ何だろう?」とか「さあ、見よう、見よう」など何気なく発した言葉には「子ども観」や「教科観」などが含まれているんですね。逆に言えば、何気ない言葉からは、その先生の「観」が見えるというか。
そこで、現場の先生方が、自分の授業中の発話を振り返り、その意味を考え合う中で、お互いの「観」について語り合おうというプログラムをやるんです。そうすると先生たちは内省や交流が深まっていきます。この研究が進んでいけば、先生たちの「技能」に対する「観」についても、何か分かるかもしれません。
私が教師になったばかりの頃、けっこう描き方中心の指導をしていて、でもそこに何か違和感があったんです。そのとき、ある子どもの展覧会を見たときに愕然としたんですね。「この先生が指導した絵は、私と違う。何が違うのだろう」と作品に見入ったのです。どの作品からも子どもの声や息づかいが聴こえてくる。こう手を動かしたであろうとか、こんな身体のリズムがあったのだろうというようなことを感じるのです。まるで子どもがそこにいるかのように思えました。つくりだしている喜びが伝わってくるのです。この体験は、私の「観」が転換する大きなきっかけになりました。
それからは図画工作・美術の研究会や研修会にどんどん出かけて行って、素晴らしい実践者や研究者とたくさん出会って、自分の「感覚や行為」を大切にすることや、「感覚や行為の経験」を積み重ねていくことが大事だなと思うようになりました。
今は、図画工作の時間に子どもが何事かを起こしていく瞬間に立ち会えるのが何より嬉しくて、これからも学びの環境を編み直し続けていければなと思っています。
問題は、それが切実な要請に応じた切実な問題解決の中で生じてくるということです。果たして図画工作の授業の中で、そうした「切実さ」をどれだけ位置付けているのでしょうか?図画工作に限らず学校教育全体で大事にしていかないといけないことだと思うのですが。
また、子どもの技能を支えるために、教師の確かな「観」が必要で、そこには人々との出会いや縁が大切だという指摘も大変心に残りました。技能は、それが生まれる状況、教師の「観」、カリキュラムなど様々な縁起があって、はじめて技能として成立するのでしょうね。
今日はありがとうございました。
※1:ともにかなでる図工室 第26回「オーロラ」
https://www.zukonomikata-nichibun.net/tomonikanaderu26/
※2:ともにかなでる図工室 第22回「絵の具となかよし」
https://www.zukonomikata-nichibun.net/tomonikanaderu22/
コミュニティ・オブ・クリエイティビティーひらめきの生まれるところ(2022年7月末発刊予定) 日本文教出版 ひらめきスケッチ1「ひらめきが連れていくところ」参照。
