学び!とESD
学び!とESD
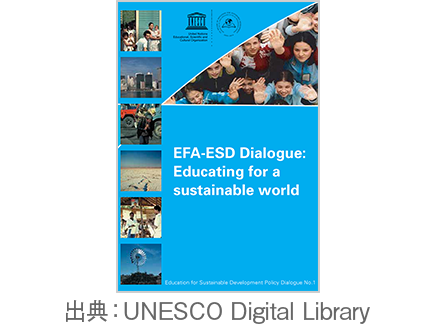
ESDが国連のフラッグシップ事業としてスタートして以来、かれこれ20年が経ちました。「国連ESDの10年」(以下、「10年」と略)以後の歴史をふり返ると、注目度は決して高くはなかったものの、そこに込められた主張やキーフレーズがESDの今後を吟味していく上で貴重であるという論文や報告書がいくつかあります。‘ESD for 2030’(「学び!とESD」Vol.07, Vol.08, Vol.09)も後半に差し掛かった現在、それらをいま一度吟味することは大事な作業となるでしょう。これまでの「ヒューマンとノンヒューマン」等のシリーズに加えて、「いまふり返るESDの重要文献」も不定期のシリーズとして今号から始めます。
「重要文献」のトップバッターは「EFAとESDの対話」(原著:
さて、なぜ60ページにも満たない上記の冊子が重要なのでしょう。それは、ESDの本来の特徴がEFAとの比較によって明らかにされているからであり、またESD誕生から20年以上経った今、その本義をいま一度確認することが必要になってきた世界情勢下に、私たちが置かれているからだと筆者は捉えています。
著者はロス・ウェードとジェニス・パーカー。共に英国の大学で研究する教育学者です。ウェードは2011年に来日し、ユネスコアジア文化センターによるESDの会議で講演したこともある、国際的にも活躍する論客です。
この冊子が刊行されたのが2008年ですから、すでに「10年」がスタートして4年が経っており、運動としてもその特徴を広くアピールしてより拡充していきたい時期にあったと言えます。
冊子の基調トーンは、EFAという「先輩」に敬意を表しつつも、ESDをより明確に特徴づけて、その意義を広めることに見出せます。その表現は丁寧ではありますが、EFAの旧態依然たる性格を所々で批判している論考でもあります。EFAに比べてESDの特徴はその守備範囲の広さであると述べ、それは持続可能な未来に向けた態度・価値観・行動の変容を前提としているため、量的拡大のみならず質的拡充も優先される、とESDを特徴づけています。
ここでEFAは決して量的拡大のみに終始した実践ではなかったことは、筆者もその一端に民間組織の識字運動に携わった経験からも強調しておかねばなりません。とはいえ、その運動は全体として、量的な指標が大きな影響力を持ち、就学率や識字率という数値目標が政策を左右したことは否めず、ウェードらが教育の質を強調するのも理解できます。
さらに、EFAは「開発モデル」として目されるがゆえに、どうしても支配的な開発のあり方、つまり経済成長というモデルの影響から逃れられない。その一方で、ESDは開発のあり方や方向性そのものに対して疑義の眼差しを向けるところにその特徴がある、と指摘しています。これは「学び!とESD」Vol.08でお伝えしたスターリンの主張とも重なり、先を見通した主張だと言えましょう。
EFAは教育を通した貧困削減を目標に掲げる一方で、ESDはそれだけでなく貧困予防も視野に入れた教育である、とも述べられており、以下の表のように各々の特徴が区分けされています。ウェードらは建設的にEFAとESDの特徴を共に活かすことでシナジーを生み出すことを強調していますが、教育機会を万人に保障することが最も優先された時代に、教育の方向性や質を強調したESDは、物議を醸すようなメッセージをもって生まれた時代の申し子だったのです。
EFA |
ESD |
|
|---|---|---|
価値 |
人権に関する価値 |
人権も含めた諸々の価値 |
スキル |
職業上の基礎技能 |
批判的思考やシステム思考、世代間や未来に関する思考 |
表1 貧困問題の解消をめぐるEFAとESDの特徴
出典:Wade and Parker (2008), p.17をもとに筆者作成
こうしたESDならではの特徴をユネスコスクールはじめ、ESDを実践する学校や地域活動が体現できているのかどうか、いま一度、確かめてみる必要があるのではないでしょうか。
このようなメッセージを内包した教育運動であったESDはさぞかし理想をもって勇猛果敢に推進されたように思われるかもしれませんが、当時、ユネスコ本部の国際委員会のメンバーであった筆者からすれば、実際は決してそうではありませんでした。その推進過程は常に試行錯誤だったと言えます。以下に記すように、上記のような批判の対象ともなっていたEFAの専門家にESDの論客たちが助言を求める場面もあったのです。
今となっては教育運動としてのESDの逸話になるのでしょうか、ESDはEFAに助けられた場面もありました。というのは、筆者が「国連ESDの10年」のモニタリング評価専門家会合(MEEG)のメンバーとして日本政府から年に2回の定期会議に派遣されていた頃は、ESDが各国であまりにも広まらない(知られない)という課題に同会合は直面していました。「学び!とESD」で引用されてきたスターリンやウォルスなど、世界で知られるESDの論客が集まってもなかなか乗り越えられない難題でした。
そこに、ユネスコ本部事務局の取り計らいで、EFAを牽引してきた先達の専門家が同会合の会議室に来て助言をしたことがあったのです。曰く、「あなたたちにはピンポイント(ウリ)がない」と。EFAは就学率や識字率の向上というターゲットが共通の認識になっていたがゆえに、教育運動としてやるべきことが明確でしたが、上記の変容を目指すESDの成果は目に見えにくいし、価値観の変容という成果を実感できるまで数年単位の時間がかかるのだ、と。そこで伝えられた具体的なアドバイスは、前述の「守備範囲の広さ」ゆえに「なんでもあり」になってしまいがちなESDを焦点化することでした。具体的に挙げられたのは、「気候変動、生物多様性、防災(災害リスク削減)」という3本柱を掲げるアクチュアルな運動の推進です。その後、「10年」の後半に入り、この3点が強調されながらESDは推進され、地球温暖化の深刻化も相まって、気候変動教育がESDを凌駕するほどに重視される時代になっていったのです。当時、国際的な運動の渦中にいた筆者にとって、それは「親子が逆転」したかのような印象を受けたのでした(「学び!とESD」Vol.18 を参照)。
【参考文献】
- Wade, Ros and Parker, Jenneth (2008)
EFA-ESD Dialogue: Educating for a sustainable world.
(Education for Sustainable Development Policy Dialogue No.1). UNESCO