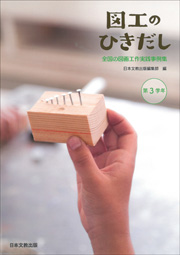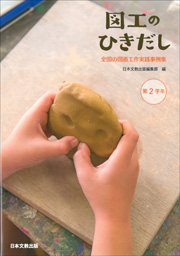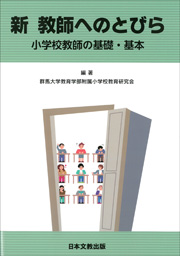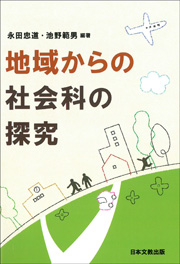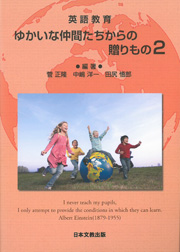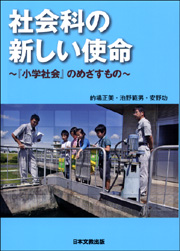すべて
すべて
図工のひきだし 全国の図画工作実践事例集 第3学年
編著者日本文教出版編集部
編著者日本文教出版編集部
定価1980円(本体1800円+税10%)
発行日2015/08/30
体様 A4判、104ページ
発行元 日本文教出版
ISBN 978-4-536-60068-2
教科: 図画工作・美術
図工のひきだし 全国の図画工作実践事例集 第3学年
1~6学年の6分冊で,それぞれの学年に合った実践を掲載しています。
豊富な図版・情景写真により,活動の流れや教師の働きかけ・評価規準がわかりやすく,授業をイメージしやすい構成です。
目次
本書について
ギャラリー
A 表現(1)
【造形遊びをする】
おって、ねじって、丸めて、かさねて、つなげて……
こおりのせかい
つながれ広がれ
ふくらませてビニールパラダイス
ふしぎな形、見いつけた ~形や色を楽しもう~
雪となかよし ~かためて・つんで・色つけて~
A表現(2)
【絵に表す】
生きものといっしょ
色から広がるゆめのせかい
色と形のハーモニー ~わたしのステンド・ペーパー~
えいようたっぷりのおしろの話
おかしの家
おしゃれなりゅう
お花紙でステンドグラス
紙はん画コラージュ ~ハーメルンのふえふき男~
かれ木に花をさかせましょう!
こんなときのわたし ~自分を見つめて~
すきなものえらんで、すきな形にならべて
すってうつしたゆめののりもの
すみでつなぐストーリー
せかい一のしいくがかり
とび出すメッセージ
ふしぎなりんご
へんしん!たんけん!ふしぎなのりものレッツゴー!
○○なしし頭 ~すみと手づくり顔りょうでかく~
回して! かさねて!
【立体に表す】
木切れとえだでつくろう
どんぐりさんのかくれんぼ
とんとんくぎうち
ぬののへんしん
ぼうけん! たからじま
まもりがみシーサー うれシーサー
わたしたちの学校ではっ見! わたしだけの生きもの
【工作に表す】
とび出すしくみのあるプレゼントをつくろう
光とかげのせかいで ~ステンドペープサートをつくろう~
ピコパタトンから生まれたよ
ビックネームカード
ファンタジースクリーン
マイ絵ふででいいかんじ
B鑑賞
【鑑賞する】
アートゲームで見る楽しさをかんじとろう
アートたんけんたい
きっといるよ さがしてみよう
くらしの中にかお、カオ、顔
ここにワクワクびじゅつかん
さわってみると
広がれ、ぼくらの生めいの樹
まるいものたんけんたい
ものがたりのせかい
図工のひきだし 全国の図画工作実践事例集 第3学年
1~6学年の6分冊で,それぞれの学年に合った実践を掲載しています。
豊富な図版・情景写真により,活動の流れや教師の働きかけ・評価規準がわかりやすく,授業をイメージしやすい構成です。
目次
本書について
ギャラリー
A 表現(1)
【造形遊びをする】
おって、ねじって、丸めて、かさねて、つなげて……
こおりのせかい
つながれ広がれ
ふくらませてビニールパラダイス
ふしぎな形、見いつけた ~形や色を楽しもう~
雪となかよし ~かためて・つんで・色つけて~
A表現(2)
【絵に表す】
生きものといっしょ
色から広がるゆめのせかい
色と形のハーモニー ~わたしのステンド・ペーパー~
えいようたっぷりのおしろの話
おかしの家
おしゃれなりゅう
お花紙でステンドグラス
紙はん画コラージュ ~ハーメルンのふえふき男~
かれ木に花をさかせましょう!
こんなときのわたし ~自分を見つめて~
すきなものえらんで、すきな形にならべて
すってうつしたゆめののりもの
すみでつなぐストーリー
せかい一のしいくがかり
とび出すメッセージ
ふしぎなりんご
へんしん!たんけん!ふしぎなのりものレッツゴー!
○○なしし頭 ~すみと手づくり顔りょうでかく~
回して! かさねて!
【立体に表す】
木切れとえだでつくろう
どんぐりさんのかくれんぼ
とんとんくぎうち
ぬののへんしん
ぼうけん! たからじま
まもりがみシーサー うれシーサー
わたしたちの学校ではっ見! わたしだけの生きもの
【工作に表す】
とび出すしくみのあるプレゼントをつくろう
光とかげのせかいで ~ステンドペープサートをつくろう~
ピコパタトンから生まれたよ
ビックネームカード
ファンタジースクリーン
マイ絵ふででいいかんじ
B鑑賞
【鑑賞する】
アートゲームで見る楽しさをかんじとろう
アートたんけんたい
きっといるよ さがしてみよう
くらしの中にかお、カオ、顔
ここにワクワクびじゅつかん
さわってみると
広がれ、ぼくらの生めいの樹
まるいものたんけんたい
ものがたりのせかい
上田 薫 講演集 「今、何をなすべきか」
編著者講演者:上田薫
著者:中川義三
編著者講演者:上田薫
著者:中川義三
定価1980円(本体1800円+税10%)
発行日2015/08/01
体様 A5判、352ページ
発行元 日本文教出版
ISBN 978-4-536-60087-3
カテゴリー: 一般図書
上田 薫 講演集 「今、何をなすべきか」
著者 中川義三氏より
講演者の上田先生は、京都大学文学部哲学科を卒業。学徒出陣、その後見習士官として中国へ。帰国後、文部省に勤務。学習指導要領の編成を2度、道徳の手引き書も作成。名古屋大、東京教育大、立教大などの教授、都留文科大学学長、信濃教育研究所所長等を歴任されました。その間、教育哲学を実践現場で、指導・研究されました。訪問された学校数は数千に上り、一貫して、「問題解決学習」の必要性を説いてこられました。少子高齢化等未曾有の課題を抱える日本、グローバル化する世界の問題に、国民一人一人が前向きに取り組む姿勢を、小さい子どもたちだからこそ、想定外の問題にも、みんなの幸せを実現できるに意欲と夢をはぐくむ学習について語る上田先生の講演集を、ぜひ、1度お手にお取り下さい。あなたの人生に、勇気と希望が生まれます。
問題解決学習は、文科省の推進する「アクティブラーニング」にも取り上げられ、また、平成25年には、文科省による上田先生の聞き取りも行われました。詳しくは、文科省のホームページをご覧下さい。
編集者として10回以上精読した私も、また、1冊を購入し、毎日、読んでいます。そして、反省と勇気を頂いています。
初任の先生に、教育に関係のある方々に、そして、国民一人一人が充実した、幸せな社会を作ることに努力されている方々に送る、勇気と希望の1冊です。
目 次
はじめに 7
上田先生よりの文 10
第1章 「今、何をなすべきか」…………………………………………………12
1 登校拒否をめぐって 14
2 失敗の価値 20
第2章 「問題解決学習を考える」① …………………………………………29
1 あたりまえのことを辛抱する 30
2 人間の教育として自然のこと 34
3 未知のものにぶつかる 40
4 子どもが世の中と向き合う 45
第3章 「教師の姿勢」……………………………………………………………54
1 失敗をこそ生かせ 56
2 受けて立て、引く姿勢 61
3 いじめの克服 69
第4章 「問題解決学習を考える」② …………………………………………77
1 生死のことと関わるのか 78
2 視野貧しき故に 84
3 不完全さが鍵 93
第5章 「指導計画」……………………………………………………………101
1 メモの大切さ 102
2 後始末とカルテ 110
3 見逃すのもいいことだ 115
第6章 「カルテによる教師の深まり」………………………………………121
1 カルテは教師のためにある 122
2 驚きをもとにして 130
3 やわらかくもちこたえる 138
第7章 「全体のけしき」………………………………………………………149
1 有事に強い 150
2 生き生きと打ちこめるように 157
3 主体的な子は視野深く 164
◆質問に答えて◆
① 「裸になる」ということ 174
② ハプニングに、どうぶつかるか 175
③ 実践記録で大切なこと 176
④ 上田先生の思想の原点 177
第8章 「想像力…イマジネーション」………………………………………179
1 人間を育てる根幹として 180
2 発見も、さし迫った判断も 188
3 自分を突き出す我慢 196
第9章 「教師の発想を生み出すカルテ」① …………………………………205
1 立体性のこと 206
2 カルテの奥深さ 213
3 完全で自分を守ろうとする 221
◆質問に答えて◆
① カルテの中の驚き 230
第10章 「教師の発想を生み出すカルテ」② ……………………………………237
1 カルテは教師を変えるためにある 238
2 総合の重要さ、失敗の重要さ 246
3 たがいに人間としての信頼を 256
◆質問に答えて◆
① つまづきを生かす 267
② 子どもを立体化して捉える 271
③ 子どもを信じることについて 273
第11章 「子どもをやりがいある授業に導くには」…………………………277
1 後始末ができるということ 278
2 「独りぼっち」を大切にすること 287
3 どうなれば信頼が生まれるか 296
第12章 「総合学習をめぐって」………………………………………………305
1 総合が好きにならなくては 306
2 個性的であればこそ、総合が生きる 316
3 生きている人間のあり方をこそ大切に 327
◆質問に答えて◆
① 生きる要求を核として展開する総合学習 336
② 総合学習の年間計画 337
③ 教科学習と総合学習の関連 341
あとがき 349
上田 薫 講演集 「今、何をなすべきか」
著者 中川義三氏より
講演者の上田先生は、京都大学文学部哲学科を卒業。学徒出陣、その後見習士官として中国へ。帰国後、文部省に勤務。学習指導要領の編成を2度、道徳の手引き書も作成。名古屋大、東京教育大、立教大などの教授、都留文科大学学長、信濃教育研究所所長等を歴任されました。その間、教育哲学を実践現場で、指導・研究されました。訪問された学校数は数千に上り、一貫して、「問題解決学習」の必要性を説いてこられました。少子高齢化等未曾有の課題を抱える日本、グローバル化する世界の問題に、国民一人一人が前向きに取り組む姿勢を、小さい子どもたちだからこそ、想定外の問題にも、みんなの幸せを実現できるに意欲と夢をはぐくむ学習について語る上田先生の講演集を、ぜひ、1度お手にお取り下さい。あなたの人生に、勇気と希望が生まれます。
問題解決学習は、文科省の推進する「アクティブラーニング」にも取り上げられ、また、平成25年には、文科省による上田先生の聞き取りも行われました。詳しくは、文科省のホームページをご覧下さい。
編集者として10回以上精読した私も、また、1冊を購入し、毎日、読んでいます。そして、反省と勇気を頂いています。
初任の先生に、教育に関係のある方々に、そして、国民一人一人が充実した、幸せな社会を作ることに努力されている方々に送る、勇気と希望の1冊です。
目 次
はじめに 7
上田先生よりの文 10
第1章 「今、何をなすべきか」…………………………………………………12
1 登校拒否をめぐって 14
2 失敗の価値 20
第2章 「問題解決学習を考える」① …………………………………………29
1 あたりまえのことを辛抱する 30
2 人間の教育として自然のこと 34
3 未知のものにぶつかる 40
4 子どもが世の中と向き合う 45
第3章 「教師の姿勢」……………………………………………………………54
1 失敗をこそ生かせ 56
2 受けて立て、引く姿勢 61
3 いじめの克服 69
第4章 「問題解決学習を考える」② …………………………………………77
1 生死のことと関わるのか 78
2 視野貧しき故に 84
3 不完全さが鍵 93
第5章 「指導計画」……………………………………………………………101
1 メモの大切さ 102
2 後始末とカルテ 110
3 見逃すのもいいことだ 115
第6章 「カルテによる教師の深まり」………………………………………121
1 カルテは教師のためにある 122
2 驚きをもとにして 130
3 やわらかくもちこたえる 138
第7章 「全体のけしき」………………………………………………………149
1 有事に強い 150
2 生き生きと打ちこめるように 157
3 主体的な子は視野深く 164
◆質問に答えて◆
① 「裸になる」ということ 174
② ハプニングに、どうぶつかるか 175
③ 実践記録で大切なこと 176
④ 上田先生の思想の原点 177
第8章 「想像力…イマジネーション」………………………………………179
1 人間を育てる根幹として 180
2 発見も、さし迫った判断も 188
3 自分を突き出す我慢 196
第9章 「教師の発想を生み出すカルテ」① …………………………………205
1 立体性のこと 206
2 カルテの奥深さ 213
3 完全で自分を守ろうとする 221
◆質問に答えて◆
① カルテの中の驚き 230
第10章 「教師の発想を生み出すカルテ」② ……………………………………237
1 カルテは教師を変えるためにある 238
2 総合の重要さ、失敗の重要さ 246
3 たがいに人間としての信頼を 256
◆質問に答えて◆
① つまづきを生かす 267
② 子どもを立体化して捉える 271
③ 子どもを信じることについて 273
第11章 「子どもをやりがいある授業に導くには」…………………………277
1 後始末ができるということ 278
2 「独りぼっち」を大切にすること 287
3 どうなれば信頼が生まれるか 296
第12章 「総合学習をめぐって」………………………………………………305
1 総合が好きにならなくては 306
2 個性的であればこそ、総合が生きる 316
3 生きている人間のあり方をこそ大切に 327
◆質問に答えて◆
① 生きる要求を核として展開する総合学習 336
② 総合学習の年間計画 337
③ 教科学習と総合学習の関連 341
あとがき 349
図工のひきだし 全国の図画工作実践事例集 第2学年
編著者日本文教出版編集部
編著者日本文教出版編集部
定価1980円(本体1800円+税10%)
発行日2015/06/28
体様 A4判、96ページ
発行元 日本文教出版
ISBN 978-4-536-60067-5
教科: 図画工作・美術
図工のひきだし 全国の図画工作実践事例集 第2学年
1~6学年の6分冊で,それぞれの学年に合った実践を掲載しています。
豊富な図版・情景写真により,活動の流れや教師の働きかけ・評価規準がわかりやすく,授業をイメージしやすい構成です。
目次
本書について
ギャラリー
A 表現(1)
【造形遊びをする】
カラフル いろ水
カラフル ひらひら
土を かんじて
ひかり マジック
ようこそ! せんの せかいへ
わっかの かたちを つかって……
A 表現(2)
【絵に表す】
あきからの おくりもの
ありさんの ほらあな たんけん
1ぱんで 3ど たのしむ かみはんが ~へんしん する きょうりゅう~
うつして うつして
うつして みると
かげを うつして たのしもう
カラフル コロコロ
きせつの カーテンを つくろう ~カラーテープの さんぽから~
ザリガニ 先生
しろい え
だいじな だいじな あかちゃん
つなげて ひろげて みんなの え
なにに かいてみる? ~スイミーの せかい~
ふしぎな たまご
ふわふわ はじけたら
○○が 町に やって きた
○○を たべちゃった 虫さん
ゆめまくら
【立体に表す】
かみを 立てて
カラフル たんじょう日ケーキを つくろう!
ケーキやさん
スペシャル☆パフェ
たわしさんの 大ぼうけん
どうぶつさんの おうち
見て,かんじて,つくって ニキに ちょうせん
ねん土で へんしん いろ水 タワー
ふくろちゃん
ふしぎな ともだち ずかん ~こんな ともだち,学校に いたら いいな~
ふわふわ フィッシュ
ゆうえんちを つくろう
わくわく どきどき おもい出の アート・ロード
【工作に表す】
カップくんと いっしょ
出ぱつ~ わくわく れっ車!
はつめい! スゴイ ぼうし
わくわく おしゃれな ぼうし
B 鑑賞
【鑑賞する】
えっ?絵! ~よーく 見てね~
どの カード?
なんでも あー! と
はるの いろ見つけ
図工のひきだし 全国の図画工作実践事例集 第2学年
1~6学年の6分冊で,それぞれの学年に合った実践を掲載しています。
豊富な図版・情景写真により,活動の流れや教師の働きかけ・評価規準がわかりやすく,授業をイメージしやすい構成です。
目次
本書について
ギャラリー
A 表現(1)
【造形遊びをする】
カラフル いろ水
カラフル ひらひら
土を かんじて
ひかり マジック
ようこそ! せんの せかいへ
わっかの かたちを つかって……
A 表現(2)
【絵に表す】
あきからの おくりもの
ありさんの ほらあな たんけん
1ぱんで 3ど たのしむ かみはんが ~へんしん する きょうりゅう~
うつして うつして
うつして みると
かげを うつして たのしもう
カラフル コロコロ
きせつの カーテンを つくろう ~カラーテープの さんぽから~
ザリガニ 先生
しろい え
だいじな だいじな あかちゃん
つなげて ひろげて みんなの え
なにに かいてみる? ~スイミーの せかい~
ふしぎな たまご
ふわふわ はじけたら
○○が 町に やって きた
○○を たべちゃった 虫さん
ゆめまくら
【立体に表す】
かみを 立てて
カラフル たんじょう日ケーキを つくろう!
ケーキやさん
スペシャル☆パフェ
たわしさんの 大ぼうけん
どうぶつさんの おうち
見て,かんじて,つくって ニキに ちょうせん
ねん土で へんしん いろ水 タワー
ふくろちゃん
ふしぎな ともだち ずかん ~こんな ともだち,学校に いたら いいな~
ふわふわ フィッシュ
ゆうえんちを つくろう
わくわく どきどき おもい出の アート・ロード
【工作に表す】
カップくんと いっしょ
出ぱつ~ わくわく れっ車!
はつめい! スゴイ ぼうし
わくわく おしゃれな ぼうし
B 鑑賞
【鑑賞する】
えっ?絵! ~よーく 見てね~
どの カード?
なんでも あー! と
はるの いろ見つけ
図工のひきだし 全国の図画工作実践事例集 第1学年
編著者日本文教出版編集部
編著者日本文教出版編集部
定価1980円(本体1800円+税10%)
発行日2015/06/28
体様 A4判、96ページ
発行元 日本文教出版
ISBN 978-4-536-60066-8
教科: 図画工作・美術
図工のひきだし 全国の図画工作実践事例集 第1学年
1~6学年の6分冊で,それぞれの学年に合った実践を掲載しています。
豊富な図版・情景写真により,活動の流れや教師の働きかけ・評価規準がわかりやすく,授業をイメージしやすい構成です。
目次
本書について
ギャラリー
A 表現(1)
【造形遊びをする】
あれ これ ぺったん
かみと なかよし
クレヨンと なかよし
すなばが だいへんしん!
でこぼこ たんけんたい うつして あそぼう
どんぐり ころころ せんの おさんぽ
ならべて つないで……
ならべて・つんで
パズルで アート
まほうの めいろ
A 表現(2)
【絵に表す】
かたちから うまれたよ
かたちから うまれたよ ~○○みぃつけ!~
コロコロ ぺったん
こんな いきもの いたら いいな
じゅわ じゅわ にじみ
だいすき! みんなの えのみの き
たのしく とんだよ
つないで つないで おはなし ひろがれ
どんな かたちの かみにも
ピカソに ちゃれんじ!
ペタペタ ロボット
【立体に表す】
いきもの だいすき
おうちの はこを すてきに へ~んしん!
キラキラ むしランド
これは なんでしょう
すんでみたいな ゆめの おしろ
どうぶつさんの おうち
ならべて つんで ~マイタワー~
はこから うまれた ふしぎな いきもの
はこの なかまたち ~だいじな おともだちを つくろう~
はこの なかまたち ~ならべて つくろう~
ふくろちゃん
ふしぎな てるてるぼうずから ~おおきく なったね、ぼく・わたし~
【工作に表す】
おって たてて ゆめの まち
コロコロ ころがるよ!
コロコロ へんしん!
そのイス、いーっすね!
まどを ひらいて
みんなで かざろう
ゆらゆら シーソー
B 鑑賞
【鑑賞する】
アートで あそぼ
いろの おまもりを つくろう
かんじた ことを
○○いろの くにの おしろ
図工のひきだし 全国の図画工作実践事例集 第1学年
1~6学年の6分冊で,それぞれの学年に合った実践を掲載しています。
豊富な図版・情景写真により,活動の流れや教師の働きかけ・評価規準がわかりやすく,授業をイメージしやすい構成です。
目次
本書について
ギャラリー
A 表現(1)
【造形遊びをする】
あれ これ ぺったん
かみと なかよし
クレヨンと なかよし
すなばが だいへんしん!
でこぼこ たんけんたい うつして あそぼう
どんぐり ころころ せんの おさんぽ
ならべて つないで……
ならべて・つんで
パズルで アート
まほうの めいろ
A 表現(2)
【絵に表す】
かたちから うまれたよ
かたちから うまれたよ ~○○みぃつけ!~
コロコロ ぺったん
こんな いきもの いたら いいな
じゅわ じゅわ にじみ
だいすき! みんなの えのみの き
たのしく とんだよ
つないで つないで おはなし ひろがれ
どんな かたちの かみにも
ピカソに ちゃれんじ!
ペタペタ ロボット
【立体に表す】
いきもの だいすき
おうちの はこを すてきに へ~んしん!
キラキラ むしランド
これは なんでしょう
すんでみたいな ゆめの おしろ
どうぶつさんの おうち
ならべて つんで ~マイタワー~
はこから うまれた ふしぎな いきもの
はこの なかまたち ~だいじな おともだちを つくろう~
はこの なかまたち ~ならべて つくろう~
ふくろちゃん
ふしぎな てるてるぼうずから ~おおきく なったね、ぼく・わたし~
【工作に表す】
おって たてて ゆめの まち
コロコロ ころがるよ!
コロコロ へんしん!
そのイス、いーっすね!
まどを ひらいて
みんなで かざろう
ゆらゆら シーソー
B 鑑賞
【鑑賞する】
アートで あそぼ
いろの おまもりを つくろう
かんじた ことを
○○いろの くにの おしろ
子どものための美術 Art for Children
図画工作・造形教育教材集
編著者福岡教育大学美術教育講座
編著者福岡教育大学美術教育講座
定価2750円(本体2500円+税10%)
発行日2015/03/30
体様 A4判、96ページ
発行元 日本文教出版
ISBN 978-4-536-60082-8
カテゴリー: 大学・短大テキスト
教科: 図画工作・美術
子どものための美術 Art for Children
目次
本書の発行にあたって
この本を読む人へ
1 描いてみよう
色のくにからきたなかま コラージュで描こう
ぬってけずってスクラッチ コリコリけずって描く
10才のわたし
ギョ!タク版画 紙粘土で版画を刷ろう
ようこそ!私たちの世界へ ハトメを使って動かそう
私の心と とけあった木 心のもようと木の特徴を組み合わせたら
もう一人の私 いろいろな「描き方」,いろいろな「自画像」
この気持ちはどんな色? 色で私を表現しよう
見えないから見えてくるもの
絵の具の研究 絵の具の混色について学ぶ
水彩絵の具の使い方 基本的な使い方と表現効果について
墨色の世界 濃淡と筆使いを習得して水彩画を描く
コラム 図工室をきれいに変身させる
2 つくってみよう
お面をつくろう 自分の「守り神」~スッポリかぶれる「お面」のせいさく
秋のぼうし <造形遊び> 季節の中で遊ぼう
モビールの楽しみ ゆうゆうとたゆたう空間の造形
夢あふれるMUNAKATAランド
パズルの街 私だけの街をつくろう
組み木のパズル 板から生まれるいきものたち
「ねぶた」づくり<共同制作> みんなでつくってたくさんの人に楽しんでもらおう
まわるまわる色が変わる ぶんぶんゴマで混色を楽しもう
どんな気持ち 色とかたちで表わそう
ポスターで伝えたい! 一目で伝わるポスターの描き方
クレヨンをつくろう
いい音するかな?ねん土で鈴をつくろう 土鈴づくり
木の匙をつくろう1 バターナイフづくり
木の匙をつくろう2 つくろう!ごちそうスプーン
ピカピカ銀メダルをつくろう 溶けた金属に紙粘土鋳型に流し込もう
キラキラな顔をつくろう! 溶けた金属に鋳型に流し込もう
コラム 子どもの気分になって図工室で活動
3 みつめてみよう
パブリックアート 自分たちの美術館
どっちが強いかな? 仁王像を比べよう
どんな人かな? 誰と誰が仲良しかな?
近くのアートをさがしてみよう
美術館に行ってみよう
美術館で学ぼう,楽しもう ワークショップに参加してみよう
作品を飾ってみよう 作品のよさを工夫して伝えよう
作品をつくる アーティストの栗林隆さんに聞いてみました
図工実践記録 2013
執筆者一覧
子どものための美術 Art for Children
目次
本書の発行にあたって
この本を読む人へ
1 描いてみよう
色のくにからきたなかま コラージュで描こう
ぬってけずってスクラッチ コリコリけずって描く
10才のわたし
ギョ!タク版画 紙粘土で版画を刷ろう
ようこそ!私たちの世界へ ハトメを使って動かそう
私の心と とけあった木 心のもようと木の特徴を組み合わせたら
もう一人の私 いろいろな「描き方」,いろいろな「自画像」
この気持ちはどんな色? 色で私を表現しよう
見えないから見えてくるもの
絵の具の研究 絵の具の混色について学ぶ
水彩絵の具の使い方 基本的な使い方と表現効果について
墨色の世界 濃淡と筆使いを習得して水彩画を描く
コラム 図工室をきれいに変身させる
2 つくってみよう
お面をつくろう 自分の「守り神」~スッポリかぶれる「お面」のせいさく
秋のぼうし <造形遊び> 季節の中で遊ぼう
モビールの楽しみ ゆうゆうとたゆたう空間の造形
夢あふれるMUNAKATAランド
パズルの街 私だけの街をつくろう
組み木のパズル 板から生まれるいきものたち
「ねぶた」づくり<共同制作> みんなでつくってたくさんの人に楽しんでもらおう
まわるまわる色が変わる ぶんぶんゴマで混色を楽しもう
どんな気持ち 色とかたちで表わそう
ポスターで伝えたい! 一目で伝わるポスターの描き方
クレヨンをつくろう
いい音するかな?ねん土で鈴をつくろう 土鈴づくり
木の匙をつくろう1 バターナイフづくり
木の匙をつくろう2 つくろう!ごちそうスプーン
ピカピカ銀メダルをつくろう 溶けた金属に紙粘土鋳型に流し込もう
キラキラな顔をつくろう! 溶けた金属に鋳型に流し込もう
コラム 子どもの気分になって図工室で活動
3 みつめてみよう
パブリックアート 自分たちの美術館
どっちが強いかな? 仁王像を比べよう
どんな人かな? 誰と誰が仲良しかな?
近くのアートをさがしてみよう
美術館に行ってみよう
美術館で学ぼう,楽しもう ワークショップに参加してみよう
作品を飾ってみよう 作品のよさを工夫して伝えよう
作品をつくる アーティストの栗林隆さんに聞いてみました
図工実践記録 2013
執筆者一覧
新 教師へのとびら
小学校教師の基礎・基本
編著者群馬大学教育学部附属小学校教育研究会
編著者群馬大学教育学部附属小学校教育研究会
定価2475円(本体2250円+税10%)
発行日2015/03/25
体様 A4判、192ページ
発行元 日本文教出版
ISBN 978-4-536-60077-4
教科: 教科全般
新 教師へのとびら
【目次】
はじめに
目次
第1章 教育実習の概要
Ⅰ 教育実習の目的
Ⅱ 教育実習上の心得
1 教師としての自覚
2 勤務に関する基本事項
Ⅲ 教育実習中の生活
1 週予定表と校時表
2 1日の生活
Ⅳ 事前指導
1 事前指導の内容
Ⅴ 本実習
1 学習参観
2 実習録
3 学習指導
4 研究授業
第2章 学校経営・学級経営
Ⅰ 小学校教育の本質
1 小学校教育の目的・目標
2 小学校教育の基本
3 小学校教育の特徴
4 教育課程の編成・実施
5 小学校教師に求められる資質
6 小学校教育をめぐる課題
Ⅱ 学校経営と附属小学校
1 附属小学校の経営の基盤
2 附属小学校の教育目標
3 附属小学校の教育方針
4 附属小学校の経営の重点
5 附属小学校の学校運営組織
Ⅲ 学級経営と担任の役割
1 担任の役割
2 児童理解の心構え
3 学級集団の育成
4 教室環境の整備
5 授業時間外の活動
6 家庭,地域との連携・協力
7 学校の事務
8 その他
Ⅳ 児童の発達と理解
1 児童の発達
2 児童理解
第3章 生徒指導・その他の教育活動
Ⅰ 生徒指導
1 生徒指導の意義
2 生徒指導の目標
3 生徒指導の内容
4 生徒指導の原理・方法
Ⅱ 人権教育
1 人権教育の目標
2 人権教育の内容
Ⅲ 学校保健
1 学校保健の概要
2 保健教育・保健管理の進め方
3 保健室の利用
4 学校で行う救急処置活動
5 救急処置活動の流れ
第4章 学習指導
Ⅰ 学習指導
1 学習指導の原則
2 学習指導の計画
Ⅱ 教材研究と学習指導案
1 教材研究
2 学習指導案
Ⅲ 学習指導の実際
1 学習指導の過程とその意味
2 学習指導の形態・方法
3 学習指導の技術
Ⅳ 研究授業
1 研究授業の意義
2 研究授業に関わる役割
3 学習指導の見方
第5章 各教科等の特色と指導案の書き方
1 国語科
2 社会科
3 算数科
4 理 科
5 生活科
6 音楽科
7 図画工作科
8 家庭科
9 体育科
10 道 徳
11 外国語活動
12 総合的な学習の時間
13 特別活動
巻末資料
あとがき
新 教師へのとびら
【目次】
はじめに
目次
第1章 教育実習の概要
Ⅰ 教育実習の目的
Ⅱ 教育実習上の心得
1 教師としての自覚
2 勤務に関する基本事項
Ⅲ 教育実習中の生活
1 週予定表と校時表
2 1日の生活
Ⅳ 事前指導
1 事前指導の内容
Ⅴ 本実習
1 学習参観
2 実習録
3 学習指導
4 研究授業
第2章 学校経営・学級経営
Ⅰ 小学校教育の本質
1 小学校教育の目的・目標
2 小学校教育の基本
3 小学校教育の特徴
4 教育課程の編成・実施
5 小学校教師に求められる資質
6 小学校教育をめぐる課題
Ⅱ 学校経営と附属小学校
1 附属小学校の経営の基盤
2 附属小学校の教育目標
3 附属小学校の教育方針
4 附属小学校の経営の重点
5 附属小学校の学校運営組織
Ⅲ 学級経営と担任の役割
1 担任の役割
2 児童理解の心構え
3 学級集団の育成
4 教室環境の整備
5 授業時間外の活動
6 家庭,地域との連携・協力
7 学校の事務
8 その他
Ⅳ 児童の発達と理解
1 児童の発達
2 児童理解
第3章 生徒指導・その他の教育活動
Ⅰ 生徒指導
1 生徒指導の意義
2 生徒指導の目標
3 生徒指導の内容
4 生徒指導の原理・方法
Ⅱ 人権教育
1 人権教育の目標
2 人権教育の内容
Ⅲ 学校保健
1 学校保健の概要
2 保健教育・保健管理の進め方
3 保健室の利用
4 学校で行う救急処置活動
5 救急処置活動の流れ
第4章 学習指導
Ⅰ 学習指導
1 学習指導の原則
2 学習指導の計画
Ⅱ 教材研究と学習指導案
1 教材研究
2 学習指導案
Ⅲ 学習指導の実際
1 学習指導の過程とその意味
2 学習指導の形態・方法
3 学習指導の技術
Ⅳ 研究授業
1 研究授業の意義
2 研究授業に関わる役割
3 学習指導の見方
第5章 各教科等の特色と指導案の書き方
1 国語科
2 社会科
3 算数科
4 理 科
5 生活科
6 音楽科
7 図画工作科
8 家庭科
9 体育科
10 道 徳
11 外国語活動
12 総合的な学習の時間
13 特別活動
巻末資料
あとがき
地域からの社会科の探究
編著者永田忠道、池野範男
編著者永田忠道、池野範男
定価2420円(本体2200円+税10%)
発行日2014/12/15
体様 A5判、280ページ
発行元 日本文教出版
ISBN 978-4-536-60081-1
教科: 社会
地域からの社会科の探究
その社会科を創設・指導してこられた先達にお話を伺うとともに,
現在行われている実践を紹介することで,日本の社会科の深化・発展の可能性を探る。
<目次>
はじめに
序 章 各地域の先達と多様な社会科の探究
1 社会科のゆるやかな交通整理
2 先達による社会科とゆるやかな交通整理との関連
3 ある枠組みだけでは描ききれないからこそ魅力的な社会科の多様性
第1部 知識・概念・教材を軸とする探究学習
第1章 知識の構造化による探究学習
第1節 先達:松田康博先生と伊東冨士雄先生のお話
第2節 東京都の実践例から
①地域が支えるお祭りとわたしたち(小3)
②つながるからつなげるへ(小5)
第3節 [研究者コメント]東京の社会科
第2章 教材の人間化による探究学習
第1節 先達:立岡誠先生のお話
第2節 長崎の実践例から
くらしを支える情報(小5)
第3節 [研究者コメント]「人間化」というキーワードが示す道
第3章 中心概念による子どもの探究学習
第1節 先達:佐藤正一郎先生のお話
第2節 千葉の実践例から
これからの食生活とわたしたち(小5)
第3節 [研究者コメント]レジェンドな実践者と地域性をふまえた実践例
第4章 「窮め探り,その極を覧る」探究学習
第1節 先達:辻迪夫先生のお話
第2節 京都市の実践例から
情報を生かすわたしたち(小5)
第3節 [研究者コメント]歴史と伝統ある京都社研「極覧」の神髄とは
第2部 子どもと人間の意識を軸とする問題解決学習
第5章 「子どもの意識の流れ」による問題解決学習
第1節 先達:堀公明先生のお話
第2節 大阪市の実践例から
ものを作る人びとのしごと(小3)
第3節 [研究者コメント]堀公明社会科の理論と実践
第6章 「なお,……したい」ことをめざす問題解決学習
第1節 先達:安東裕先生のお話
第2節 大分の実践例から
資源プラ分別のきまりをゆるめた清掃センターのSさん(小4)
第3節 [研究者コメント]教師が本気で子どもたちに問題解決を期待するとき,
子どもたちは無意識のうちにそれに応える
第7章 人間教育の核としての問題解決学習
第1節 先達:深谷孟延先生のお話
第2節 愛知の実践例から
我々の誇りを未来に伝える~半田に残る歴史遺産と私たちとのつながり~(小6)
第3節 [研究者コメント]問題解決学習のこれから
第8章 子どもが主体的に追究する問題解決学習
第1節 先達:片桐清司先生のお話
第2節 和歌山の実践例から
もっともっと工業!~オカジのダンボール作りから考えよう~(小5)
第3節 [研究者コメント]地域に根づく問題解決学習
第3部 子ども同士や地域を軸とする関連相関による社会科学習
第9章 「聴き合い」による社会科
第1節 先達:山田耕司先生のお話
第2節 福岡市の実践例から
オッペケペー節と自由民権運動(小6)
第3節 [研究者コメント]戦後社会科の初志を引き継ぐ実践として
第10章 子どもの身近なかかわりを核とする社会科
第1節 先達:砂田武嗣先生のお話
第2節 石川の実践例から
新しい日本 平和な国へ~東京オリンピックと昭和時代~(小6)
第3節 [研究者コメント]受け継がれる社会科実践研究
第11章 「こ・た・ね(個・多・練)」の社会科
第1節 先達:渋谷光夫先生のお話
第2節 山形の実践例から
ごみの?(ハテナ)大研究(小4)
第3節 [研究者コメント]芳醇端麗の社会科「こたね」─子どもの主体性喚起と
教師としての条件の追究─228
第12章 子どもが自ら楽しく取り組む教材の開発による社会科
第1節 先達:岡崎明宏先生のお話
第2節 岡山の実践例から
アジア・太平洋に広がる戦争と国民生活(小6)
第3節 [研究者コメント]自ら学ぶ子どもを育てる社会科の継承と創造
第13章 郷土室の整備と地域素材の教材化による社会科
第1節 先達:中村雅利先生のお話
第2節 茨城の実践例から
金沢用水(小4)
第3節 [研究者コメント]足下からの社会科地域教材の開発
終 章 世界的視野の中での地域からの社会科の探究
1 終章の意図
2 本書の意図と成果
3 世界の中の社会科
地域からの社会科の探究
その社会科を創設・指導してこられた先達にお話を伺うとともに,
現在行われている実践を紹介することで,日本の社会科の深化・発展の可能性を探る。
<目次>
はじめに
序 章 各地域の先達と多様な社会科の探究
1 社会科のゆるやかな交通整理
2 先達による社会科とゆるやかな交通整理との関連
3 ある枠組みだけでは描ききれないからこそ魅力的な社会科の多様性
第1部 知識・概念・教材を軸とする探究学習
第1章 知識の構造化による探究学習
第1節 先達:松田康博先生と伊東冨士雄先生のお話
第2節 東京都の実践例から
①地域が支えるお祭りとわたしたち(小3)
②つながるからつなげるへ(小5)
第3節 [研究者コメント]東京の社会科
第2章 教材の人間化による探究学習
第1節 先達:立岡誠先生のお話
第2節 長崎の実践例から
くらしを支える情報(小5)
第3節 [研究者コメント]「人間化」というキーワードが示す道
第3章 中心概念による子どもの探究学習
第1節 先達:佐藤正一郎先生のお話
第2節 千葉の実践例から
これからの食生活とわたしたち(小5)
第3節 [研究者コメント]レジェンドな実践者と地域性をふまえた実践例
第4章 「窮め探り,その極を覧る」探究学習
第1節 先達:辻迪夫先生のお話
第2節 京都市の実践例から
情報を生かすわたしたち(小5)
第3節 [研究者コメント]歴史と伝統ある京都社研「極覧」の神髄とは
第2部 子どもと人間の意識を軸とする問題解決学習
第5章 「子どもの意識の流れ」による問題解決学習
第1節 先達:堀公明先生のお話
第2節 大阪市の実践例から
ものを作る人びとのしごと(小3)
第3節 [研究者コメント]堀公明社会科の理論と実践
第6章 「なお,……したい」ことをめざす問題解決学習
第1節 先達:安東裕先生のお話
第2節 大分の実践例から
資源プラ分別のきまりをゆるめた清掃センターのSさん(小4)
第3節 [研究者コメント]教師が本気で子どもたちに問題解決を期待するとき,
子どもたちは無意識のうちにそれに応える
第7章 人間教育の核としての問題解決学習
第1節 先達:深谷孟延先生のお話
第2節 愛知の実践例から
我々の誇りを未来に伝える~半田に残る歴史遺産と私たちとのつながり~(小6)
第3節 [研究者コメント]問題解決学習のこれから
第8章 子どもが主体的に追究する問題解決学習
第1節 先達:片桐清司先生のお話
第2節 和歌山の実践例から
もっともっと工業!~オカジのダンボール作りから考えよう~(小5)
第3節 [研究者コメント]地域に根づく問題解決学習
第3部 子ども同士や地域を軸とする関連相関による社会科学習
第9章 「聴き合い」による社会科
第1節 先達:山田耕司先生のお話
第2節 福岡市の実践例から
オッペケペー節と自由民権運動(小6)
第3節 [研究者コメント]戦後社会科の初志を引き継ぐ実践として
第10章 子どもの身近なかかわりを核とする社会科
第1節 先達:砂田武嗣先生のお話
第2節 石川の実践例から
新しい日本 平和な国へ~東京オリンピックと昭和時代~(小6)
第3節 [研究者コメント]受け継がれる社会科実践研究
第11章 「こ・た・ね(個・多・練)」の社会科
第1節 先達:渋谷光夫先生のお話
第2節 山形の実践例から
ごみの?(ハテナ)大研究(小4)
第3節 [研究者コメント]芳醇端麗の社会科「こたね」─子どもの主体性喚起と
教師としての条件の追究─228
第12章 子どもが自ら楽しく取り組む教材の開発による社会科
第1節 先達:岡崎明宏先生のお話
第2節 岡山の実践例から
アジア・太平洋に広がる戦争と国民生活(小6)
第3節 [研究者コメント]自ら学ぶ子どもを育てる社会科の継承と創造
第13章 郷土室の整備と地域素材の教材化による社会科
第1節 先達:中村雅利先生のお話
第2節 茨城の実践例から
金沢用水(小4)
第3節 [研究者コメント]足下からの社会科地域教材の開発
終 章 世界的視野の中での地域からの社会科の探究
1 終章の意図
2 本書の意図と成果
3 世界の中の社会科
英語教育 ゆかいな仲間たちからの贈りもの2
編著者菅 正隆、中嶋 洋一、田尻 悟郎
編著者菅 正隆、中嶋 洋一、田尻 悟郎
定価1980円(本体1800円+税10%)
発行日2014/12/15
体様 A5判、256ページ
発行元 日本文教出版
ISBN 978-4-536-60078-1
カテゴリー: 一般図書
英語教育 ゆかいな仲間たちからの贈りもの2
前作『英語教育 ゆかいな仲間たちからの贈りもの』が発刊されて早10年。英語教育はもとより,教育全般,社会情勢,すべてが大きく変わろうとしている。しかし,変わらない者たちがここにいる。中嶋洋一,髙橋一幸,田尻悟郎,久保野雅史,そして菅正隆。(中略)全国でゲリラ的に開催している「英語教育 ゆかいな仲間たち」の司会を務める小畑壽,松永淳子,そして,それを支えるサポーターも増えた。参加いただいた方々も全国で総計5,000人を優に超えた。全員が「ゆかいな仲間たち」の一員なのである。
ところで,昨今,日本が間違った方向にベクトルが向かっているように感じる。教育に関しても妙な方向に進みかけている。日本が危ない。教育が危ない。そして,子どもが危ない。この状況を憂えた3人がまたまた立ち上がった。中嶋洋一,田尻悟郎,菅正隆,そして,お笑い小畑壽を加えた何とも微妙な4人組。それを猛獣使いのごとく操る司会者松永淳子。さあ,『ゆかいな仲間たち』の第2弾の発信だ。(後略)
◇目次
刊行に寄せて(髙橋 一幸)
はじめに(菅 正隆)
1章 日本の教育にもの申す! 特別座談会
菅 正隆・中嶋 洋一・田尻 悟郎・小畑 壽・松永 淳子(コーディネーター)
1節 昨今の日本の教育
2節 昨今の英語教育の課題
3節 他教科から見た英語教育の怪
4節 小学校の英語教育
5節 中学校の英語教育
6節 高等学校の英語教育
7節 大学の英語教育
8節 入試について
9節 教科書・教材・教具
10節 指導力を向上させる術
11節 英語力を向上させるには
12節 13年経った「ゆかいな仲間たち」秘話
2章 「ゆかいな仲間たち」からのメッセージ
1節 人の優しさに触れる(菅 正隆)
2節 研究授業をするに当たって(田尻 悟郎)
3節 「当たり前」と考えられる「空気」を作ろう!(中嶋 洋一)
4節 「ゆかいな仲間たち」とジョイントトーク(小畑 壽)
5節 「ゆかいな仲間たち」との13年(松永 淳子)
6節 臨時定員増の実員化-指名打者から先発メンバーへ-(久保野 雅史)
おわりに
―充実した教員生活を送る秘訣―(田尻 悟郎)
―Edutainmentを目指そう―(中嶋 洋一)
著者紹介
英語教育 ゆかいな仲間たちからの贈りもの2
前作『英語教育 ゆかいな仲間たちからの贈りもの』が発刊されて早10年。英語教育はもとより,教育全般,社会情勢,すべてが大きく変わろうとしている。しかし,変わらない者たちがここにいる。中嶋洋一,髙橋一幸,田尻悟郎,久保野雅史,そして菅正隆。(中略)全国でゲリラ的に開催している「英語教育 ゆかいな仲間たち」の司会を務める小畑壽,松永淳子,そして,それを支えるサポーターも増えた。参加いただいた方々も全国で総計5,000人を優に超えた。全員が「ゆかいな仲間たち」の一員なのである。
ところで,昨今,日本が間違った方向にベクトルが向かっているように感じる。教育に関しても妙な方向に進みかけている。日本が危ない。教育が危ない。そして,子どもが危ない。この状況を憂えた3人がまたまた立ち上がった。中嶋洋一,田尻悟郎,菅正隆,そして,お笑い小畑壽を加えた何とも微妙な4人組。それを猛獣使いのごとく操る司会者松永淳子。さあ,『ゆかいな仲間たち』の第2弾の発信だ。(後略)
◇目次
刊行に寄せて(髙橋 一幸)
はじめに(菅 正隆)
1章 日本の教育にもの申す! 特別座談会
菅 正隆・中嶋 洋一・田尻 悟郎・小畑 壽・松永 淳子(コーディネーター)
1節 昨今の日本の教育
2節 昨今の英語教育の課題
3節 他教科から見た英語教育の怪
4節 小学校の英語教育
5節 中学校の英語教育
6節 高等学校の英語教育
7節 大学の英語教育
8節 入試について
9節 教科書・教材・教具
10節 指導力を向上させる術
11節 英語力を向上させるには
12節 13年経った「ゆかいな仲間たち」秘話
2章 「ゆかいな仲間たち」からのメッセージ
1節 人の優しさに触れる(菅 正隆)
2節 研究授業をするに当たって(田尻 悟郎)
3節 「当たり前」と考えられる「空気」を作ろう!(中嶋 洋一)
4節 「ゆかいな仲間たち」とジョイントトーク(小畑 壽)
5節 「ゆかいな仲間たち」との13年(松永 淳子)
6節 臨時定員増の実員化-指名打者から先発メンバーへ-(久保野 雅史)
おわりに
―充実した教員生活を送る秘訣―(田尻 悟郎)
―Edutainmentを目指そう―(中嶋 洋一)
著者紹介
学力向上を保証する探究学習
知識注入の思想から授業成立条件を探る
編著者佐藤正一郎
編著者佐藤正一郎
定価2750円(本体2500円+税10%)
発行日2014/08/25
体様 A5判、282ページ
発行元 日本文教出版
ISBN 978-4-536-60075-0
社会科の新しい使命
「小学社会」のめざすもの
編著者的場正美、池野範男、安野功
編著者的場正美、池野範男、安野功
定価2200円(本体2000円+税10%)
発行日2013/11/01
体様 A5判、196ページ
発行元 日本文教出版
ISBN 978-4-536-60062-0
教科: 社会
社会科の新しい使命
これを堅持しながらも“社会的な見方・考え方の成長”を通して,“よりよい社会の形成に参画する資質や能力の基礎”を育てる新時代の社会科の理論と実践を提起します。
もくじ
序 章 座談会 変わる社会科をどう教えるか
~社会科と問題解決学習~
第1章 『小学社会』と問題解決学習(的場正美)
第1節 問題解決学習とは,どのような学習なのですか。
第2節 問題解決学習における「問題」とは,どのような問題なのですか。
第3節 問題解決学習における「解決」とは,どのような状態なのでしょうか。
第4節 授業でどのように子どもを生かせばよいのでしょうか。
第5節 問題解決学習に適した教材を,どのように開発すればよいのでしょうか。
第6節 まとめ
第2章 『小学社会』における「社会的な見方・考え方」の成長(池野範男)
第1節 『小学社会』がいう「社会的な見方・考え方」とは,どのようなものでしょうか。
第2節 社会的な見方・考え方」はどのように設定するのですか。
第3節 「社会的な見方・考え方」の設定と,問題解決学習とはどのように関連しているのですか。
第4節 「社会的な見方・考え方」の成長とは,どのような段階への到達を想定しているのですか。
第5節 「社会的な見方・考え方」によって培われる「公共性」とは,どのようなものですか。
第6節 まとめ
第3章 『小学社会』の基本的な考え方をふまえた実践のあり方(安野功)
第1節 基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させるには,どうすればよいでしょうか。
第2節 思考力・判断力・表現力等を育てるには,どうすればよいでしょうか。
第3節 社会の形成に参画する資質や能力の基礎を育てるには,どうすればよいのでしょうか。
第4節 社会科における評価をどのように進めればよいのでしょうか。
第5節 まとめ
社会科の新しい使命
これを堅持しながらも“社会的な見方・考え方の成長”を通して,“よりよい社会の形成に参画する資質や能力の基礎”を育てる新時代の社会科の理論と実践を提起します。
もくじ
序 章 座談会 変わる社会科をどう教えるか
~社会科と問題解決学習~
第1章 『小学社会』と問題解決学習(的場正美)
第1節 問題解決学習とは,どのような学習なのですか。
第2節 問題解決学習における「問題」とは,どのような問題なのですか。
第3節 問題解決学習における「解決」とは,どのような状態なのでしょうか。
第4節 授業でどのように子どもを生かせばよいのでしょうか。
第5節 問題解決学習に適した教材を,どのように開発すればよいのでしょうか。
第6節 まとめ
第2章 『小学社会』における「社会的な見方・考え方」の成長(池野範男)
第1節 『小学社会』がいう「社会的な見方・考え方」とは,どのようなものでしょうか。
第2節 社会的な見方・考え方」はどのように設定するのですか。
第3節 「社会的な見方・考え方」の設定と,問題解決学習とはどのように関連しているのですか。
第4節 「社会的な見方・考え方」の成長とは,どのような段階への到達を想定しているのですか。
第5節 「社会的な見方・考え方」によって培われる「公共性」とは,どのようなものですか。
第6節 まとめ
第3章 『小学社会』の基本的な考え方をふまえた実践のあり方(安野功)
第1節 基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させるには,どうすればよいでしょうか。
第2節 思考力・判断力・表現力等を育てるには,どうすればよいでしょうか。
第3節 社会の形成に参画する資質や能力の基礎を育てるには,どうすればよいのでしょうか。
第4節 社会科における評価をどのように進めればよいのでしょうか。
第5節 まとめ
ご購入について
当サイトでは販売は行っておりません。書籍のご購入をご希望の方は、 全国の書店、またはamazon等のオンライン書店にてお買い求めください。